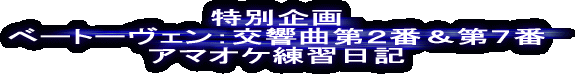
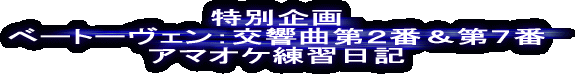
2013年 7月21日(日)午後2時開演
市川市文化会館大ホール
(入場無料)
ベートーヴェン:交響曲第2番
ベートーヴェン:交響曲第7番
指揮:小田野 宏之
市川交響楽団
2013年7月21日(日) 本番当日
10時より、ベト2のリハーサル。良くまとまっているとは思うのですが、第2楽章はマエストロの求める音楽とオーケストラの間で、まだ開きがあるようです。入念に確認が行われていました。ベト7は、昨日からの好調を維持。ここ数回の練習で、飛躍的に仕上がりが良くなったと思います。
14時に定刻通り開演しました。ベートーヴェンの交響曲第2番。降り番なので、客席で聴いていました。マエストロが求めるバランスの良いサウンドと、見通しの良い音楽。本番ならではの緊張からか、少し堅いサウンドに感じましたが、なかなかの好演。ラストの盛り上がりも、胸にぐっとくるものがありました。この曲は練習から本番までずっと安定した演奏でしたね。素晴らしい。
後半は、ベートーヴェンの交響曲第7番。第1楽章。練習の時よりマエストロが若干テンポを落としたように感じましたが、リズムも正確に響き、安定した演奏でした。第2楽章。弦楽器の安定さが際だっていました。特に低弦は素晴らしかった。ずっとこの楽章のこの弦楽器の響きに浸っていたい・・。そんな風に感じながら演奏していました。
第3楽章。昨日のGPから急成長した楽章です。ここはリズムが決まれば、あとはノリでいけます。これまでの練習で、このリズム感をオケの中で共有できていないように感じられ、とても辛かった。でも、今日はそれが出来て清々しい気持ちでした。
第4楽章。第3楽章のノリの良さをそのまま持続し、これまでで一番良い演奏だったと思います。マエストロの予告通り「狂う」ところでは、オケが一斉に狂い、何よりも最後の一音までメンバー一人一人のベクトルが同じ方向を向いていたことに、感動をしました。過去に熱演は何回かありましたが、皆のベクトルが揃ったことがあったかどうか、記憶にありません。そのくらい特別な演奏でした。お客様の反応も素晴らしく、正に演奏者とお客様が一体になった希有な演奏会だったと思います。
これもマエストロのご指導の賜です。的確な指摘で一切無駄のない練習。これではオーケストラも上達する以外に道はないでしょう。また何度も客演していただき、是非ベートーヴェン・チクルスを完成させたいです。(終わり)
2013年7月20日(土)
前日のGPです。毎回GPの時には、今までの練習環境と大きくことなり、自分の音や周りの音が違って聞こえ演奏がしにくいものですが、今日は珍しく周りの音が良く聞こえ、演奏しやすかったです。驚きました。オケの並びのせいでしょうか、それとも曲のせいでしょうか。
前半はベト2。こちらは相変わらずの順調な仕上がりです。後半はベト7。先週まで仕上がりが心配でしたが、今日は急にまとまってきました。ベト7の特徴であるリズムが、ここにきてようやくオケ全体で共有されつつあります。特に第3楽章は、見事な進歩です。
明日の本番が楽しみになってきました
2013年7月13日(土)
マエストロ練習ですが、急用ができ、練習に参加することができませんでした。
2013年7月6日(土)
練習指揮者による練習です。会場は贅沢にも本番で演奏するホールでした。
前半は降り番のベト2。部分的にしか聴けませんでしたが、いい感じでまとまっていると思います。少なくとも、曲の雰囲気を掴んでいる演奏でした。
後半はベト7。こちらは少し不安の残る内容でした。第2楽章は曲の雰囲気が出ていて、良いと思います。しかし、第1楽章と第4楽章は、頑張れば2週間後には曲の雰囲気を掴めるかも、という印象。第3楽章は、ほとんど崩壊してました。テンポは各人バラバラ、1括弧と2括弧の違い(デクレッッシェンドがあるかないかの区別)がまるで表現されていません。あちゃー!
来週はマエストロ練習です。どこまで精度を上げられるか・・。
2013年6月30日(日)
日曜日のマエストロによる特別練習です。
前半は、交響曲第7番。第1楽章、序奏はとても良くなりました。楽章全体で足りないのは、曲の雰囲気に合った自然なノリ、だけだと思います。頭で一生懸命理解しようとしているのを、心で自然に感じるようになれば、全ての問題が解決するように思います。第2楽章は、とても良いと思います。第3楽章は、残念ながらまだまだですね。生き生きとした雰囲気がでていないように思います。重いですね。
後半は、交響曲第2番。降り番ですが、セカンドを代奏しました。大分ベートーヴェンの雰囲気が感じられるようになりました。良いですね。この調子、この調子。
練習中にマエストロが、「ベルリンフィルのパユとウィーンフィルのシュルツ、どちらが好きか」という質問をされました。個人的にはサーカス的な演奏をするパユと、力づくで吹くシュルツのどちらも好きではないなあ、と思っていたら、マエストロが「本当は昔のウィーンフィルのトリップが好きなんだけど・・」とおっしゃっていたことに、激しく同意です。出しゃばるような演奏をすることはありませんが、不思議と存在感のある、素晴らしいフルート奏者。まさにオーケストラプレーヤーの鏡だと思います。
おすすめの演奏は、1975年にNHKホールで演奏された、ベートーヴェンのレオノーレ第3番。数年前に過去の映像でHNKで放送された映像を見たのですが、あの演奏に私は鳥肌がたち、トリップにはまりました。
2013年6月29日(土)
マエストロ練習です。
前半は、交響曲第2番。演奏が難しい曲だとは思いますが、それでもこのオケにとっては第7番よりとっつき易いのかな、と思います。今日は第4楽章が中心でした。全体的な音楽の方向性が揃ってきた故でしょうか、今度は細かい音程やフレーズ感のズレが気になり始めました。そういう場面はあるものの、感触としてはとても良いと思います。
後半は、交響曲第7番。第2楽章は、とても良くなりました。特に弦楽器の響きが良くなったと思います。しかし、第4楽章はかなり問題ありですね。まだ散らかっている感じがします。一生懸命演奏をしているが、この楽章に必要なパッションが感じられません。各人が目の前の音符の処理に追われていて、ベクトルが揃っていないことが一因かもしれません。オーケストラで一つの火の玉になれるような演奏がしたいものです。ちょっと残念。
2013年6月22日(土)
管楽器の分奏です。
本日も残念ながら練習に参加することができませんでした。
2013年6月15日(土)
マエストロ練習です。
急用ができ、残念ながら練習に参加することができませんでした。どんな練習だったのか、気になるところです。
2013年6月8日(土)
管楽器の分奏です。
前半はベト7。第1楽章を中心に練習をしました。第1楽章は、どの作曲家も気合いをいれて書くため、演奏しがいがある反面、難しく感じます。実際、この楽章は全体練習でもかなり手こずっています。
しかし今日の練習で、練習を始めた4月頃と明らかに変わったことがあります。それは、各人がより良いサウンドやフレーズへと修正するスピードが上がったことです。この前向きの姿勢、素晴らしいではないですか!来週のtuttiでその成果を発揮したいものです。
後半は降り番のベト2でした。
2013年6月1日(土)
今回のマエストロ、小田野先生による初めての練習です。
前半はベト2。降り番なので、後ろで聴いていました。第1楽章こそ緊張をしていたようですが、第2楽章以降は聴いていて、とても楽しい演奏でした。細かなことはまだまだ修正する余地はありますが、もっと聴いていたい!と思わせる雰囲気がありました。これまでの練習指揮者による密度の濃い練習が功を奏し、とてもいい雰囲気でした。マエストロも終始ご機嫌。また、演奏するためには、楽譜を読み込むことと同時に、作曲当時の時代背景を知ることが重要であることを、再認識。分かってはいるけど、ついつい目の前の音符に追われてしまっている、今日この頃です。
後半はベト7。爽やかなベト2とは対照的で、しつこいリズムが肝になる曲です。出だしのマエストロのテンポ感が素晴らしく、演奏していてドキドキしましたね。流れるようなテンポで、ffの世界へと自然と誘われるかのような気分になりました。指揮ぶりも一切無駄がなく、演奏を止めて口頭での指示も的確。一言でオーケストラの演奏がぐっと良くなる場面もありました。
充実した練習時間。この調子で本番の演奏会へ向けて頑張りたいと思います。
2013年5月25日(土)
ベト2、ベト7の練習指揮者によるtuttiです。
前半は、ベト2。降り番ですので、聴いていました。前回までは、ベト7よりベト2の方が、このオケには合っているのではと思っていましたが、今日は苦労していましたね。特に第2楽章と第3楽章は、曲の雰囲気を掴むのが難しそうでした。目の前のパーツを組み立てるのに必死で、パーツとパーツを組み合わせることが、なかなか出来ないでいるようです。練習回数が増えていけば、きっと良くなるでしょう。
それにしても、この曲のクラリネットの扱い方は面白いですね。木管楽器の仲間ではなく、ホルンやトランペットとほぼ同じ扱いをされています。スコアを見ていると、木管群の中に周りと馴染まないラインが1本あって、少し飛び越えた金管群と馴染むような楽譜を見ることができます。
後半は、ベト7。第1楽章が一番難しいかな・・。もう少し時間をかけて練習したいですね。第2楽章は、指揮者のテンポ感が素晴らしく、感動しました。演奏をしていて、とても力が入りましたね。第3楽章は、ff、f、pの区別をもっとつけないと、聴いている方が飽きてしまいます。第4楽章は体力勝負。ペース配分が重要になります。
来週は、初マエストロ練習です。
2013年5月18日(土)
管楽器の分奏、ベト7です。
今日の練習で感心したのは、これまで練習指揮者が指摘した大事な事を、皆がかなり意識しながら演奏をしていたことです。とてもうれしかった!例えば、ffとsfの違いです。当たり前ですが、この区別を意識していない演奏は、ベートーヴェンらしくなりません。第4楽章の最後では、皆がヘロヘロになるまでベートーヴェンを表現しようとしていた姿に感動をしました。
その他、1st同士のユニゾン等、各々の微妙なタイミングのズレを調整したり、とても有意義な時間でした。本番のマエストロがどんな要求をしても、何とかそれを消化し表現しようとする準備はできたようです。
2013年5月11日(土)
練習指揮者による、ベト2&ベト7のtuttiでした。
まずベト2。1番フルートを代奏しました。第1楽章に、たっぷり80分もかけました!指揮振りも言葉での説明も、とても説得力があり、特に弦楽器へのアドバイスは素晴らしいですね。オーケストラのレベルが、急に1段階あがったように感じます。自らも弦楽器を奏で、また他のオケで見聞きしたボーイング等の豊富な知識は、とても魅力的です。いつか、本番の演奏会でも振ってほしいものです。
また、練習指揮者、という立場を自覚した振る舞いにも、好感がもてます。自らの考えを持ちながらも、決してそれを押しつけず、他の指揮者はこうこう、と色々な解釈を披露されます。
休憩後は、ベト7。んー、今日も、やっぱりこのオケはベト7が苦手なのでは、と思いました。いまひとつ、この曲独特のリズムにのりきれていないように感じます。少し不安ですが、時間をかければ何とかなるかもしれません。辛抱。
2013年5月4日(土)
今週の練習は、弦楽器分奏のみとなり、お休みです。
2013年4月27日(土)
練習指揮者によるベト7&ベト2のtuttiでした。
前半はベト7の第4楽章。今日はまるでベートーヴェンとは何たるか、という授業を受けているようでした。セクションごとに分解し、音符一つ一つの感じ方、それを出すための奏法と、とても細かい練習内容。30分経過しても、まだ出だしの数小節しか、練習が進んでいませんでした。充実した練習にうれしさを感じる反面、まだまだ基礎的な演奏能力が足りない、と感じています。
休憩後はベト2。こちらは降り番ですので、演奏に邪魔にならない距離で聴いていました。マエストロは、ベト2は9つの交響曲の中でも最も難しい、とおっしゃっていました。しかし、演奏を聴いて、ここのオケにはベト7よりベト2の方が向いているのでは、と思いました。ベト7ほど体力を使わないからでしょうか!?
2013年4月20日(土)
練習指揮者によるベト7、tuttiでした。しかも、本番と同会場、大ホールでの練習です。
楽章順に、キーになるフレーズやリズムを重点的にとりあげ、曲を少しずつ作り上げていきました。棒を見ていれば何をこちらがすればいいのかが手に取るように分かり、言葉での説明では一言一言に納得をさせられました。素晴らしい指揮者です。また別の機会に、この指揮者による演奏会があればなあ、と思いました。
今日の合奏で印象に残ったのは、ベートーヴェンが使用していたメトロノームについての説明です。使っていたメトロノームが狂っていたので、よくベートーヴェンが楽譜に書いたテンポ指示はあてにならないと言われます。しかし、今日の説明では、狂っていたにせよ、曲の中での相対的なテンポ感は間違いではない、ということでした。納得!!
こういう内容の濃い練習が続きますように。
2013年4月13日(土)
今日は第7番の練習、管楽器の分奏でした。ベートーヴェンは一つ一つの音符の重みが違います。例えば、マーラーでは、なんとなく雰囲気で誤魔化せる場面もありますが、ベートーヴェンはそうはいきません。全ての音符に神経を張り巡らせながら、音程・リズム・フレーズ、等に細心の注意を払う必要があります。
そういう意味でも、分奏の練習はとても有効です。今日の練習でも、特に第7番の特徴であるリズムについては、大きな収穫がありました。いつも重要だと分かりつつ、つい忘れてしまいがちの休符の存在。これをどう感じるかで、発する音が良くも悪くもなります。
実に良い練習でした。
2013年4月6日(土)
バレエの連続公演が終了し、7月21日のベートーヴェンの演奏会へ向けて、練習が始まりました。交響曲の第2番と第7番の2曲プロです。
今日は第2番のみの練習で、私は折り番なのでお休みです。聞くところによると、とてもよいトレーニングを受けたそうで、充実した練習だったようです。見に行けば良かったなあ。
これまでの特別企画
・No.35 モーツァルト「魔笛」&ワーグナー「指輪」 アマオケ練習日記
(2012年10月、12月、12月)
・No.34 マーラー:交響曲第1番「巨人」 アマオケ練習日記
(2012年7月)
・No33 ベートーヴェン:交響曲第9番「合唱」 アマオケ練習日記
(2012年4月)
・No32 カヴァレリア&ドヴォルザーク8番 アマオケ練習日記
(2011年11月・12月)
・No31 サン=サーンス:交響曲第3番「オルガン」 アマオケ練習日記
(2011年6月・7月)
・No30 ベートーヴェン:交響曲第9番「合唱」 アマオケ練習日記
(2011年2月)
・No29 ブラームス交響曲第1番&箏協奏曲初演 アマオケ練習日記
(2010年12月)
・No28 ティル・オイレンシュピーゲル&英雄の生涯 アマオケ練習日記
(2010年7月)
・No.27 コープランド&バーンスタイン&ガーシュイン アマオケ練習日記
(2009年12月)
・No.26 メンデルスゾーン生誕200年プログラム アマオケ練習日記
(2009年7月)
・No.25 ヴェルディ「レクイエム」 アマオケ練習日記
(2009年2月)
・No.24 ムソルグスキー:組曲「展覧会の絵」アマオケ練習日記
(2008年12月)
・No.23 ブルックナー交響曲第7番 アマオケ練習日記
(2008年7月)
・No.22 天地創造&シンデレラ&チャイ5アマオケ 練習日記
(2007年12月)
・NO.21 ベートーヴェン:交響曲第3番「英雄」アマオケ練習日記
(2007年7月)
・No.20 ショスタコーヴィチ:オラトリオ「森の歌」アマオケ練習日記
(2007年2月)
・No.19 コダーイ「ハーリヤーノシュ」アマオケ練習日記
(2006年12月)
・No.18 マーラー交響曲第2番「復活」アマオケ練習日記
(2006年7月)
・No.17 歌劇「カルメン」&「バラの騎士」組曲
アマオケ練習日記
(2005年12月)
・No.16 ツェムリンスキー交響詩「人魚姫」 アマオケ練習日記
(2005年7月)
・No.15 マテキフルート工場見学記
(2005年4月)
・No.14 Ph.ハンミッヒ木管フルート ノマタチューンナップ記
(2005年2月)
・No.13 ベートーヴェン交響曲第9番「合唱」 アマオケ練習日記
(2005年2月)
・No.12 新世界より&キャンディード アマオケ練習日記
(2004年12月)
・No.11 ロイヤルコンセルトヘボウ管弦楽団2004年日本公演レポート
(2004年11月)
・No.10 幻想交響曲&ラヴァルス アマオケ練習日記
(2004年7月)
・No.9 ハイドン交響曲全104曲 完全制覇日記
(2003年11月より)
・No.8 イスラエルフィルハーモー管弦楽団2003年日本公演レポート
(2003年12月)
・No.7 シカゴ交響楽団2003年日本公演レポート
(2003年10月)
・No.6 マーラー交響曲第5番アマオケ練習日記
(2003年7月)
・No.5 ギルバート・キャプラン
(2002年8月)
・No.4 月に1度はコンサートへ行こう企画2001年総括
(2002年3月)
・No.3 ウィーンフィルハーモニー管弦楽団2001年日本公演レポート
(2001年10月)
・No.2 マーラー交響曲第3番アマオケ練習日記
(2001年7月)
・No.1 ベルリンフィルハーモニー管弦楽団2000年日本公演レポート
(2000年11月)