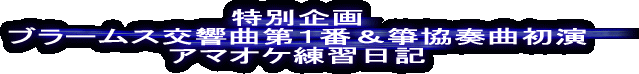
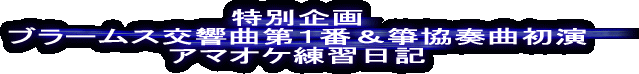
�Q�O�P�O�N�P�Q���T���i���j�ߌ�Q���J��
�s��s������ّ�z�[��
���c�m��F�u���V���v
�i�nj��y�łQ�O�O�U�j
��ˈ��FⵂƊnj��y�ɂ�鋦�t���@�`�莙�ޓ`���ɂ悹�ā`
�i�s���U�O���N�Ϗ���i�E���E�����j
�u���[���X�F�����ȑ�P��
���ꖳ��
�Ƒt�F�|�V�x�q�iⵁE�\�����E�́j
�w ���F ��@����
�s������y�c
�i�I�����܂����j
�Q�O�P�O�N�P�Q���T���i���j�@�ŏI��
�@�{�ԓ����ł��B
�@�P�O������́u�u���P�v�̃��n�[�T�����O�Ɋy������B�u���P�A�\��ł͂P���Ԃł������A��Q���Ԃ����Ă����Ղ���K�����܂����B�܂������I�Ɋm�F������K�łP���ԋ��A���̌�A�S�Ȓʂ����K���s���܂����B�����Ɍ����Ȃ�S�Ȓʂ����Ƃ͋H�Ȃ��Ƃł����A���t����I����������v���A���ꂪ�g�Əo���Ǝv���܂��B���̗��K�Ŏw���҂ƃI�P�Ƃ̉�b���X���[�Y�ɂȂ�A�悤�₭���t����}���鏀�����������ƁA�q�ȂŒ����Ȃ��犴���܂����B
�@�o�`�����̌�A�uⵋ��t�ȁv�̃��n�ł��B�����Ȃ��Ȃ��E�E�E�B��l��ⵂƏ\���������t�A�����ĉS�܂ł���܂��B�I�P��ⵂƂ̉��ʓI�o�����X�́A�S�Ăo�`�ő���B�ł��̂ŁA���̂�����͒ʏ�̋��t�Ȃ�艉�t���₷���Ɗ����܂����B
�@��������Ղ莞�Ԃ��g�����u���V���v�͏o�����������K���A���I���B�A���R�[���́A�w���҂��H�v���Â炵�A�ƂĂ��y�������o�ɂȂ�܂����B���[���A�����Ԃ��Ȃ��J��̎��Ԃł��I
�@�@
�@�@�u���[���X�̔M�̂����������n�[�T��
�@���H���}���łƂ�A�ݑ܂��c��܂ܕ��䑳�ɑҋ@�B�ߌ�Q���A�\��ʂ�J�����܂����B�P�Ȗڂ́u���V���v�B�o�����̒����̔��ʉ����̋����A�����ă��B�I���̃����f�B���ƂĂ��������܂��ď�X�̏o�����ł����ˁB�f���炵���W���́B���̎��_�ō����̉��t��͐�������A�Ɗ����܂����B�����u���X���̃R�[�h�i�s���A���������߂̃T�E���h�Ńo�b�`���B�I�n�����ɐi�݁A�u�a�ƃ^���S�v�������͕\���ł������ȁA�Ǝv���܂��B���t�I���Ɠ����ɁA�}�G�X�g�����q�Ȃɂ����ȎҁA���c�m�����X�e�[�W�ɌĂсA�p�`�p�`�p�`�p�`�B
�@�Q�Ȗڂ́uⵋ��t�ȁv�B�y��̃Z�b�e�B���O�Ɏ��Ԃ������邽�߁A���̊Ԃ̓}�G�X�g���̃}�C�N�p�t�H�[�}���X�̎��Ԃł��B����܂��q�Ȃɂ����ȎҁA��ˈ�������X�e�[�W�ɌĂсA�C���^�r���[�J�n�B��Ȃ��˗����ꂽ�o�܁A��Ȃ����邽�߂ɐ^�Ԃ̒n��K�ꂽ���ƂȂǁA�Ȃ̃l�^������Ȃ����x�ɂ��b������܂����B�Z�b�e�B���O�I����A���t�J�n�B�P�ȖڂɈ��������A���̋Ȃ��W���͂̂��鉉�t�Ŏn�܂�܂����B�r���A�؊NJy��ɂ�鏬���̂�������Ȃǂ́A�{�Ԃ������K�̎��ƈقȂ�^�C�~���O�Ŋe�X�̊y�킪��A������Ƃт�����B��莩�R�ȕ��͋C�i�H�j�A�Ƃ������Ƃŗ������܂��悤�B
�@�\���X�g���f���炵�������I���Ɏ㉹�ł̉��t�ƉS�́A�g�k��������قǂł����B���q�l���A�������N�����Ă���낤�A�Ƃ����\������Ȃ��璮�������Ă��܂����ˁB�y�������߂Č����Ƃ�����D��ۂ̋Ȃł������A����͍Ō�܂ŕς��܂���ł����B�܂����̋Ȃ��A�����\���X�g�ʼn��t�ł�����A�Ǝv���܂��B
�@�x�e��A���C���́u�u���P�v�ł��B���̓t���[�g�����܂��A�s�b�R�������������āA�q�ȂŒ����Ă��܂����B��P�y�́A�o�����̔ߑs���Y�������f�B�A�}�G�X�g�����I�P���C���������Ă��܂����ˁB�}�G�X�g���́A���������T�E���h��]��ł����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�����͑S�v���O�����A�o���������ł��I��Q�y�͂́A�Ƃɂ��������������B�\���E���@�C�I�����{�I�[�{�G�{�z�����̃����f�B�A�ō��I
�@��R�y�͂́A���y��ƊNJy��̃o�����X���ǂ��A�y�������y�ɂȂ��Ă����Ǝv���܂��B�����đ�S�y�́A�z�����ƃt���[�g�̊|���������I���A�L���ȃ����f�B���o�Ă������ɂ͈��S��������܂����ˁB���O�܂Ŋ댯�n�т��������K�ԍ��m�̂U���ߑO����́A�{�Ԃł͓�Ȃ��i�H�j�N���A�ł��B�����āA�R�[�_�ւƓ˂��i�ލ��g���́A���̋Ȓ���Ԃ̊����ł����B�Ȃ��I����ۂ┏�芅�т��N�������Ƃ́A�����đ傰���ł͂Ȃ������Ǝv���܂��B
�@�}���ŋq�Ȃ��畑�䑳�ɖ߂�A�A���R�[���̏����B�Ȃ́A���x����ȁu�����{�v�B���x���́u�{�����v���t���ɉ��t����Ƃ������̂ł��B�������牉�t���n�܂�A���t���I������l���珇�Ԃɋq�ȂɎ��U��Ȃ���X�e�[�W������A�Ƃ������o�t�ł��B�Ō�͍ĂуX�e�[�W�ɏオ��A���q�l���X�^���f�B���O�I�x�[�V�����Ō}���Ă���āA���t�͉X�����I���I�}�G�X�g���H���A�r�n�r�iStanding
Ovation System�j�������ł��B
�@�ł��グ�ł́A�}�G�X�g���Ə����������b���o���܂����B�b��́A�O�P�W��ȁu�[�w�̍Ձv�ɂ��āB�}�G�X�g�������C�ɓ���̋Ȃ̂悤�ŁA�ǂ������I�i�I�j
�Q�O�P�O�N�P�Q���S���i�y�j
�@�O���̂f�o�ł��B
�@����݉c��A�v���Ԃ�́u���V���v������K���n�܂�܂����B���炭�I�P���K�����Ă��Ȃ������̂ŁA�������ꂽ���y�ɂȂ��Ă��܂��܂����B���A���K���Ԃ������Ղ�Ƃ����̂ŁA���̋Ȃ̓����ł���A�u�a�{�^���S�v���������v���o����Ă����悤�ł��B�����ăA���R�[���B�F�X�Ǝ�����Â炵�Ă��܂��B�y���݂ł��B
�@���Ɂuⵋ��t�ȁv�B�ʏ�̃I�P�̉��t��ł͂��܂茩�邱�Ƃ��Ȃ��o�`�̃Z�b�e�B���O�ɁA�R�O���ȏォ����܂����B���Ȃ��|����ł��ˁBⵂƏ\�����̂Q��̊y�����ׂāA�}�C�N�����ꂼ��Z�b�e�B���O�B�y������炷�ƁA����ƈꏏ�Ƀ}�C�N�����炷�B���Ԃ�������܂��B���K�͂܂��܂��A�Ƃ������Ƃ���ł��傤���B
�@�Ō�́u�u���P�v�B��S�y�̗͂��K�ԍ��m�̂U���ߑO������W���I�ɁA���x�����K�����܂����B�x���̊��������A�w���҂ƃI�P�ň�����悤�ł��B�܂��܂����S���ł͂���܂��A�q�ȂŒ����Ă��āA���������������鉉�t�ɂȂ��Ă��܂����B
�Q�O�P�O�N�P�P���Q�V���i�y�j
�@�{�ԂP�T�ԑO�́A�}�G�X�g�����K�ł��B
�@�܂��́A�A���R�[���B������ƂP��ʂ��A���Y�����̉��y�I�Ȋ������̃A�h�o�C�X������܂����B�����Ƃ����ԂɏI���B
�@���Ɂuⵋ��t�ȁv�B��Ȏ҂ƃ\���X�g�̗���̂��ƁA�I�[�P�X�g���݂̗̂��K�ł����B����ȂƂ͂����A�ƂĂ�������₷���Ȃł��B�s���a���Ŗ��ߐs�����ꂽ�Ȃł͂���܂���B�ł�����A���R�n�[���j�[�̔�������v������܂��B������]�v�ɓ���E�E�E�B�Z�p�I�Ȕ\�͂ʼn����ł��鎖�́A�啪�o���Ă���Ǝv���܂��B��́A�Z�p�ʼn����ł��Ȃ�������������K�v������܂��B
�@�Ō�̓u���[���X�B��T�Ɠ��l�A�܂Ƃ܂��Ă��Ă���Ǝv���܂��B��͖{�ԂȂ�ł͂̏W���͂������A�Ǝv���܂��B
�Q�O�P�O�N�P�P���Q�O���i�y�j
�@�}�G�X�g�����K�ł��B
�@�O���́A�\���X�g���}���Ă�ⵋ��t�ȁBⵂ����Ă���̂͊y�����B�V�N�Ɋ����܂��B���t�́A���_��������B
�@�㔼�́A�u���[���X�B�܂Ƃ܂��Ă͂��Ă���Ǝv���܂��B�����Ă���l��������������ɂ́A������H�v�K�v��������܂���B
�Q�O�P�O�N�P�P���P�R���i�y�j
�@�O���́Aⵋ��t�ȁB��ȉƗ���̉��A�I�[�P�X�g�������ŗ��K���i�݂܂����B�r�����x���~�߂Ȃ���A��Ȏ҂��v���`�����ʂ�̉��t�ɂȂ��Ă��邩���m�F�B�������߂Â��Ă���悤�ł����A�܂�������������Ȃ��͗l�B�����ĉ����̐������Ȃ���ʂł̉��t���A���萫�Ɍ����Ă���悤�Ɋ����܂����B
�@�㔼�́A�A���R�[���̏����K�B�����̋Ȃ̏��Ԃ����ւ��āA���ǂ݂����܂����B�m���ƃn�T�~�Ŋe�X���쐬�����y���̂��߁A�ׂ����Ƃ���̒����͕K�v�ł����A����͂����Ƃ܂Ƃ܂�ł��傤�B
�Q�O�P�O�N�P�P���U���i�y�j
�@�{�Ԃ܂ŁA�P����������܂����B�����́A�NJy��̍��t�ł��B
�@�O���́A�u���V���v�B�������x���Q���ł����̂ŁA�y������O�ɒg�߂��A�܂��`���[�j���O�����t�����Ȃ��璲���������̂ŁA����Ƃ̃A���T���u�����Ƃ��܂Ŏ��Ԃ�������܂����B�Ȃ��̂��̂͂���قǓ�Փx�������Ƃ͎v���܂��A�S�ʓI�ɉ��t�ɒ��J��������Ȃ����ȁA�Ɗ����܂����B�f�B�~���k�G���h�̂������Ɖ��̏I���̏����A������ƂȂ郁���f�B�ł̃A�N�Z���g�̏����A���B�����̂悤�ɁA���ߍׂ����w�����Ă���������̂́A���t�̂����Ƃ��낾�Ǝv���܂��B�ƂĂ��L�Ӌ`�ł����B
�@�㔼�́A�uⵋ��t�ȁv�B�����ł�����A�Q�l�ɂȂ�b�c���͂���܂���̂ŁA���̋Ȉȏ�ɁA�y����ǂݍ��ޕK�v������Ɗ����܂����B��P�y�͂̎莙�ނ�����������ʁi�T�W���ߖڈȍ~�j�ł́A�A�����鉹�^�̒��ł��A����|�C���g�ɒ��ڂ���ƁA����w���̌`���N���A�ɂȂ锭��������܂����B�܂��A�����������f�B���t�ł���R�Q���ߖڈȍ~�ł́A�P���ڂ̋��ǂ̃n�[���j�[���ƁA��莩�R�ɓ��邱�Ƃ��o���܂����B��́A�㉹�ł̉��̈��萫���ۑ�ł��ˁB
�Q�O�P�O�N�P�O���R�O���i�y�j
�@�}�G�X�g�����K�ł��B�����͐��肾������B�O���͍~��Ԃ̃u���[���X�̑�Q�E��R�y�́A�������͂��ł��B�x��������A�ʎ��ʼn����������Ă����̂ŁA�قƂ�ǒ������Ƃ��o���܂���ł����B�����A�ʎ��Ɏ��X�����R��Ē������Ă��܂����B������ƁA�������������J��Ԃ��ė��K�����Ă����悤�ł��B�\���̃j���A���X�𑵂��Ă����̂�������Ȃ��ł��ˁB
�@�㔼�́A�u���V���v�B�v���Ԃ�̗��K�ŁA���̋Ȃ̊��o��Y�ꂩ���Ă��܂����B�s�b�R���̃s�b�`�̂Ƃ�����A�t���[�g�̃s�b�`�̂Ƃ���ʼn��t���Ă��܂��A��Q�āB�r������C�����A�Œ���̕����������ł����A�ǂ����������E�E�E�B���̋Ȃ́A���Y���ɂ̂��ĉ��t�ł��邩�ǂ����A�������Ǝv���܂��B�u���[���X�ɔ�ׂ�ƁA�����Ԃ̗��K�͕K�v�Ȃ��Ǝv���܂����A���Y���́u�m���v��Y�ꂸ�ɉ��t�ł���A�W�O�����炢�͊������Ă���悤�Ȃ��̂ł��傤�B�����́A�����܂ł͎��炸�B
�@�\��ł́A���̂Q�Ȃł������A��Ȏ҂�ⵂ̃\���X�g�������邱�ƂɂȂ����̂ŁA�}篁A�V���ⵋ��t�Ȃ̗��K���lj��ɂȂ�܂����B�����ƂP��ʂ������ł������AⵁE�\�����E�́A������ƁA���͋C���ς��܂��ˁB�w���҂̘e�ɁAⵂƏ\�������k���^�ɕ��ׁA�����ڂ��s�ςł����B�r���Aⵂ����R�ɉ��t�����ʂł́A�������Ă���낤�ƌ������Ă��܂��A�������ǂ������t���Ă��邩������Ȃ��Ȃ��ʂ��B���������l�́A�ǂ����l�����ł͂Ȃ������炵���E�E�E�B
�@�Ō�ɍ�ȎҎ���A���̋Ȃ��ǂ������C���[�W�ł������̂��A����������܂����B�s��̘̐b�u�^�Ԃ̎莙�ށi�Ă��ȁj�v���ނɁA�莙�ނ䂩��̒n�����ۂɑ����^��ł݂Ă����C���[�W�A���̃C���[�W���Ȓ��łǂ��\���������A���B��ȉƂɒ��ژb����̂́A�������Ƃł��ˁB�u���[���X��}�[���[�ł́A�����͂����Ȃ��ł�����B���Ȃ݂Ɏ莙�ނƂ́A�u���t�W�ɉ̂�ꂽ�����ŁA�����̒j���ɕ�����A�N�Ɋ��Y�����Ƃ��Ȃ��A�^�Ԃ̓���]�ɐg�𓊂����Ɠ`������`���̃q���C���v�i�ȏ�@�s��s�̂g�o���]�ځj�A�ł��B
�@��[�A���t�����������q�Ȃł������蒮���Ă��݂����E�E�E�B
�Q�O�P�O�N�P�O���Q�R���i�y�j
�@�}�G�X�g�����K�ł��B�O���́A�V���ⵋ��t�ȁB��P�y�͂͂�������ƁA��Q�E��R�y�͂͂�����ƒʂ��܂����B��P�y�͂́A�������I�[�P�X�g�������̗��K�ł������A�y�������t�ł��܂����B���ɒ��ԕ��A�Î�̒��ł̒������̖������v�킹��V�[���B�J���o�Ԃ������A��r�I���R�ɉ��t�ł���̂������ł��ˁB�}�[���[�������ł����A�I�[�P�X�g���Ƃ����g�̒��ŁA�ꎞ�I�ɑt�҂����R�ɊJ�����Ă����̂��C�ɓ����Ă��܂��B�����ⵂ���������A�ǂ�ȋȂɂȂ�̂��낤���B�y���݂ɂȂ��Ă��܂����B��Q�E��R�y�͂́A�����̗��K�ł́A�܂��S�̑��������܂���B����ɁA�t���[�g�̎㉹�ł̕\���ŁA���K�����Ȃ�K�v�ȉӏ���������܂����B
�@�}�G�X�g���̎w���́A����ȂƂ����W�������̂������A�������蔏��������悤�ȐU����B���Ȃ���S�^�]�ł��B
�@�x�e��̓u���[���X�B������2nd�t���[�g���t���܂����B�{�Ԃł͉��t���܂���̂ŁA���̋@��ɂ�������y���݂܂����B�u���[���X�ł́A���߂ă}�G�X�g���ƌ��������܂������A�S�g���g���ĂȂ�Ƃ��t�҂Ɏ����̃C���[�W��`���悤�Ƃ���}�G�X�g���̓w�͂ɂ́A�E�X�ł��B
�@�u���[���X���āA�{���ɓ���B1st�t���[�g���t�������قǂł͂���܂��A���Â������ɂ̓u���[���X��\������v�f�̌��Ђ�������Ă��Ȃ��Ȃ��A�Ɗ����܂��B���̂܂܂ł́A�w�L�т��ăn���K���[���ȁA�V���t�H�j�[�Ɏ���o���͔̂��Ɋ댯�ȏ�Ԃł��B�A�[�����B
�Q�O�P�O�N�P�O���P�U���i�y�j
�@�O���́Aⵋ��t�ȁB��T�͕��t�ł����̂ŁA�����̓I�[�P�X�g���S�̂ł́A�����t�ɂȂ�܂��B�Ȃ̑S�̑������ނ̂͏������Ԃ������肻���ł����A�Z�p�I�Ȃ��ƂɌ��肷��A����قǓ�Փx�͍����Ȃ��Ǝv���܂��B�S�ȗ��K�����܂������A�l�I�ɂ͂������ʂ�ǂ������Ă��邾���ŁA�ǂ������Ȃ��́A�܂��C���[�W���킫�܂���B
�@�㔼�́A�u���[���X�B�~��Ԃł����A�Ō�܂Œ����Ă��܂����B��S�y�͂Ƒ�P�y�͂������Ղ�Ɨ��K���܂����B���K���n�߂ĂP�����Ə��X�B����Ƃ̘A�W���A�������ł͂���܂����A�A���T���u�����o���Ă���ӏ��������Ă���悤�Ɏv���܂��B�u���[���X�炵���A�Ƃ������ƂɂȂ�ƁA����ɗ��K���K�v�ɂȂ�Ǝv���܂����A����̍��t�Œi�X�Ɛ������Ă����ߒ����q�ϓI�Ɋy����ł��������Ǝv���܂��B
�Q�O�P�O�N�P�O���X���i�y�j
�@�NJy��̕��t�ł��B
�@�O���́A���̂P�Q���̉��t��̂��߂ɍ�Ȃ��ꂽ�Aⵋ��t�Ȃ̏����K�ɂȂ�܂��B�a�y��Ƃ̃R���`�F���g�́A����قNjȂ������Ȃ��Ǝv���܂��̂ŁA�ƂĂ��M�d�Ȍo���ł��ˁB�\����ⵁA�\�����A�̂̂R������܂����A�X�R�A������ƑS�Ĉ�l�ŒS������悤�ł��B
�@���āA�������ǂ݂ł��B�o�����́A�؊NJy��ɂ��O�\�����̗��ɂ��₪��B�y��ɂ���Ă͘Z�A���ʼn��t���Ă���p�[�g������܂��̂ŁA���Ȃ��悤�ɁA��������Ɣ��𐔂���K�v������܂��B���ꂪ�o����A���Ƃ��N���A�ł������ł��B�S�Ȓʂ��܂������Aⵂ̃\�����Ȃ��ƁA�������悭�킩��܂���B�\��������̂͗����̗\��ł��̂ŁA����܂ł͐h�������Ȃ�������Ă����܂��B
�@�㔼�́A�u���[���X�̌����ȑ�P�ԁB�����́A1st���t���܂����B���ʂ͎S�邽����̂ŁA�܂�ŗ��K�ɂȂ�Ȃ������ł��ˁB�ז����������ŏI����Ă��܂��܂����B����͖{�Ԃ̃X�e�[�W�ɏオ��l�ł����̂ŁA�{���ɐ\����Ȃ��B�E�E�E��������ŁA�u���[���X�Ƃ̋���������ɂT�V���L�тĂ��܂��܂����B
�Q�O�P�O�N�P�O���Q���i�y�j
�@�O���́A�u���V���v�B�������ɂȂ����̂́A���Y���̊������B�P�R�`�P�U���ߖڂɂ����āA�����ĂP�R�V�`�P�S�O���߂̃p�^�[���ł��B�y���𐳖ʂ��猩�Ă��܂��ƁA�ǂ����Ă��P���ځ{�Q���ڂłP�u���b�N�A�R���ځ{�S���ڂłP�u���b�N�ɂȂ��Ă��܂��܂��B������Q���ڂ̗������R���ڂɂȂ���C���[�W�����ƁA���܂ł̊��o�Ƃ͈Ⴄ�A��������Ƃ������y�ɂȂ����悤�ȋC�����܂����B�����������y�̑�����������ƁA�q�ȂŒ������Ă��鉹�y���A���Ȃ�̈Ⴂ���o�Ă���̂��Ǝv���܂��B
�@�㔼�́A�u���[���X�B��Q�E��R�y�͂��P���Ԕ��A��������Ɨ��K���܂����B�q�Ȃ��猩�w�B����Ƃ̘A�W�A����ɗ����ꂸ�Ɏw�����������茩��Ƃ���ȂǁA�|�C���g�ʂɎw��������܂����B��Q�y�͂͑e���Ȃ�����A�ƂĂ��������������鉉�t�ł����B���オ�y���݂ł��B��R�y�͂́A�����܂ŏ������Ԃ������肻���B��Q�y�͂̂������Ƃ����O���q�̋C���������̂܂܂ɁA��R�y�͂̓q�����t���Ă��镵�͋C�����܂��B�ł��A�y�͂��ƂɋC�������X�p�b�ƕς���ꂽ��A���I�ɕω����邩������܂���B
�Q�O�P�O�N�X���Q�T���i�y�j
�@���̃}�G�X�g�����K�ł��B�O��̏o���́A�Q�O�O�X�N�P�Q���̃A�����J�E�v���O�����ŁA�Q�N�A���Q��ڂɂȂ�܂��B����̃v���O�����́A�O��Ƃ͎�̈قȂ�A�a���{�h�C�c���ł��B�}�G�X�g�����ǂ̂悤�ɑf���炵�����y�ւƓ����Ă���邩�A�y���݂ł��B
�@���C���̃u���[���X����B�q�ȂŒ����B��P�y�͂̑O���́A�I�[�P�X�g���̃G���W�����Ȃ��Ȃ������炸�A�������邢���y�ɂȂ��Ă��܂����B�������A�}�G�X�g�����`�́u�V���|�V���|�̑��v���s���ƁA����s�v�c�A���悭�͂������ăI�[�P�X�g���炵���T�E���h�ɑ�ϐg�B����ɂ͋����܂����ˁB�y�͑S�̂̃e���|�̓T�N�T�N���Ɛi�ފ����ŁA����Ă����܂����B��Q�y�͂́A�����Ղ�Ƃ����I�[�\�h�b�N�X�ȉ��t�B�o���������߂́A�ƂĂ��������������Ă����Ǝv���܂��B
�@��R�y�͂́A�w���҂ƃI�P�ł��Ȃ�e���|���̃Y��������A�ƂĂ��`�O�n�O�ł����B�e���|�����łȂ��A�t�_�̊��������M���b�v�����肻���B��S�y�͂���R�y�͂Ɠ�����ۂł��B�����K�Ƃ������Ƃ�����܂����A�w���҂̉��߂��I�P�w�i�~��Ԃ̎����܂߂āj�̗\�z�ƁA���Ȃ�Ⴄ���Ƃ��͂����肵�Ă��܂����ˁB�ӊO�ȂƂ���ŋ}�u���[�L������������A�t�ɓ˂��i�ނƂ���Ńe���|����肾������ƁA�����̃u���[���X�ł����B�����A�ŏI�I�ɂ͂ǂ̂悤�ɂ܂Ƃ܂�̂ł��傤���B
�@�㔼�́A�u���V���v�B�w���҂ƍ�ȉƂ��m�荇���ł��邱�Ƃ��琶�܂ꂽ�I�ȁB�}�G�X�g���H���A�u�����v�ł��B������̓u���[���X�Ƃ͕��͋C���Ⴂ�A���̉�H���ւ���K�v������܂��B�}�G�X�g�����Ȃ̖{���𗝉����Ă��邩��ł��傤�A������ƂĂ�������₷���A�I�[�P�X�g���̉��t����X�������Ǝv���܂��B���̒��q�ł�����Ƃ����ł��ˁB
�@�u�U�N�v����u�V���[��p�U�N�v�ւ̕ω��B�X�s�[�h���R�{�B�ڂ������������ցB
�Q�O�P�O�N�X���P�W���i�y�j
�@�����͌��y��̓��B�NJy��͗��K������܂���ł����B
�Q�O�P�O�N�X���P�P���i�y�j
�@�~��ԁi�\��j�̃u���[���X����B��P�y�͂͂������莞�Ԃ������āA��Q�E��R�y�͂͂�����Ɨ��K�����܂����B�����͋q�ȂŒ����Ă��܂������A�܂��e���ł��ˁB���K���n�܂��ĊԂ��Ȃ��̂ŁA����͓��R�ł��B�ł��A���X�s�^�b�Ƃ͂܂鏊������A�v�킸���������Ă��܂��u�Ԃ�����܂����B
�@�l�I�ɂ̓u���[���X�́A���t����̂��ł������ȉƂ̈�l���Ǝv���Ă��܂��B�u���[���X�炵���E���͋C���o���̂�����ł���ˁB���̍�ȉƂ����t�Ŋy���߂�悤�ɂȂ�����A�I�[�P�X�g���̓J�����i��̃��x���Ŋy���߂�悤�ɂȂ�̂��Ǝv���܂��B�������A�u���P�͑O��i�P�X�X�S�N�j��1st�A�V�A����͍~��ԁi�\��j�Ƃ������ƂŁA���܂艏���Ȃ��悤�ł��B
�@�㔼�́A�u���V���v�B�ւɂ�B�I���B
�Q�O�P�O�N�X���S���i�y�j
�@�V����R.�V���g���E�X�Â������I���A�~�̉��t������ė��K���ĊJ���܂����B�v�X�̃I�[�P�X�g���ł킭�킭�B�O���́A���c�m���ȁu���V���v�B���X�́A�Q�O�O�S�N���t�y�R���N�[���̉ۑ�Ȃł����A����͊nj��y�p�ɕҋȂ��ꂽ���̂����t���܂��B�������I�Ȃ��Ǝv���܂��B
�@�ۑ�Ȃɂ��ď����B�����g�R���N�[���ɏo�Ă����̂͂ق�̐��N�Ԃł��̂ŁA���̉ۑ�Ȃ��悭�m���Ă���킯�ł͂���܂��A���������t�������Ƃ̂���ۑ�ȂŁA�ł��v���o�Ɏc���Ă���Ȃ́A�P�X�W�W�N���O�P�W��ȁu�[�w�̍Ձv�ł��B�t�@�S�b�g�̃\���Ŏn�܂�A�ϔ��q�����������ŏo�v�B�r���P�ӏ������S���̂R�D�T���q���������Ǝv���܂��B�u�t�̍ՓT�v���v�������ׂȂ���A�y�������t�����v���o������܂��B�Z�p�I�ȓ�����������邾���łȂ��A�Ȏ��̂���ϖ��͓I�ŁA�O�P�W�̑��̍�i���������������ɂ��Ȃ�܂����B����́u���V���v�͏��߂ĉ��t���܂����A���i�nj��y�ł͉��t����Ȃ����͋C�̋Ȃ��y���݂����Ǝv���܂��B
�@���āA���K�ł��B�����x��ĎQ�������܂����B����ɂ��čs�����A�܂���������������Ă���̂���������Ȃ���Ԃŗ��K���I����Ă��܂��܂����B���[���[���[���[�B�t���[�g�Ƃ͈Ⴄ�s�b�R���̃s�b�`�̂Ƃ�����A��������Y��Ă��܂����B������A������B
�@�㔼�̓u���[���X�̌����ȑ�P�ԁB�~��ԁi�̗\��j�ł��̂ŁA�����͗��K�������ɋA��܂����B
����܂ł̓��ʊ��
�ENo28�@�e�B���E�I�C�����V���s�[�Q�����p�Y�̐��U�@�A�}�I�P���K���L
�i�Q�O�P�O�N�V���j
�ENo.27�@�R�[�v�����h���o�[���X�^�C�����K�[�V���C���@�A�}�I�P���K���L
�i�Q�O�O�X�N�P�Q���j
�ENo.26�@�����f���X�]�[�����a�Q�O�O�N�v���O�����@�A�}�I�P���K���L
(�Q�O�O�X�N7���j
�ENo.25�@���F���f�B�u���N�C�G���v�@�A�}�I�P���K���L
�i�Q�O�O�X�N�Q���j
�ENo.24�@���\���O�X�L�[�F�g�ȁu�W����̊G�v�A�}�I�P���K���L
�i�Q�O�O�W�N�P�Q���j
�ENo.23�@�u���b�N�i�[�����ȑ�V�ԁ@�A�}�I�P���K���L
�i�Q�O�O�W�N�V���j
�ENo.22�@�V�n�n�����V���f�������`���C�T�A�}�I�P�@���K���L
�i�Q�O�O�V�N�P�Q���j
�ENO.21�@�x�[�g�[���F���F�����ȑ�R�ԁu�p�Y�v�A�}�I�P���K���L
�i�Q�O�O�V�N�V���j
�ENo.20�@�V���X�^�R�[���B�`�F�I���g���I�u�X�̉́v�A�}�I�P���K���L
�i�Q�O�O�V�N�Q���j
�ENo.19�@�R�_�[�C�u�n�[�����[�m�V���v�A�}�I�P���K���L
�i�Q�O�O�U�N�P�Q���j
�ENo.18�@�}�[���[�����ȑ�Q�ԁu�����v�A�}�I�P���K���L
�i�Q�O�O�U�N�V���j
�ENo.17�@�̌��u�J�������v���u�o���̋R�m�v�g��
�A�}�I�P���K���L
�i�Q�O�O�T�N�P�Q���j
�ENo.16�@�c�F�������X�L�[�������u�l���P�v�@�A�}�I�P���K���L
�i�Q�O�O�T�N�V���j
�ENo.15�@�}�e�L�t���[�g�H�ꌩ�w�L
�i�Q�O�O�T�N�S���j
�ENo.14�@Ph.�n���~�b�q�؊ǃt���[�g�@�m�}�^�`���[���i�b�v�L
�i�Q�O�O�T�N�Q���j
�ENo.13�@�x�[�g�[���F�������ȑ�X�ԁu�����v�@�A�}�I�P���K���L
�i�Q�O�O�T�N�Q���j
�ENo.12�@�V���E��聕�L�����f�B�[�h�@�A�}�I�P���K���L
�i�Q�O�O�S�N�P�Q���j
�ENo.11�@���C�����R���Z���g�w�{�E�nj��y�c�Q�O�O�S�N���{�������|�[�g
�i�Q�O�O�S�N�P�P���j
�ENo.10�@���z�����ȁ������@���X�@�A�}�I�P���K���L
�i�Q�O�O�S�N�V���j
�ENo.9�@�n�C�h�������ȑS�P�O�S�ȁ@���S���e���L
�i�Q�O�O�R�N�P�P�����j
�ENo.8�@�C�X���G���t�B���n�[���[�nj��y�c�Q�O�O�R�N���{�������|�[�g
�i�Q�O�O�R�N�P�Q���j
�ENo.7�@�V�J�S�����y�c�Q�O�O�R�N���{�������|�[�g
�i�Q�O�O�R�N�P�O���j
�ENo.6�@�}�[���[�����ȑ�T�ԃA�}�I�P���K���L
�i�Q�O�O�R�N7���j
�ENo.5�@�M���o�[�g�E�L���v����
�i�Q�O�O�Q�N�W���j
�ENo.4�@���ɂP�x�̓R���T�[�g�֍s�������Q�O�O�P�N����
�i�Q�O�O�Q�N�R���j
�ENo.3�@�E�B�[���t�B���n�[���j�[�nj��y�c�Q�O�O�P�N���{�������|�[�g
�i�Q�O�O�P�N�P�O���j
�ENo.2�@�}�[���[�����ȑ�R�ԃA�}�I�P���K���L
�i�Q�O�O�P�N�V���j
�ENo.1�@�x�������t�B���n�[���j�[�nj��y�c�Q�O�O�O�N���{�������|�[�g
�i�Q�O�O�O�N�P�P���j