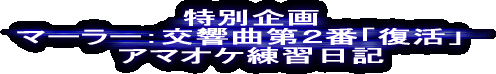
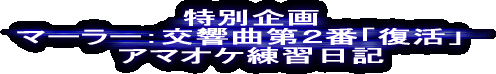
2006年7月17日(月・祝)午後2時開演
市川市文化会館大ホール
マーラー:交響曲第2番ハ短調「復活」
指揮:金洪才
市川交響楽団
(終了いたしました)
7月17日(祝)
いよいよ、20年間の夢が実現する日です。朝9時に楽屋に入り、楽器を組み立て早速音だし。これはここ数年間、続けている習慣です。このぐらい早くホールに着いていないと、落ち着かないんですよね。今日は、朝一でオルガンの設置作業がありました。ここのホールは、パイプオルガンがないのが残念。なかなか立派なコンソール(というのかな?)だと思います。鍵盤部分と、スピーカーの写真です。
10時30分よりリハーサル開始。楽章ごとに一度通した後、部分的に確認がありました。ここでも、少しずつ良くなっていっているなあ、と感じました。私も各楽章、いくつか確認をする箇所がありましたので、きちんと合奏の中でそれができるかどうか、調整をしました。ここ2日間、マエストロと息の合わなかった合唱前のナイチンゲールのソロ、今日はきちんとお互いの意思の疎通が出来ているように感じました。これでひと安心です。
今回の演奏会は色々と仕掛けが多いので、昼飯を少し早目に終わらせ、写真を撮っておくことにしました。まずは、上手・下手に分かれたバンダです。
左の写真が上手のバンダ席。トランペット4本と、Cis音にチューニングされたティンパニです。右の写真が下手のバンダ。ここでは、ホルン4本と大太鼓などの打楽器です。一部、トランペット2本がこちらで演奏するようですね。こういう仕掛けは、ライヴならではの楽しみだと思います。
バンダに気を取られ、舞台に乗り切らない打楽器を撮影するのを忘れていました。過去数日の練習の写真で、打楽器は散々撮影したので、それでご勘弁を。言葉だけで状況を書こうと思います。
まずは、ティンパニ。一人あたり4台ですので、それが2セットで合計8台。狭いスペースに強引に2セット配置しているため、一旦叩く位置につくと、そこから出るのに楽器をどかさないと出られないという、とてもいい環境とはいえない状況でした。そして、3つのカリヨン。これは、なかなかスペースをゆったりと(!?)とっていたようです。おかげで、カリヨンとカリヨンの間のスペースにグロッケンが置かれ、楽器と楽器の間から撥が伸びてきてグロッケンを叩いていたようです。大太鼓やシンバル等は、笑うに笑えないほどコンパクトにまとめられていていました。ここまでは何とかステージにセットされていましたが、大小2つのドラにいたっては、場外の花道に・・・。
打楽器さん、申し訳ないです。でも、管楽器もかなりスペース的に苦労しました。本来、指揮者の正面に来るはずのフルート&オーボエの1番、今回はめちゃくちゃ上手によっていて、フルート&クラリネットの3番が指揮者の正面でした。おかげで、フルートへの指揮者のサインが3番フルート(私)にくるし、ピッコロ(私)へのサインは下手にセッティングされているホルンに出されるし・・・。コールアングレにいたっては、もう少しで舞台裏に行ってしまうところでした・・・。最後に、開場直前の舞台の写真を掲載します。
さて、開演時間の14時。ステージに上がってみて、あまりのお客様の多さにびっくりしました。1階席は、ほぼ満席。2階席も、どんどん人が入っていく様子が見えました。後から聞いた話しですが、用意していたプログラムがなくなってしまい、急遽コピーをとりに走ったそうです。これだけ多くのお客様がいると、こちらの気持ちも自然と高まります。
第1楽章。マエストロの最初の一振りは、いつもよりも力強さを感じました。オーケストラもとても落ち着いていて、堅実な演奏だったと思います。一方私は、いつもならステージに上がって最初の一吹きをすると、気持ちが落ち着くのですが、この日は違いました。ずっと緊張をしていました。
第2楽章。この楽章のオーケストラの安定感は、抜群だったと思います。その証拠に、マエストロの指揮もカウントだけでなく、なんと表情豊かな振り方だったこと!おそらく、ルバート等をかけても、オーケストラは崩れない、と感じたのでしょう。この楽章になっても、私は緊張感から開放されませんでした。いつもなら間違えたことのないところでミスをしたり、Fl+Picc+Hpでタンギングをミスしてしまったり、と色々問題がありました。ここで、15分間の休憩です。
合唱とソリストが入場して、第3楽章が始まりました。もっとも技術的に難しい楽章、緊張の10分間です。順調に進んでいきましたが、練習中何度となく苦しんだ正にその場所で、アンサンブルが崩れてきました。私の緊張度はさらに増しましたが、徐々に立て直し、元の安定したアンサンブルに戻りました。通常3ヶ月の練習で1つの演奏会、短い時は1ヵ月半で演奏会をむかえます。今回は、通常の2倍の6ヶ月間を練習にあてました。どのような事故が起こっても、その練習量の多さで事故をカバーできたのではないでしょうか(強引なプラス思考?)。んー、練習量の多さって、偉大ですね。
アタッカで第4楽章へ突入。アルト独唱による、月光です。本当に美しく、いい曲ですね。実はこの日、ソプラノとアルトの2人のソリストは弦楽器と木管楽器の間、つまり私の目の前で歌ったのです。これこそ特等席!もしかしたら、私が最もこの歌声を楽しめたのかもしれません(!?)。
これまたアタッカで、嵐のような第5楽章が始まりました。出だしタイミングも、バッチリでしたね。第2楽章の後の休憩が良かったのか、あるいは各々が体力を温存していたのか分かりませんが、どのパートもさらにパワーアップして演奏しているような気がいたしました。打楽器のロールによる地獄の扉以降、行進曲風のテーマの演奏を聴きながら、私は今日の演奏会が成功することを、確信しました。このころ、ようやく私の緊張感がほぐれてきたのですが、今度は興奮から手に震えが・・。私がソロを演奏する前に必ず行う、トーンホールの水滴取り。クリーニングペーパーを挟もうとしても、手の震えでなかなかうまくいきませんでした。つまり、今日は1曲通して、一度も落ち着くことがなかったのです。
合唱前のシーン。私にとっては、今日一番の見せ所です。興奮で震える手で、なんとかトーンホールをクリーニングし、演奏が始まりました。マエストロとの呼吸も、ピッタリだったと思います。ただ、私のイメージしていたものと比べると、本番で表現できたのは80%くらいだった、と思います。まだまだ、練習量や練習方法に問題があるのでしょうね。まあ、失敗したとは思っていないので、よしとしましょう。舞台裏のバンダも、この会場では午前中1回の練習だけでしたが、よくあそこまでアンサンブルができたなあ、と感心しました。
合唱が入り、オーケストラがそれ応える。ソリストの歌声から再び合唱に引き継がれ、音楽は一気にクライマックスへ!オルガンも加わり、オーケストラの合唱も更にパワーアップ!極めつけは、マエストロの唸り声でした。まるでコバケンのような唸り声!相当気合が入っていたのでしょう。本当に素晴らしい一体感のある演奏、そしてお客様からの暖かい拍手。最高の瞬間です。終演後、合唱好きの友人、マーラー好きの友人、そして約15年ぶりに再会した友人に会いました。皆さんそれぞれ楽しんでいただけたようで、良かったです。
贅沢な6ヶ月の練習期間、スコアどおりの贅沢な楽器を揃え、オーケストラメンバーの熱意、そして最高の指揮者によるマーラー復活。個人的とはいえ、こういった形で自らの夢を実現できたこと、心からうれしく思います。しばらくは、この余韻に浸っていそうです!(完)
・トップへ戻る
7月16日(日)
前日のゲネプロですが、いつものようにホールは使えず、昨日と同じ場所での練習になりました。いつものように、第1楽章から順番に練習を開始。各楽章、ポイントを押さえていくような感じの合奏でした。本番前日の最終チェックです。問題の第3楽章、今日になって少し明るい兆しが見えてきたように感じました。明日はもっと良くなることを期待したいと思います。
ゲネプロ終了後、夜間になってホールで舞台の設営のみ行いました。昨日心配した舞台のスペース、やはり狭すぎて全ての楽器が収容し切れませんでした。それなりにステージの広いホールだとは思っていたのですが、復活となると話は別です。こうなると、舞台上以外でも、空いているところは全て楽器置き場、と割り切るしかありません。
明日はいよいよ本番。20年間、想い続けていた夢の実現です。
7月15日(土)
今日から17日までの3日間、復活づけの毎日です。今日も復活、明日も復活、そしてあさっても復活。いよいよ練習も大詰めです。何はともあれ、今日の主役に登場していただきましょう。
ご覧のとおり、カリヨンです。先週までは、チューブラーベルだったはずですが、急遽カリヨンになったそうです。音もいいのですが、なによりもこの見た目、存在感です。ただでさえステージに所狭しと並んでいる打楽器、さらにスペースをとる楽器が登場してしまい、本番のステージ内にきちんと収まるのか、ちょっと心配。2年前の幻想交響曲の時もカリヨンを使いました。でも、その時は、舞台裏に設置し、かつベルの向きが上下逆の楽器でしたね。
もちろん、カリヨンだけでなく、練習もきっちり行われました。基本的には、各楽章いけるところまで通して、その後部分的にかえすというやり方。そうですね、先週よりも部分的に細かな指示が多かったように感じました。それもいつも以上に、ニュアンスがでるまで繰り返しての練習。そういうところは、以前とは全く次元の異なるサウンドが生まれるので、本当に不思議です。マエストロは、魔術師か!?
最も難しい第3楽章、今日も苦戦をしました。先週よりは、落ち着いてきて形が出来つつあるところもあります。でも、演奏をしていて不安が消えないのです。参りましたねえ・・・。まだ練習する時間はあります。落ち着いて、練習していくしかないですね。
第5楽章の合唱前のナイチンゲールのソロ。スコアも読んで、他のパートの動きや音を確認をしていたつもりでしたが、私が1箇所勘違いをしていることに気がつきました。そのため、私のソロの前後で少しぎこちなさを生じる(感じる)所が・・。でも、帰宅をしてからスコアを見直したので、私のスコアの読みが正しいかどうか、明日の合奏でもう一度確認をしようと思います。
7月9日(日)
日曜日の特別練習。今日はマエストロ練習で、全楽章行われました。これまでのマエストロ練習で、全5楽章を1回ずつ通し、おおよそどんなテンポで曲が進行するのか、イメージができました。これからは、各楽章をより深く、マエストロのイメージするマーラーになるように、練習をしていきます。本番まで、あと1週間。また今日は、下の写真のように、ハープも楽譜どおり2台入りました。ついでに、足元のペダルの部分も撮影。
楽章順に、練習が進みました。まずは、第1楽章。出だしの弦の嵐のようなトレモロ、ここへのアドバイス1つで、完全にマエストロのマーラーの世界に引き込まれました。まるで別のオーケストラのようなサウンドが、目の前に繰り広げられたのです!とてつもないショックを受けてしまいました。ほんのちょっとのアドバイスで、ここまで変わるとは・・。
ここの冒頭について、具体的にどういうアドバイスをしたかについては、んー、書くのをやめておきます。弦のボーイングとか、管楽器のブレスの位置・フレーズの感じ方などは、時にはその指揮者やオーケストラにとって、財産と言えるような価値があるのでは、と私は思っています。もし将来、私がG.キャプラン氏のように、この復活を指揮する機会があれば(!?)、その時にちょっと披露してみようかなあ・・・。
続いて第2楽章。この楽章もマエストロによるアドバイスで、整えられていきました。第1楽章とはあまりに対照的な、冒頭ののどかなメロディ。素晴らしい表情です。ここもマエストロのアドバイスで、いい方向に変わってきました。私が少し目立つ、Picc+Fl+Harpのユニゾン。今日初めてハープが入ったことで、少し感じが変わってきました。ピッチももう少し合わせられるといいですね。というか、ハープは演奏中にピッチコントロールはできない(と思う・・)でしょうから、管楽器が調整をしなければならないでしょう。ここで、お昼休み。
午後は、第3楽章から練習を開始しました。ティンパニのフォルテシモの始まりで象徴されるように、この楽章は特に打楽器が活躍します。今日も上の写真のように、ずらっと打楽器が並びました。楽器がそろっても、この楽章は本当に難しい。他のパートの方に聞いても、そう感じている方がいらっしゃいます。そして、今日はマエストロからも、全楽章中この第3楽章が一番難しい、との言葉が。そう感じているのは私だけではないようです。少しほっとしました。ほっとしても、その難しさは変わらないので、やはり練習はしなければ・・・。
聴いているだけだと、とてもユニークな曲。しかし、演奏するとどうして難しく感じるのか、少し考えてみました。おそらく、この楽章のリズムやアンサンブルの感覚が他の楽章とは大きく異なり、かつ自分の体の中に、そういうリズム感が存在していないのでは、と思います。本番1週間前になっても、突破口が見ません・・・。
第4楽章は、今日はアルト独唱がいないため、さっと流して終了。そして合唱を加えた第5楽章。舞台裏のバンダも、それぞれ上手・下手に分かれて、マーラーのスコアの指示どおりに配置されました。きちんと楽器が揃った中での練習、マエストロの熱い指揮をみていると、演奏をしているこちらも熱くなってきます。オーケストラだけのところは、ほとんど止められることなく、練習が進んでいきました。いい曲ですねえ、復活は。単純で明快、そしてかっこいい。
練習後は、合唱が出る前のソロの掛け合いの指揮の見かたについて、2箇所ほどマエストロに確認をしました。その後はまっすぐ帰宅。長時間にわたる練習でしたが、とても心地よい疲労感です。
7月8日(土)
第1、第2、第3楽章の練習。特に書くことはありません。明日の日曜日も練習があるので、早く寝ます。
・トップへ戻る
7月1日(土)
今日は木管楽器とホルンによる分奏です。分奏は久しぶりで、3月18日以来になります。本番2週間前に分奏を行うことで、もう一度楽譜を細かくチェック。次回以降の合奏に向けて、いい練習になりました。
第1楽章より、リズム&音程の徹底チェック。マーラーの付点のリズム、オーケストラ全体の合奏で目立つところは大分形になってきました。が、全体合奏では聞き落しがちなところは、今日の分奏でリズムの甘さが新たに発見されました。こういうところまできっちりさせておくと、オーケストラ全体のアンサンブルの精度が、ぐんと上がるのだと思います。
第2楽章の個人的に少し目立つ、Picc+Fl+Hp。ここは、3つの音にそれぞれ「強・中・弱」の意識をもつことがポイント。ただし、1拍目が2泊目・3泊目より音域が低い場合、1泊目に「より強い」意識を持たないと、バランスが取れないことを今日の練習で確認をしました。
第3楽章。全体的に音楽の感じ方に問題がありました。もちろん3拍子の曲ではあるのですが、1小節をきっちり1・2・3ととらえるのではなく、1拍目を吹いたら後は流れにまかせるような、そんな感覚が必要な曲です。前回の練習で、ユーモラスな演奏になるまでには、まだ時間がかかる、と書きました。おそらく、こういうところの音楽の感じ方一つで、変わってくるのだと思います。
この楽章は、個人的に色々問題を抱えています。①練習番号30~31のPicc+Cl+Fg、②練習番号34のPicc+Str、③練習番号36のPicc+Fl、④練習番号55のPiccの発音、等々。③と④については、今までの練習を通して解決方法が分かってきました。後は、できるだけ高い確率でそれができるようになること。①と②は、まだ解決方法が見つかっていません。
時間の関係で第4楽章はとばして、第5楽章の練習。この楽章も第1楽章同様、付点のリズムがキーになります。練習をしていると、各々がこのリズムを相当意識をして演奏しているのがよく分かります。このリズムは、練習し始めの頃から散々注意を受けていました。それが、少しずつ実り始めているようです。
6月25日(日)
午前中から夕方まで、集中練習が行われました。全ての楽章を、かなり丁寧にさらいました。しかも、これまで2回行われたマエストロ練習のテンポ設定を意識した、有意義な練習になったと思います。また、下の写真にあるように、ティンパニ2セット+半セット(最大3人の奏者)、大太鼓、大小ドラ2組、チューブラベル等、打楽器が揃ったため、いつもと音楽の引き締まり方が違いました。常時、団にこれだけの物がそろっていればいいんですけどね。
第1楽章から練習を開始。ポイントは、やはり付点のリズムです。練習初めの頃に比べると、少しずつ良くなってきているように感じます。より多くの演奏者が、このリズムを意識することが出来ているのでしょう。マーラーの付点のリズムが完成するまで、もう少しです。その他の注意点は、他の楽器が何をしようと、自分のパート譜に書いてあることを信じること。他の楽器が弱音で演奏していても、自分のパート譜にフォルテの指示があれば、自身を持ってフォルテで演奏すること。この曲に限らず、マーラーではとても重要なことです。
第2楽章、雰囲気は出来てきているように感じました。練習番号12からのPicc+Fl+Harp。ここでの私の注意点は、それぞれ3つの音を吹くときに、「強・中・弱」の意識をもつこと。これをきちんと意識できた時は、うまくいっているように感じます。
午後は合唱団を加えて、第5楽章から練習が始まりました。合唱の出だしも、低音域が少しずつ安定してきているように感じました。オーケストラの方は、そうですね、以前にも書きましたが俊敏な動作を求められるところが、もう一歩かなあ、と。練習番号7~10、及び21~25といったところでしょうか。音楽自体は荒々しさが必要なところですが、頭ではしっかり理性を持ってカウントをしなければならない所。大きな難所の一つだと思います。
マーラーらしさの一つに、他の作曲家ではなかなか要求しない、通常はまず使わない音が出てきます。この曲のピッコロの場合、第五楽章の練習番号21の2小節目に、第4オクターブのDes音が出てきます。フルートでは近現代で時々要求されるのですが、ピッコロでは私は初めてお目にかかりました。ピッコロをミニ・フルートとお考えの方もいらっしゃるでしょうが(私は別の楽器だと思っています)、この辺の音域やトリルと言うのは、フルートとは指使いが違うものが多々あります。この音もフルートとピッコロでは指使いが違います。でも、こういうところで色々覚えていけるのですから、マーラーはいい勉強になります。
続いて、第4楽章。こういう曲(楽章)って、実際に演奏すると本当にその曲の良さが分かってきます。5年前に演奏した、マーラー3番の第4楽章も同じような雰囲気をもっていて、かつ同じアルト独唱の曲なのですが、その時も同じように感じました。なんて美しい曲なんだろう!
最後は苦手の第3楽章。今まで、私が演奏するピッコロの音量の小ささが問題になっていました。そこでちょっと実験。気になっている箇所で、これ以上ないほどの力(ほとんど理性なし)で吹いてみることに。結果は全く効果なし、というか逆効果であることが判明。リズムは壊すし、音量も上がっているわけではない。こんなことは2度としません。ピッコロさん、ごめんなさい。後は、こっそり自分専用のPAを使うか、どうやって解決していこうかなあ・・。
この第3楽章は、全5楽章の中でも最も難易度が高い楽章、と私は感じています。楽譜をきっちり演奏することはもちろん、その上でユーモアをも求められるからです。今日現在、まだ楽譜をおっている段階でしょうか。ユーモラスな演奏になるまで、もうしばら時間がかかりそうです。
6月24日(土)
今日の練習は・・・・、ありません。明日の日曜日、半日練習という変則日程で行われます。
6月17日(土)
オケの練習の前に、フルートのレッスンを受けてきました。曲は、Andersen
Op.21の13曲目。大体、2曲練習をしてくるのですが、今回はこの1曲のみ。1時間じっくりレッスンを受けました。
大体指の練習のエチュードが多いのですが、このNo.13はPastoraleの曲です。テンポを一定に吹くのではなく、時にはまいて戻し、時にはたっぷり歌って戻したりと、そういう練習をしました。そして、テンポを戻す1拍前がポイントになることも、師匠に教わりました。こういうのが自然と身につくと、もっと音楽的に演奏できるようになるんでしょうねえ。それはいつのことやら・・・。
さて、復活。今日はマエストロ練習です。前回は第1楽章から第3楽章まで練習をしましたので、今回は第4楽章と第5楽章の練習。ソプラノとアルトのソリストも、参加をしました。ソリスト合わせといっても、この楽章を金先生の指揮で演奏するのはオケも初めてですので、三者ともテンポの探り合いです。
マエストロのテンポ設定、今まで練習をしていたのとは違うところが多々ありました。ただ、マエストロの指揮を見ていると、次はこういうテンポでくる、というのが不思議と分かるように気がしました。今現在の音楽を指揮しているはずなのに、先の音楽の姿が読み取れるのです。恐るべしマエストロ!ですから、今まで何度もこのHPで書いてきた、ピッコロ+フルートと舞台裏の金管楽器のアンサンブルも、自然に吹けるのです。あ、これは少なくともPicc奏者自身が感じていることですけどね。周りにもそう聞こえていていることを願います。
余談ですが、ピッコロを吹く上で、演奏することと同じくらい大事なことがあります。それは、管内部の水滴をこまめに吸い取ることです。上の写真、ピッコロの裏側(手前)です。水滴を取らないと、こういう小さなキーの穴に水滴が入り、常にトーンホールがふさがった状態になってしまうのです。
例えば、H音からC音にあがる時、写真のど真ん中の大きなキーを離すとC音に切り替わるのですが、これが空かない状態になり、H音のままの状態に。フルートでは、ピッコロよりトーンホールが大きいので、こういうことは起こりにくいのですが、ピッコロでは日常茶飯事。強奏のトゥティであればいいのですが、大事なソロがある前は、必ずトーンホールに水滴が溜まっていないか、チェックをするようにしています。
6月10日(土)
合唱団を加えて、第5楽章と第4楽章の練習です。まず、第5楽章。オーケストラ自体はいつもと変わらない調子だったと思います。合唱団も、前回の練習より調子が上向いています。が、なぜか私自身が、今一つ合奏に集中できないでいました。体調が悪いわけでもないし、曲が嫌になったわけでもない。原因不明。
合唱前の舞台上の楽器と舞台裏の楽器とのアンサンブル。こちらは、集中できないなりに、なんとかまとまったと思います。毎回いろいろ試していることがあり、それが客観的に聴いても自分がイメージしたとおりになっているかを確認するため、MDで録音をしています。5月27日のレッスンで指摘された、四分音符を長く、三連符を短く、吹くこと。この点については、完成まで後少しです。四分音符を、自分がイメージしているよりも、もっと長く吹くことで解決しそうです。
どうにもならない問題が1つ。ピッコロの音量です。とにかく中音域での鳴りが足らなさすぎです。毎回のようにこのことは書いていますが、一向に解決策が見当たりません。書くことで自分にプレッシャーをかけ、解決するかと思っていたのですが、いよいよ限界か・・・。
合奏後は、珍しく飲んで帰りました。明日日曜日の朝、出かけなければならない用事があることを、すっかり忘れていました。しかも、少し頭を使う用事が。案の定、日曜日の朝起きたら、頭にお酒が残っていました。2日連続で、今ひとつ集中できず・・・。
・トップへ戻る
6月3日(土)
初のマエストロ練習、金洪才先生の登場です。2000年のブルックナー8番、2001年のマーラー3番に引き続き、3回目。今回のマーラー2番も、素晴らしい指揮振りを初日から披露してくれました。テンポ設定も明快で分かりやすく、一気にその世界に引き込まれました。
第1楽章、出だしからマエストロの気合の入った表情、オーケストラの状態もとてもいいですね。以前より合奏で指摘されていた、付点リズムのあまさ。マエストロもすぐにそれを指摘しました。やはり、マーラーではこのリズムはキモなのですね。そのリズムをはじめ、楽譜の隅々まで、今まで私が気がつかなかったことを、どんどん指摘してくれました。マエストロ、完全にこの曲を知り尽くしている・・・。熱い熱い第1楽章が終わったところで、休憩。
休憩後は、第2楽章。第1楽章同様、オーソドックスなテンポでした。オーケストラの細かい三連符の刻みも、きちんと落ち着いて演奏されいました。後半のフルート+ピッコロ+ハープの場面、今までよりも緊張感のある音楽がつくられたと思います。おそらく、演奏者が「pp、ppp」の音量を意識したからなのでしょう。楽譜をきっちり読むって、大事ですね。
苦手の第3楽章。オーケストラは、いつになくまとまっていました。とりあえず、音楽が崩れてしまう心配はなくなりました。あとは、ユーモラスさなどの表情付けでしょう。問題は、私個人でした。
①練習番号34のピッコロと弦との合わせ
②ピッコロ音量が全体的に小さい
①の問題はクリアされていたと思っていたのですが、まだでした。要するに、このフレーズに対する緊張感・緊迫感が、少し足りなかったようです。周囲と比較して、私の演奏がのんびりしていた、ということでしょう。ここの指摘は、マエストロに感謝です。②は、これは今のところ解決策が見当たりません。これ以上強く吹こうとすると、オーバーブローになってしまうからなあ・・。根本的な解決方法は、今回は取るつもりはないので、後は音の形とか音色で、何とかクリアしていかないと。
個人的には問題がありましたが、とてもいい合奏だったと思います。7月の本番には、きっといい演奏会になるのでは、と思わせるような練習でした。
5月27日(土)
オケの練習の前に、フルートのレッスンを受けてきました。曲は、Andersen
Op.21の11曲目と12曲目。11曲目は、2ヶ月前に1度レッスンを受けたもので、今日は1回吹いただけですぐに終了。でもこの曲、かなり吹きにくい(3月11日に楽譜の写真があります)。ほとんどの時間を、次の12曲目に割きました。
左の写真のように、跳躍の激しい曲です。前の曲程吹きにくくはないのですが、音楽の感じ方、特に1拍目のウェイトの置き方が問題でした。思い返してみると、このような曲を演奏する時に、毎回指摘されていたような気がします。つまり、跳躍ばかりに気持ちがいってしまい、肝心のメロディに対する意識がなくなってしまうことです。それでも、大きな問題点はそこだけでしたので、1拍目に意識を持つことで、すぐに解決をしました。この曲は、珍しく1回でパス。
残り時間で、復活のピッコロパートを2箇所ほど、教えていただいていただきました。そのうちの一つは右の写真の、合唱前の箇所です。たっぷり吹くか軽く吹くかで迷っていたのですが、どうも音符の長さの考え方が間違っていたようです。今までは客観的に聞くと、四分音符の長さが短く、逆に三連符が長すぎて間延びをしていました。それを、逆に四分音符をたっぷり、三連符を短めに、と師匠から指摘されました。なるほど、これで少し前進をしました。後は、オケの中で実践をできるかどうかの問題です。
さて、前置きが長くなりましたが、オケの練習です。今日は、初めて合唱との合わせです。初めは、お互いに探り合っている、というか違う環境でびっくりしてしまっている感じでした。時間が経つにつれて、お互いが何をやっているのかが分かり始めて、少しずつではありますが、近づいてきたような気がします。今日のところは、こんな感じでいいのでは。
個人的に問題の合唱前のシーン。録音を聞く限り、今までの中では最もよくまとまっていたように聞こえますし、私のピッコロもレッスンを受けたことを実践できているように感じました。ただ、他の楽器へのブリッジの時、具体的にはピッコロからフルートへ受け渡す時(右上の写真)、わずかに「空白の時間」が出来てしまっていることに気がつきました。ここは客観的に聞いてみると、集中力が途切れてしまいますね。演奏している時は、他の楽器への受け渡しを意識している箇所なので、自然にそういうことが起きてしまっているのかもしれません。意外と淡々と受け渡しをしたほうが、全体の演奏は自然に聞こえるのかな? 次回は、そのようにやってみたいと思います。
後半は、第1楽章の練習。うん、今までの中では1番良く出来たのでは。また1段階レベルが上がってきたように思えます。問題の付点のリズムも、場所によっては改善されてきていて、マーラーの音楽に近づいてきています。場所によっては、です。ですから、いまだに「ウサギのダンス」「盆踊り」の箇所もたくさんあります。出来ているところもあるのですから、意識さえきちんともっていれば、修正できるのでは、と思います。
5月20日(土)
今週もまた遅刻参加です。ふーっ。前半の第3楽章、第4楽章はさらっと終わってしまいました。途中参加をした私は、合奏に集中できず(気持ちを切り替えることができず)、何も考えることなく、何も感じることなく終了・・。でも、この遅刻参加は、おそらく今日で最後。次回から演奏会本番までは、フル出場できそうです。ようやく正常な状態に戻れます。
休憩後、第5楽章の後半からスタート。練習番号21から25までは、オーケストラにとってかなりの難所です。特に伴奏系の楽器は、理性をしっかりと持たないと、音楽の流れに乗り遅れてしまいそうな・・。おまけに、変拍子+バンダとのアンサンブルが、さらにここを難しくしているように感じられます。
さて、この楽章の私の難所の一つは、合唱がでる直前の箇所です。4月15日の合奏で空中分解を起こしてしまったため、今日は音楽の流れよりも、自分が入る箇所をきっちり見極めることに注意をはらいました。つまりレベルを1段階、落としたのです。まあ、やっぱり普通にやれば空中分解なんて起こらないですよね。次回からはレベルを元に戻して、音楽の流れをつくれるようにしていきます。
合奏前半は集中できなかったのですが、第5楽章の練習で、特に合唱ppで歌い終わったとのオーケストラの旋律を聴いたとたん、マーラーの音楽に入り込めました。20年間聴きつづけた曲ですが、何度聴いても素晴らしい曲です。
5月13日(土)
久々の復活の合奏。事前にしっかり練習していきたいなあ、と思っていたのですが、そう簡単にはいきません。今朝は午前4時に目覚ましが鳴り、車に乗り込み5時前に家を出る。途中千葉によって所用を済ませ、午前7時には木更津、しかもかなり山のほうにいました。昨年の人魚姫も、一昨年のラヴァルス&幻想の時も、5月に同じ事を書いていました。
ここって、音楽家の卵を教育するための施設ですよね?日によっては、指揮者の大友直人氏が来るようなのですが、今日はいなかったようです。でも、ヴァイオリンやフルートのケースを持った人たちがちらほら・・・。当然、私もフルートとピッコロをここに持ってきているのですが、音楽とは全く関係ない理由で、しかも毎年来ています。嫌がらせだよなあ。
車を飛ばして練習会場に戻り、ようやく練習に参加。もちろん、大遅刻。第1楽章はすでに終了、第2楽章もほとんど終わりのほうから練習に参加しました。果たして周りの雰囲気に溶け込めるか、心配しましたが、今日はなんとか迷惑はかけずに済んだようです。今日の私の問題点は、やはり第3楽章でした。楽章全般的にいえることは、タンギングの甘さが気になります。もう一度個人練習でさらい直しです。逆に、練習番号36のフルートとのオクダーヴのロングトーンは、今日はよかったと思います。
・トップへ戻る
5月6日(土)
先週に引き続き、弦楽器のみの練習。これだけでは申し訳ないので、「Flute」のページを全面改装、リニューアルオープンいたしました。
4月29日(土)
今日は弦楽器のみの練習で、管楽器はお休み。練習の模様は書くことが出来ないので、代わりにこの曲の楽器編成を掲載したいと思います。
木管楽器
フルート4本(全員ピッコロと持ち替え)、オーボエ4本(3番、4番はイングリッシュホルンと持ち替え)、B管クラリネット3本(3番はバスクラリネットと持ち替え)、Es管クラリネット2本、ファゴット4本(4番はコントラファゴットと持ち替え)
金管楽器
ホルン6本、遠くからひびくホルン4本(7番-10番のホルンとしてオーケストラでも使う)、トランペット6本、遠くからひびくトランペット4本(このうち2本はオーケストラから5番、6番を持ってきてもよい)、トロンボーン4本、バスチューバ
オルガン
ハープ2本
弦楽器
打楽器
ティンパニ奏者2人、各自ティンパニ3台ずつ(あとから第3奏者がはいる)、大太鼓、シンバル、高いタムタム、低いタムタム、トライアングル、小太鼓(できれば複数)、グロッケンシュピール、鐘3つ(低い、一定の音律を持たない鋼鉄の棒)、むち
(演奏には2人のティンパニ奏者の他に5人の奏者を必要とする)
遠くからひびくもの
ティンパニ1、大太鼓、シンバル、トライアングル
ソプラノ独唱、アルト独唱、混声合唱
マーラーですからね。それでも、今まで私が演奏したことのある第1番から第5番までの中では、明らかに一番大きな楽器編成です。ちなみに私が担当するフルートの全員ピッコロ持ち替えは、第3番、第5番に続いて3回目です。
4月22日(土)
第3楽章より、練習が始まりました。個人的にとても苦手な楽章なのですが、どうもオーケストラ全体としてもやりにくそうな楽章のようです。初めに楽章全体を通した時に、そう感じました。おそらく全5楽章中、今後最も練習時間を必要とするでしょう。これまでの練習で、大分縦線は合ってきて次は表現付けの段階、とこのページで書いてきましたが、第3楽章については、まだその段階までいっていません。まだまだ符読みの段階です。
この楽章で最も大事なソロパートのひとつに、私が担当するピッコロがあります。当初それほど難しさは感じていなかったのですが、アンサンブルの中での演奏となると、色々な問題が発生しました。
①練習番号34のピッコロソロ+弦の縦線合わせ
②練習番号36のピッコロ+フルートのオクターヴピッチ
③全体的にピッコロの音量が小さい
①は今日まで色々迷ったのですが、結局指揮者の棒をきちんと見ることだけで、解決できそうです。練習を始めた直後はそうしていたのですが、途中から迷いがでて、他のパートの動きを見たり聴いたりしていました。今日は何通りか試してみたのですが、録音を聴き返してみて、周りを気にせず、指揮者にのみ集中している時が一番「アンサンブル」が出来ていました。皮肉なことですが。①はこの方法で決定。
②はお互いのクセは分かっています。フルートは低くなりやすく、私のピッコロは高くなりやすい。今日は最初に通し練習をしたときには、バッチリだったと思います。私が描いていたイメージ通りでした。でも、その後はボロボロでしたね。ここについては良い時のイメージが頭にあるので、今後はそれが高い確率で演奏に表れるようにしていきたいです。
③については、本当に困ったものです。指摘される前から、常に自分では、2段階くらい音量を上げて吹いていますので。根本的な解決方法もなくはないのですが、それは数年後にいたしましょう。
残り時間で、第4楽章と第1楽章を練習いたしました。第4楽章は、中間部の「天使が舞い降りた」ピッコロのメロディ。録音を聴いてみて、あーあという感じ。これでは天使は舞い降りません。残念ですが。第1楽章、ピッコロはあまり活躍しませんので、割愛させていただきます。
・トップへ戻る
4月15日(土)
久しぶりに初めから練習に参加をしました。今日は第2楽章と第5楽章の合奏です。
前半は第2楽章。今までは縦線あわせが多かったのですが、今日は音色や強弱のバランスといった、曲の表情付けの練習が多かったように感じられました。ただ、曲は通るようになったものの、表情付けをしようとすると、今度は縦線が崩れてしまうところも出てきてします。まだまだ、メトロノームでの練習が必要ですね。楽章後半のピッコロ+フルート+ハープのアンサンブル、今日は音程が?でした。今まで良くはなってきていて、音程に関しては何もしなくてもほぼ許容範囲に収まっていたはずなのですが。
後半は第5楽章。数箇所を除いて、大分交通整理の成果が出てきたように感じられます。オケ全体として苦手だなと感じるのは、練習番号7~10や39~41といったところ。つまりアンテナをはって、俊敏な動作を求められる場所だと思います。確かにこういうところは難しいですね。。でも、ベルリンフィルやニューヨークフィルの演奏を聴いていると、なんか違うようなあ、とも思ってしまう、けどうまくいかない。理想と現実のギャップ・・。
ここでも何度も書いている、舞台上のフルート&ピッコロと舞台裏の金管とのアンサンブルについて。どこでどう間違えたのか分からないのですが、ピッコロの大きなソロの直前で、周りと完全にずれてしまい、演奏を止めてしまいました。ここの場所で今日のような間違いをしたことはなかったので、演奏をしていて自分でびっくりしてしまいました。録音を聴いてみたのですが、映像がないのではっきりとは分かりません。ただ、舞台上奏者・舞台裏奏者とで「グループごと」に指揮者の棒を違う読み方をしていたのでは、と推測します。
・トップへ戻る
4月8日(土)
先週に引き続き、また遅刻参加しました。何か嫌な予感が・・。
第2楽章の後半から吹いたのですが、やっぱり周りと合わない。不安な気持ちになりましたが、その後の第5楽章の練習中に、必死で調整をしました。先週の二の舞はいやだ! そのかいあって、今週はなんとか持ち直し、楽しく吹くことが出来ました。
第5楽章の練習番号7から10にかけて、ピッチがかなり気になっていたのですが、今日はいい感じだったと思います。3月4日の①でも指摘した第3オクターブのG-A音のトリル、まだ(ピッコロでの)いい指使いが分かりません。どなたかご存知でしたら、教えて下さい。
舞台上のフルート&ピッコロと舞台裏の金管バンダの掛け合い、3月25日の練習では、私の演奏は「軽快さ」に欠けていました。で、今日は、とにかく重くならずに、注意して吹いていました。すると私はもちろん、他の人の演奏もいつも以上に良くなってきたような気が・・・。次回以降、またMDに録音をして、客観的に演奏を聴いていてみたいと思います。
・トップへ戻る
4月1日(土)
4月になりました。本番に向けて、さらに気持ちを高めていきたいところですが、私個人としては、これまでの練習の中で、最悪の出来でした。
遅刻をして練習に参加。たびたびあることですが、途中から練習に参加すると、その場でいきなり合奏の雰囲気を感じ取らなければなりません。うまく感じ取れればいいのですが、そんなことはごくまれ。何度も遅刻参加をする以上、そういう能力がほしい・・・。
私の場合、合奏がある日には、前もってウォーミングアップをして、初めて周りの人と同じ土俵に上がれると思っています(それをしなくてもできる人はいいのですが)。事前練習をして初めて、です。練習場所に遅刻をして飛び込んで、音だしもチューニングも何もせずにステージに上がればどんな結果がまっているか、容易に想像ができます。今後は、曲の練習の他に、こういう状況に対応する練習も必要かも。でも、どうやって?
曲は、第1楽章と第3楽章。前半の第1楽章は、それでも何とか気持ちをキープできたのですが、後半の第3楽章はもうどうにもなりませんでした。3月4日にこの楽章の問題点を指摘しましたが、改善されているどころかさらに悪化しています。今日は何を言ってもだめ。気持ちが良い方向に切り替わりません。1日か2日はこのまま何もせず、放っておいて下さい・・・。
3月25日(土)
今日は合奏です。第2楽章、第4楽章、そして第5楽章の3つを練習しました。
第2楽章、綺麗なメロディが出てくるところは段々良くなってきました。が、三連符のような細かく速いリズムが出てくると、曲のバランスを崩してしまう場面があります。練習は、あまり時間を掛けずに終わってしまいました。
第4楽章、中間部の2本のピッコロのアンサンブルがでてきます。音程を注意するところは、分奏で理解していましたので、クリアできたと思います。でも、自分で吹いていてどうもしっくりこない。自分がイメージしているような音楽になっていないんですよね。何度も繰り返し吹いてみて、いい吹き方を見つけていきたいです。
第5楽章、何度も書きますが、まず交通整理が大変な楽章です。その成果が少しずつでてきたのか、部分的には整ってきたところもあります。そういうところは、次に音程やリズムが気になります。今日はMDで録音をしていて、今聴きながらパソコンに向かっているのですが、出だしの強烈なハーモニー、かなり音程が気になります。自分が担当するピッコロも、かなりやばいです。言い訳をすれば、音を出すだけでも大変なところなんですけど・・。
そして今日徹底的にしごかれたのは、これも再三申し上げている付点のリズムです。盆踊り(もしくはうさぎのダンス)から、マーラーの付点のリズムへ矯正する練習が行われました。あるパートがいいリズムで演奏すると、今度はそれができていないパートのリズムが気になります。これも時間を掛けて、辛抱強く矯正していくしかないと思います。
舞台裏の金管打楽器と、舞台上のフルート・ピッコロのアンサンブル。気をつけることは、各楽器の入りのタイミングと「ナイチンゲール」の泣き声に成りきることだと思います。でも、まだまだ雰囲気が出ていません。フルートと私が吹くピッコロのバランスも今一ですし、録音を聴いていると、私の演奏は鳴き声の「軽さ」がなく、逆に「重さ」を感じてしまいます。
3月18日(土)
1週間休みの後、管楽器の分奏です。これまでの演奏とは一味違うもののように感じました。おそらく、演奏者一人一人が曲の全体像をつかんできたのではないでしょうか。
第1楽章から順番に、練習を開始。少しずつまとまってきてるのが感じられました。ピッチやフレーズ感は、まだまだ改善の余地があります。リズムは、特に付点のリズムはこれから改善するというよりも、おそらく「盆踊り」になってしまう癖がついてしまっているのだと思います。これは要注意です。冷静になって聴いていると、結構恥ずかしいです。
第2楽章は、まあまあだと思います。写真右側に掲載されているのは、私が担当している3番フルート(1番ピッコロ)のパート譜です。上2段はフルート(+ハープ)と一緒に演奏する場面ですが、1拍目を意識することで、以前よりもうまく吹くことができました。
第3楽章は、スケルツォの楽章、結構複雑な曲です。他の楽章よりも、ユニークさが求められる楽章だと思います。それゆえ、よりオーバーな表現、例えばクレッシェンド+ディミニエンド等、を行う必要があります。そうしないと、聴いている方が面白くないでしょう。
最後は第5楽章。今日は、楽器が各パートがそれなりに人数が揃っていましたので、一番充実度の高い練習を行えたのではないでしょうか。いままで歯抜けになっていたとこがなくなり、単音ではなくハーモニーになっていました。やっぱりいい曲ですね。今日の練習で、ようやく第一段階を突破した、と感じています。
3月11日(土)
今日は弦楽器のみの練習のため、管楽器はお休みです。午後は、フルートのレッスンを2ヶ月ぶりに受けてきました。
曲はAndersen Op.21の11曲目。AisやFis、Disが頻繁に出てくる嫌な曲です。とりあえず曲を通すことができましたが、豊かな響き、そしてレガートのスムーズさを欠いてしまう演奏でした。師匠が指摘するには、 息の吸い方に問題があるのでは、とのこと。
今現在、ブレスを取る時に「雑音」がするようです(自分では気になってなかったのですが)。これは、喉を十分に開けていないために起こる音で、いい音を出すための準備の妨げになっている可能性があります。指摘された後、喉を十分に開けてブレスをし、演奏をしました。すると、師匠より前よりずっと良くなった、と言われました。これは、自分の演奏を良くしていくための第1歩かもしれない、そう感じるレッスンでした。
・トップへ戻る
3月4日(土)
今日は合奏です。まずは第3楽章のスケルツォ。オーケストラ全体でも、そして私自身にとってもいろいろ問題点が出てきました。
①練習番号34のピッコロソロの弦とのアンサンブル
②練習番号36のフルートとのオクターブのピッチ
③練習番号55のC音の発音
私の大きな問題点は、上記の3点です。もちろん他にも細かいことはたくさんありますが。①は予想外でした。というのは、ここは普通に吹いていれば、周りと自動的に合うと思っていましたので。②は一番最初の練習から気がついていて、しかもその対策もしていたつもりでしたが、結果が伴いませんでした。今後調整をしていきたいと思います。③は難しいですね・・・。今のところ、対策法が見つかりません。本当に音が当たらないのです。力が入りすぎているのか、うまくいきません。
後半は第5楽章です。この楽章は編成が大きく、音楽的なことよりもまだ交通整理の最中という状況です。その中での私の問題点は、以下の3つです。
①練習番号11から12にかけてのG音のトリル
②練習番号29から31にかけてのバンダとのかけあいのソロ
③付点のリズムが甘くなる
①のトリルは、とりあえず指つかいは分かりました。ただ、フルートの時と違い、ここのトリルは非常に難しい。安定した音が出にくいのです。でも、めちゃくちゃ目立つしなあ・・。他に替え指がないかなあ。②は今現在、なんとも言えません。楽譜には「Langsam」と書いておきながら、「nicht
schleppen」という言葉も併記されている。「ゆるやかに、しかしひっぱらずに」という意味なのでしょう。どうしてもたっぷり吹きたいという気持ちが強く、今は「Langsam」の方に意識が集中しています。③は常に意識しないと、盆踊りになってしまいますね。
2月25日(土)
管楽器の分奏でしたが、なかなか充実した内容でした。
まず一番長い第5楽章から。楽器編成もフルの4管編成になります。今現在、まだマーラーの音楽らしさは出来ていないですね。前々から感じている交通整理の必要性はもちろんですが、さらにピッチ、リズムに気を使う必要があります。今日は、特にリズムについて重要性を感じました。
そのリズムとは、マーラーお得意の付点のリズム+3連符のリズムです。付点の時にはどうしても甘くなって、盆踊りのリズムになってしまい、また3連符の時には前の付点リズムとの違いがはっきり出ていないですね。この楽章に限らず、曲全体にこのリズムは頻繁に出てきますので、今は意識的にリズムを考え、最終的にはそのリズムが自然に出せるようにしたいと思います。
残りの時間で第4楽章を練習をしました。中間部でピッコロ2本による、綺麗なメロディがあります。一箇所、ピッチで問題が発生しました。でも、意識することで改善は出来るでしょう。ここはとても目立つところなので、私にとっては今日一番の収穫でした。
しかし、この曲は楽器を吹いていない時間が長いですね。管楽器の出番のある部分だけを取り上げても、そのように感じました。
2月18日(土)
合奏だったようです。1楽章をかなり細かく練習したようです。すいません、今日は練習に参加できませんでした。
2月11日(土)
今日は弦楽器のみの練習で、管楽器はお休みでした。
2月4日(土)
前回までで、一通り曲を通しました。今日からは、少しずつ細かく見ていくことになるでしょう。
第1楽章はかなり丁寧にさらいました。縦の線すらまだ揃っていない状態ですが、音の強弱、ドイツ語表記を解説してもらうことで、音楽の表情が良くなる場面も。今の時期は、一つ一つ確実に練習をしていきたいです。それにしても休みが多いですね、3番フルートは。第九のように休みなしもきついのですが、休みが多いのも集中力を保つ上でかなり大変です。
残りの時間で、第2楽章を練習しました。後半、ハープとフルートとピッコロが一緒に演奏する場面があるのですが、ここがなんとも嫌ですね。特に難しい音もないのですが、なぜかうまくいきません。何でだろう・・。
1月28日(土)
4ヶ月ぶりに、フルートのレッスンを受けてきました。Andersenの10曲目。4ヶ月前にやり直しになった曲ですが、結局この1曲のみしか今日までさらうことが出来ませんでした。楽譜の読み間違え等がありちょとあせりましたが、なんとかパス。またマーラーの2番で出てくる、ピッコロの高~い「Des」音の指づかいを教わりました。これで、すっきりしました。
さて、オケの練習。今日は、第4楽章と第5楽章を練習しました。いやー、まだまだですね。拍子の変化、音量の変化、テンポの変化。本当に変化の嵐です。練習期間が約半年あるので、焦らず、じっくりと取り組んで生きたいと思います。
1月21日(土)
雪が降りしきる中、合奏が行われました。さすがにこの天気では、いつもより人は少なかったですが、それでもざっとみて8割以上の人が集まっていたようです。
2枚とも自宅で撮影。
今日は第1楽章から第3楽章までの合奏をしました。まあ、大変な曲ですね。マーラーのどの曲にも共通していると思うのですが、まず沢山の音符の交通整理をしないと始まりません。今日はそれすら出来なかったかも。それから、曲全体に占める休みの割合がとても高い。ベートーヴェンやブラームスはこうはいかないですからね。曲は長いのですが、休み時間も長い。これもマーラーを吹いていて思うことです。
1月14日(土)
この曲に出会ったのが今からちょうど20年前の1986年、13歳の時でした。その時の衝撃は今でもはっきり覚えています、”こんな曲が世の中にあったのか!” それ以来、色々な曲に出会いましたが、この曲は常に自分にとってあらゆる意味でNo.1であり続けました。そして、いよいよ今回、この曲を演奏する機会に恵まれたのです。
初練習である今日は、管楽器のみによる分奏。初回の練習にもかかわらず、遅刻をして参加。なんとも情けない。しかも、なぜか慌てて練習会場に到着、全く音も出さずに分奏に参加したため、完全に浮いてしまっていまた。第2楽章、第3楽章、第1楽章、そして第5楽章の途中まで進みました。んー、弦楽器がないと、結構分かりにくい曲ですね。曲が耳にこびりついているだけに、理想の音と現実の音に差があり、ちょっとショック。次回は合奏なので、曲全体の感覚をつかみたいです。
これまでの特別企画
・⑯歌劇「カルメン」&「バラの騎士」組曲
アマオケ練習日記
(2005年12月)
・⑯ツェムリンスキー交響詩「人魚姫」 アマオケ練習日記
(2005年7月)
・⑮マテキフルート工場見学記
(2005年4月)
・⑭Ph.ハンミッヒ木管フルート ノマタチューンナップ記
(2005年2月)
・⑬ベートーヴェン交響曲第9番「合唱」 アマオケ練習日記
(2005年2月)
・⑫新世界より&キャンディード アマオケ練習日記
(2004年12月)
・⑪ロイヤルコンセルトヘボウ管弦楽団2004年日本公演レポート
(2004年11月)
・⑩幻想交響曲&ラヴァルス アマオケ練習日記
(2004年7月)
・⑨ハイドン交響曲全104曲 完全制覇日記
(2003年11月より)
・⑧イスラエルフィルハーモー管弦楽団2003年日本公演レポート
(2003年12月)
・⑦シカゴ交響楽団2003年日本公演レポート
(2003年10月)
・⑥マーラー交響曲第5番アマオケ練習日記
(2003年7月)
・⑤ギルバート・キャプラン
(2002年8月)
・④月に1度はコンサートへ行こう企画2001年総括
(2002年3月)
・③ウィーンフィルハーモニー管弦楽団2001年日本公演レポート
(2001年10月)
・②マーラー交響曲第3番アマオケ練習日記
(2001年7月)
・①ベルリンフィルハーモニー管弦楽団2000年日本公演レポート
(2000年11月)