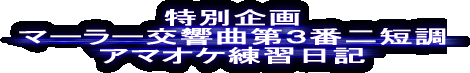
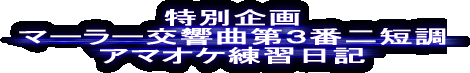
| 7月15日(日) 最終回 いよいよ演奏会当日。ついにこの日がやってきました。中学生の時にマーラーに目覚めて以来、今までずっと彼の音楽を追い求めてきました。そして、聴くだけでなく演奏もしてみたい、と思うようになりました。 アマチュアのオーケストラで、マーラーの全交響曲を演奏することは難しいだろう。第1番と第5番、ひょっとしたら第2番も吹く機会があるかもしれない。第3番は一生かけても吹くことはないだろうなあ。こう思っていました。 でも、心のどこかでは「いつかは吹いてみたい・・・」と、思っていたのでしょう。自分が望まなければ、こんなビッグ・チャンスを手に入れることなんてできないはずですから。 いつものように私は9時過ぎに楽屋に入りました。午前10時からリハーサル開始。楽章順に進めていって、ほとんど止めることなく全楽章を演奏。オケも合唱も”体調”は万全のようです。12時にリハーサルを終了。 14時開演予定が、5分押しで演奏が始まりました。第1楽章の出だしのホルンから、緊張感のある演奏で、なかなかいい雰囲気。途中あちこちで”事故”があり、演奏が破綻しかけました。でもこの曲、楽譜どおり演奏しても破綻している雰囲気があるので、そんなことは気にしない気にしない。第1楽章終了直後、なぜか客席から「ブラヴォー」の声が。第2楽章も何とかクリア。舞台裏のポストホルンもうまくいった第3楽章を終えたところで休憩。 第4楽章から演奏再開。鳴海先生のアルトが絶品で、それに応えるようにオケも前半にはなかった、安定感のある演奏をするようになった。第5楽章もGOOD、GOOD! そして間髪を入れずに第6楽章へ。この瞬間がなかなかいいんだよね。金先生も、いつもに増して感情のこもった指揮でオケを引き付けていきました。そして最後のハーモニーを吹き終えたとき、なんとも言えない充実感!マーラーは素晴らしい! 今度は何番を吹くことになるのだろうか。今から楽しみです。(完) |
|
| ・トップページへ戻る |
|
| 7月14日(土) 本番前日。金洪才先生によるゲネプロ。 歌の入る第4楽章と第5楽章から練習を開始した。合唱も徐々に上向きになってきているみたいですね。よしよし。休憩後は残りの楽章を練習したが、ほとんど通しただけ。いつもの練習場と響きが違うため、少し戸惑った。でもこれはG.P.では毎回感じること。すぐに慣れるだろう。 明日は待ちに待った本番当日。とにかく楽しみである。 |
|
| ・トップページへ戻る |
|
| 7月7日(土) 本番まであと1週間。今日は副指揮者のK氏の指揮で、全曲を一通り練習した。 当初かなりやばかった室内楽的な部分のアンサンブルもだいぶ改善され、オケ全体がまとまってきた。ただ個人的には、いままでできていた所が吹けなくなったり、楽譜を前に急に頭の中が真っ白になったりと、新たな問題が発生した。本番直前ということで緊張しているのかもしれない。 これからは体調を整えて、本番がベストの状態で演奏できるようにしていきたい。といっても、ここ数年風邪もひかず、体調不良というのを経験したことがない。ま、普段どおりの生活をすればO.K.でしょう。 |
|
| ・トップページへ戻る |
|
| 7月1日(日) 昨日に引き続き金洪才先生による合奏。今日の練習場所は小学校の体育館。当然冷房施設はない。とにかく暑かった。楽器のピッチも上がりっぱなしで、落ち着かない。 全ての楽章の練習をした。昨日と同じような感触で、演奏している方は気持ち良くなれるレベルになってきた。児童合唱もよく練習を積んでいるようで、一緒に演奏をしていてとても楽しい。 本番まであと2週間。この演奏会にご興味を持たれた方がいらっしゃいましたら、是非こちらをご覧下さい。 |
|
| ・トップページへ戻る |
|
| 6月30日(土) 金洪才先生による3回目の合奏。第1楽章、第5楽章、第3楽章の順に進んだ。 今日は管楽器も打楽器も、初めて全ての人が揃い、吹いていて非常に気持ちが良かった。マーラーのような編成の大きな曲は、人を揃えるのは非常に難しい。しかし、揃ったときとそうでないときの練習の密度の差は歴然としている。そういう意味でも今日の練習は、意義のあるものだったと思う。 合奏の様子をMDで録音していたが、確かに基本的なリズムや音程は、まだまだ改善の余地がたくさんある。ただ少し良くなったことは、合奏をしていて気持ち良く吹けるようなレベルになったということ。上向きになっていることだけは間違いがない。 |
|
| ・トップページへ戻る |
|
| 6月23日(土) 副指揮者のK氏による合奏。不安の残る部分を中心に。 第1楽章、第6楽章、そして第3楽章の順に合奏が進んだ。どの楽章にも共通することであるが、リズムの感じ方が「盆踊り」になってしまっている。つまり音符一つ一つをべったりと演奏している。もう少しノリを良くして、ウィーンの音楽に近づくようにしなければ。特に第3楽章はリズムの面白さで聴かせる楽章なので、その配慮が十分に必要だと思う。 |
|
| ・トップページへ戻る |
|
| 6月16日(土) 後半の第4楽章から第6楽章の練習。今日は金洪才先生の指揮に、アルト独唱の鳴海先生、女声合唱と児童合唱も加わった。 第5楽章から練習を開始したが、鳴海先生の表情の素晴らしさに驚いた。熱い熱い想いが伝わってくるような、そういう歌い方だった。歌だけでなく、普段の話し方などもとてもバイタリティーに溢れてる。こういうソリストと共演できるのはとてもうれしい。第4楽章も、同様である。 休憩後は第6楽章。1回目の通しは今一であったが、金先生のアドヴァイスをもらったとたんに音楽の流れが良くなった。ここぞ!というところでは、しっかりブレーキをかけて強調し、オケを熱くさせてくれる。これこれ、マーラーはこうでなくっちゃ。 |
|
| ・トップページへ戻る |
|
| 6月10日(日) 2日連続練習。今日は、仕上がりが今一の第2楽章と第3楽章を、集中的に練習した。 練習を終わってみても、清々しさや満足感を得られないのが心残りだ。それ以上に疲れを感じてしまった。一生懸命やってはいるが、どうもこの2つの楽章については、突破口が見つけられないでいるような気がする。 まあ、一生懸命やっているのだから、本番までにはそれが報われるでしょう。 |
|
| ・トップページへ戻る |
|
| 6月9日(土) 本番の指揮者、金洪才先生の一回目の合奏。第1楽章から第3楽章までの通し練習が行われた。 音楽が生きている!第1楽章では熱く、第2楽章では優雅に、そして第3楽章ではユーモラスに。去年のブルックナー8番でも感じたが、オケの力を引き出すのが上手な指揮者だと思う。金先生の練習はわずか5回だが、これからの1回1回が楽しみだ。 先生が次回いらっしゃるのは、6月16日。その時は、アルト独唱の鳴海先生、女声合唱や児童合唱も勢ぞろいする。 |
|
| ・トップページへ戻る |
|
| 6月2日(土) 本番まであと1ヶ月とちょっと。ここで各楽章の出来具合を、「○」「△」「×」の3段階で評価してみたいと思います。 第1楽章・・△ 第2楽章・・× 第3楽章・・× 第4楽章・・△ 第5楽章・・△ 第6楽章・・△ 今日の練習でも、上記の評価が明らかであった。編成が小さくなる第2楽章と、音符の数の多い第3楽章が今一歩である。第2楽章は、上流階級のワルツのイメージが必要。曲の雰囲気が、依然としてつかめていないようだ。第3楽章はとにかく個人練習がまだまだ足りない。メトロノームを使ってさらいなおしてから、全体練習に臨んだ方がよさそうだ。 マーラーの演奏に必要のことを、今日は一つ学んだ。周りが「p」でも自分が「f」なら、勇気をもってフォルテで吹く。つまり自分の楽譜を信じて、周りにつられない事である。 |
|
| ・トップページへ戻る |
|
| 5月27日(日) 2日連続の練習。 第3楽章から練習開始。いつもにも増して細かく練習した。昨日も書いたが、お互いに聴くことが忘れられている。ちょっと指摘されただけで直ってしまうのではあるが・・・。それから曲の場面を考えながら吹くことがもう少し必要であると思う。同じ3連譜でも吹き飛ばすものなのか、一つ一つ置いて吹くものなのか。つまり場面のキャラクターを考えることが必要だろう。 第2楽章、第4楽章〜第6楽章も同じようなことが言えると思う。今日はもう疲れたのでこの辺で。 |
|
| ・トップページへ戻る |
|
| 5月26日(土) 先週の分奏後の合奏、果たしてその成果は? 楽章順通り第1楽章から。初めは緊張感のない演奏でびっくりしてしまったが、だんだん楽器も温まってきて、いつものレベルに戻った。今もって改善されないところがある。それは編成が小さくなったときのアンサンブル。相変わらず、わが道を行く、になってしまっている。せっかくソロの掛け合いなのに、もったいない。 分奏が項を奏したのは第2楽章。基本的なことであるが、まずは縦を合わせることの重要性を改めて感じた。今日は初めてこの楽章を気持ち良く演奏することができた。今まで縦すら合っていなかった、合奏をする上で最低限のこと、は問題である。しかし、それはもう改善できたので、これからは楽しく音楽ができるレベルになるだろう。 |
|
| ・トップページへ戻る |
|
| 5月19日(土) このマーラー3番の練習予定の中で、初めての管分奏。 第3楽章から開始した。マーラーお得意の付点のリズムや、スラーとスタッカートが一緒に出てきたときの吹き方などについて注意があった。一言でいうとまだリズムの取り方が甘いらしい。第2楽章についても同様の指摘を受けた。全体を通して表現が平らになっている。 第5楽章はピッコロ4本のアンサンブル。なんとか必死になって合わせている、という感じが演奏に出ている。それでも最初のころよりはずっと良くなったと思う。偶然にもピッタリと合う瞬間が出てきたからだ。残りの時間で第1楽章も途中まで練習した。 |
|
| ・トップページへ戻る |
|
| 5月12日(土) 予定では第6楽章のみの練習であったが、急遽第1楽章も加えられた。 まずは第6楽章。いつもよりゆっくり(たっぷり)としたテンポが取られていて、新鮮に感じた。マーラーの書いている指示について説明があり、その通りに演奏すると曲の表情ががらりと変わった。改めて楽譜をきちんと読む重要性を痛感した。 第1楽章は時間の都合で約半分しかできなかった。練習番号20のピッコロのソロ、1回目が「poco accel.」で2回目が「ohne Rucksicht auf den Takt」の指示。初めは少し控えめに、次は大胆にという指摘を受けた。ソロなので、もっともっと目立ってもよさそうだ。 全体合奏でも個人でも、だいぶカタチはできてきた。これからはもう1度譜面を見直し、細かいニュアンスを身につけていきたい。 |
|
| ・トップページへ戻る |
|
| 5月6日(日) 昨日土曜日を休みにして、日曜日を練習日にする変則日程で行われた。練習時間もいつもより1時間多い4時間。 これまでは各楽章別に見てきたが、今日は初めて全曲をノンストップで通すつもりで練習が始まった。第1、第2楽章は何とか持ちこたえたが、第3楽章でついに止まってしまった。やはり途中で止まると集中力が続かなくなる。そのあとの第4楽章でも止まったが、なんとか最後まで通した。 結果的にはノンストップでは通らなかったが、しかし曲の全体像のようなものは何となくつかんだような気がする。もちろん個々にさらわないといけないところは山のようにあるが。 次回からまた個々の楽章の練習になる。7月の本番は、もちろん通して演奏するわけだが、演奏者もお客さんも感動するようなものに仕上がるよう、頑張りたい。 |
|
| ・トップページへ戻る |
|
| 4月28日(土) ゴールデンウィーク初日の今日は、第1楽章と第6楽章の演奏時間の長い楽章の練習。 まず第1楽章。 だいぶ楽譜も読めるようになり、細かい指使いもこなせるようになってきた。今回の練習では、特にアクセントがついている白玉の音符の吹き方について注意があった。音を抜く、つまりグロッケンや鐘のように演奏するとうまくいく。 第6楽章はほとんど弦楽器練習になってしまった。特にコメントはありません。 |
|
| ・トップページへ戻る |
|
| 4月21日(土) 今日は弦+木管+ホルンの練習。第2楽章から第5楽章まで盛りだくさんのメニュー。 前半は弦のみの練習で、後半から管楽器が加わった。時間が無いため、ほとんど通し練習になってしまった。全ての楽章に言えることだが、まだ音楽が流れていない。指使いもまだクリアされていない段階なので、当然音楽を創るところまではいけない。まだ4月とはいえ、少し心配になってきた。 個人的にもピッコロ4本のピッチを合わせられなくて、ちょっと焦っている。 |
|
| ・トップページへ戻る |
|
| 4月14日(土) ヴァイオリンが休みの第5楽章から練習開始。ここではピッコロ4本のアンサンブルがでてくる。決して出しにくい音ではないが、4本で吹くことは普段全くないことなので、音程が気になってしょうがない。要練習。 第4楽章は3連符、5連符や7連符が単に出てくるだけではなく、それらが複雑に絡み合う。ゆっくりな楽章なのでよけい厄介だ。しかし、苦労しながらもなんとか付いていっている人が、少しずつ増えてきているような気がする。 休憩後は第6楽章。あまりにも美しい曲なので、少しでも音程が合わないと気になる。でも、本番はちょうど3ヵ月後。この時までに、美しさに演奏者もお客さんも酔えるような(!?)音楽に仕上がっているといいんだけど。 |
|
| ・トップページへ戻る |
|
| 4月8日(日) 日曜練習。2日連続だとさすがにきつい。今日は第2楽章と第3楽章の弦+木管+ホルンの練習。 第3楽章から練習をした。曲中に出てくる自然の描写(鳥の鳴き声など)の吹き方について注意を受けた。マーラーはそれらをあえて音符にしただけで、演奏をするときには音符どおりではなく、実際の鳥の鳴き声をイメージしなければならない、とのこと。 第2楽章は何気ない牧歌的でのんびりとした雰囲気を持っている。しかし演奏をすると、とても牧歌的な気分になることなどできない。かなりの難曲。木管も難しいが、弦楽器が特に大変そうだった。ある程度完成するにはかなりの時間がかかりそう。 |
|
| ・トップページへ戻る |
|
| 4月7日(土) 過去2回の練習で一通り譜読みも終わり、これから各楽章を細かく練習をしていく。今日は第1楽章のみ。 とにかくこの楽章は音の数が多く、「整理」をしながら吹いていくことが大切だと感じた。また編成も4管と大きいので、気の配り方が2管の時とは違う。 例えば2本でハーモニーをつくる場合、2番フルートは1番フルートを聴いていればまず大丈夫だが、4管だと単純計算でその倍の注意力が必要。普段2管編成の曲が多いので、少し頭を切り替えることが必要だと思う。 ピッコロも2本重ねが多く、とても気を使う。わずかだが4本重ねもある。そして高音域を担当するEs管のクラリネットと一緒に吹くことも多いので、かなり大変。これは練習をしていくことで慣れるだろう。 |
|
| ・トップページへ戻る |
|
| 3月31日(土) 今日は珍しく雪が降った。もう桜が満開だというのに、いったいどうなっているのだろう。そんな天気の中、今日は後半の第4楽章から第6楽章の譜読み練習をした。指揮はトレーナーのS氏。 まず第5楽章から。約5分ほどの短い楽章だが、歌が入らないとどうも雰囲気が出ない。かなりしらけてしまう。個人的にも周りとピッチを合わせることができず、気分が乗らなかった。 しかし第6楽章は一転して非常に気持ち良く吹けた。弦楽器の弱音に始まり、木管のメロディ、そして金管のコラール... 。完成にはまだ程遠いが、それでもこの楽章の素晴らしさを感じた。 最後に第4楽章。フルートはそれほど出番がないのだが、ゆっくりなテンポの中で音符が複雑に絡み合っていてかなり厄介。第6楽章のようにメロディが流れないので、理解するまでかなり時間がかかりそうだ。 |
|
| ・トップページへ戻る |
|
| 3月24日(土) いよいよ7月15日の本番へ向けて、マーラーの3番の練習が始まった。パートは3番フルート&ピッコロ。この曲が吹けるという喜びで、練習へ行く前から落ち着かない。車の中で、バーンスタイン指揮ニューヨーク・フィルの80年代の録音を聞きながら練習会場へ向かう。 初日の指揮はトレーナーのS氏。第1楽章から第3楽章まで練習(譜読み)をした。実際に演奏をしてみて、予想したより難しいですね。もう少し形になると思っていたけど、意外とまとまらない。私の頭の中ではバーンスタインの指揮した音楽、つまり完成されているマラ3がイメージできているのだが、聴いているのと演奏をするのとでは大きな違いがあった。 オケ全体でも曲を知っていて演奏した人と、そうでない人の差が大きかったと思う。しかし練習は始まったばかり。これから回を重ねていくうちにだんだんと慣れてくるだろう。不安もあるが、喜びや期待のほうが大きい。アマチュアでありながら、この大曲の演奏に携われたのは本当に光栄に思う。記念演奏会にふさわしいものになるよう、全力で取り組んでいきたい。 |
|
過去の特別企画 ・2000年ベルリンフィル来日公演レポート |
|