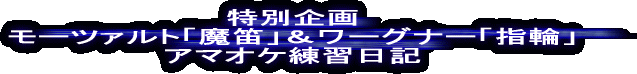
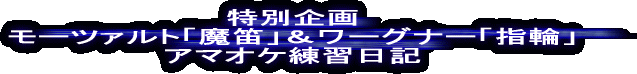
2012年10月21日(日)午後7時開演
市川市文化会館小ホール
(入場無料)
モーツァルト: グランパルティータ
ブルッフ: コルニドライ
尾高尚忠: フルート協奏曲
オペラアリア集
モーツァルト: ホルン協奏曲第3番
指揮:世川 望
市川交響楽団
(終了しました)
*********
2012年12月9日(日)午後2時開演
市川市文化会館大ホール
(入場無料)
モーツァルト: 歌劇「魔笛」より
ワーグナー: 楽劇「ニーベルングの指輪」より
指揮:安藤 敬
市川交響楽団
(終了しました)
*********
2012年12月24日(祝)
市川市文化会館大ホール
(有料公演)
チャイコフスキー: 「くるみ割り人形」 全2幕
指揮:井田勝大
市川交響楽団
(終了しました)
2012年12月24日(祝)本番当日
ピットに入っているとよく見えなかったのですが、本番のバレエの舞台は素晴らしかったようです。あるお客様からは、まるで夢の中にいるよう、という感想をいただきました。
実際に演奏をしていて、やばいところはたくさんありましたが、個人的にはとにかく楽しんで演奏することに徹しましたので、本番はこれまでで一番いい出来だったと思います。これで、今年の演奏会が全て終了いたしました。
しかし、下手奥に木管群が詰め込まれての演奏は、本当に難しい・・。(終わり)
2012年12月23日(日)
前日の練習です。オケ練習をしてから、ピットに入ってバレエとの合わせです。
明日が本番。
2012年12月22日(土)
相変わらず第1幕は難しいです。なかなか進歩が見られません。
2012年12月16日(日)
日曜日の特別練習です。今日はくるみの第2幕の練習です。この幕は、ショートピースが多いので、第1幕のような難しさはありません。
2012年12月15日(土)
ワーグナーが終わり、2週間後に公演がある、チャイコフスキーのくるみ割り人形全幕の練習です。今回はバレエ団からの依頼によるもので、いわば賛助出演。ピットの中での演奏になります。
今日は第1幕の練習です。マエストロの指導はくるみを知り尽くし、驚くほど無駄のない効率的な方法で練習が進みます。素晴らしい!でも、個人練習の量が絶対的に不足しているため、なかなかマエストロの要求に応えられません。特に9曲目の「雪片のワルツ」は難しいですね。
2012年12月9日(日)本番当日
午前10時より、プログラムと逆順でリハーサル開始。昨日のGPの問題点を中心に部分的に練習が行われました。個人的には、魔笛の序曲のソロがうまくいかず反省。本番直前まで舞台袖で繰り返し練習をしました。また魔笛のタミーノが新しい歌手に変更なっていてびっくり!本番当日にキャストが変更になるなんて、はじめてです。
午後2時開演です。モーツァルトの魔笛のハイライト。序曲、出だしの緩やかな部分は、オケがまだ硬かったのか、音に柔軟性がなく音程も不安定。スピードが上がる場面からは、少しずつ良くなりました。2ndヴァイオリンの刻み、本番が一番良かったです。安心して演奏ができました。
パパゲーノはコミカルな演出で、笑いを誘いました。続くタミーノのアリアでは、代役の歌手が私がこれまで聴いた中で最も美しいと思われるような、素晴らしい美声を披露。出番がないのでじっくり聴くことができました。夜の女王のアリアは力強い歌声で周囲を圧倒。最後はパパパ。演奏しても見ていても楽しい雰囲気の曲でした。
メインプロはワーグナーのリングから、「ワルキューレ」と「神々の黄昏」のハイライト。1曲目、チューニングをしたのにもかかわらず、周囲とピッチが合わず苦しみました。2曲目の出だし、これは八分の九拍子のヘミオラで、とてもテンポを保つのが難しい。本番でも苦しみました。このジークムントとジークリンデが結ばれる第1幕の後半は、テンポの変化の激しい曲ですが、オケ全体としては良い雰囲気で演奏できたと思います。
続く「ワルキューレの騎行」は、曲の途中でブリュンヒルデを除く8人のワルキューレがステージ上に登場。衣装の色も工夫されていて、見ているだけでも圧巻でしたが、若手を中心とした歌手陣は豊かな声量で素晴らしかった!続くヴォータンがブリュンヒルデを勘当する場面。二人のソリストは声量も豊かですが、場の空気を作るのがとても上手な方々だなあ、と感じました。オケもそれに呼応してこれまでで一番よい出来だったと思います。歌手陣の出番が終わり、オケだけによる「ラインへの旅立ち」と「葬送行進曲」。非常に難しい曲ですね。技術的な難しさもありますが、あれを自然な音楽と感じられるようになるまで、あと何年修行が必要か・・。
例年より行事が立て込み、練習回数が少ない演奏会でしたが、何とか無事に終了いたしました。これも歌手陣のお力と、弦楽器陣の頑張りによるものと思います。特にヴァイオリンのパート譜は凄まじかった!(12月ファミリー終了)
2012年12月8日(土)
前日のGP。大掛かりな舞台設営のため、いつもより遅めに練習が始まりました。
魔笛から。相変わらず序曲が難しい。テンポ感を共有することが未だに出来ません。あーあーあー。続いてリング。照明や日本語字幕等の演出があり、客席から見ているほうが楽しめそうです。
泣いても笑ってもあと1日。
2012年12月1日(土)
2週間程前から、合奏の度に胃が痛み出します。モーツァルトでは自分の技量のなさに悩み、ワーグナーでは周囲との連係の難しさに悩み・・。今日の痛みはこれまでで最大のものでした。
魔笛の序曲。これは100%自分の問題。最近は少しずつ自分とオーケストラのテンポ感の差が縮まってきたのかなあ、と思いましたが、今日は逆にその差が広がってしまいました。こんなこと、ありえない。辛いだけの練習でした。気持ちが萎縮していることが、状況をさらに悪くしています。
直ぐにワーグナーの練習。オケだけの練習では、周りの音と仲良くなれず、頭を抱えてしまうほどの仕上がり具合でしたが、ワルキューレの女性騎士たち、そして初登場のヴォータンといったソリストが入ると、オケも見違えるように良くなりました。今回の歌手陣は素晴らしい!
歌手陣にパワーをいただいたとはいえ、個人的な状況が良くなったわけではありません。練習が終わった後も、胃の痛みが・・。あと1週間でこの状況を打開しなければ。
2012年11月25日(日)
モーツァルトとワーグナーの演奏会の練習真っ只中ですが、クリスマスイブに上演される「くるみ割り人形」の練習が始まりました。これはバレエ公演の伴奏を依頼されていますので、ピットに入っての演奏の予定です。
今日は譜読み。10年ほど前にバレエ版の抜粋を演奏しましたが、その時の演奏の記憶はほとんど残っていなくて、今日の練習は四苦八苦しました。モーツァルトとワーグナーが終わったら、本格的に取り組みます。
2012年11月24日(土)
歌い手のソリストが多数参加しての練習でした。
まずは、魔笛のタミーノのアリア。声量があり、さらに美しさが加わった素晴らしい歌声でした。この1曲を聴けただけでも今日練習に参加した価値があったと思います。続いて、ワルキューレの第1幕の後半。ジークムントとジークリンデの独唱です。今まではカラオケ状態でしたが、歌が入るとワーグナーらしさ、全快です。これにも圧倒されました。
休憩後は、ワルキューレの騎行で、8人のワルキューレが勢ぞろい(今日は1~2名欠けていましたが・・)です。ワーグナーらしい、経済観念のない贅沢な歌手の使い方。若手の歌手陣でしたが、事前勉強をしっかりとされているようで、とても好感がもてました。素晴らしい歌手達です。続いて、ブリュンヒルデの登場。こちらも声量十分、引き込まれました。
一方、オーケストラは、このところ成長が止まっているような気がいたします。曲が難しく、楽しむ余裕がないのかもしれません。あと2週間・・。私ももう一度演奏のイメージを再確認をして、合奏に参加したいと思います。歌は素晴らしいのに、オケが台無しにした、なんて言われたくありません。
2012年11月17日(土)
前半は、「神々の黄昏」をじっくり練習しました。かなりあぶない・・。まだ交通整理が必要な段階かな、と感じました。
個人的にも周りとの意思疎通がいつも以上に出来ず、また1番を吹くプレッシャーからか、演奏をしながら胸が苦しくなり、
休み時間にココアを飲んで気持ちを落ち着かせるほどでした。
休憩後は「ワルキューレ」。「神々」よりは練習回数が多い分まとまっていると思いますが、綱渡りな演奏です。
残り20分で、魔笛の「序曲」と「パパパ」を練習しました。ワーグナー直後だと、どうしても重々しい演奏になってしまいます。
とてもおとぎの国のお話の序曲とは思えません。しかし、指揮者が気持ちを切り替える指示をしたとたん、音楽は軽さが加わり、
少しだけモーツァルトに近づくことが出来たと思います。私もいつもより力を抜いて吹くことができました。
「パパパ」で木管楽器と弦楽器のニュアンスが揃わないところは気になりましたが、ワーグナーに比べるとモーツァルトは一歩前進、といったところでしょうか。
2012年11月10日(土)
ソプラノのソリストを迎えての、魔笛とリングの練習です。
前半は魔笛でしたが、練習会場に約1時間遅れで到着したため、練習に参加できませんでした。着いたらもう練習が終わりそうでしたので、しばらくの間、客席から見学。練習1回分、他の人に遅れをとってしまいました。
後半はリングです。チューニングからすでに音の感覚がなくなっていて、パニックに陥りました。そんな状態ですから、ワルキューレも、管楽器は強奏でE音で入るのですが、音の塊がぐちゃぐちゃです。周りに魅惑をかけてしまいました。ごめんなさい・・。曲が進むにつれて、少しずつ調子をいつもの状態に戻ってはきたのですが、練習のはじまりからそのようにしなくては。
①「ワルキューレ」練習番号66周辺での息継ぎは目立たないように。
②「ワルキューレ」練習番号84からのフレーズ感、ピッチをもう一度確認する。今は音域によってばらつきがある。
③「ワルキューレ」練習番号88からのフレーズ感、特に3小節前のクレッシェンドを意識する。
今日の練習では少なくとも上記の3つが、個人の課題になりました。
2012年11月3日(土)
ワーグナーのみの練習です。集中力のある、とても良い練習でした。ハープやバストランペットなどが加わり、ワーグナーらしさがでたのではと思います。出来ないところがあっても、指揮者の指示を受けた後にやり直しをすると、それが出来るようになった場面もあります。少しずつですが、進歩しているように感じました。
個人的な問題点として、3つ気になりました。
①「ワルキューレ」の練習番号72と73の間のMolto
vivace
②「ワルキューレ」の練習番号92の4小節目から
③「神々の黄昏」の練習番号35から36まで
①は木管楽器とホルンがffで激しく六連符を演奏します。今まではシングルタンギングで間に合ったのですが、今日の練習では間に合いませんでした。テンポが少し速くなったのかな?こういった場合、本来なら1小節を3つ×4拍にしてトリプルタンギングが有効だと思うのですが、諸事情により、2拍3連に感じて2つ×6拍でダブルタンギングにするかもしれません。
②はフルート主体で音楽が進行するのですが、ただの棒吹きになっていて、音楽の方向性が見えません。要修行。
③は管楽器全体にいえることですが、まとまりのない演奏になっています。リズムを間違えている人がいるのか?
2012年10月27日(土)
12/9の演奏会の練習です。
前半は、ワーグナーのワルキューレと神々。全体的に集中力が感じられず、まとまりのない演奏でしたね。残念です。特に第3幕の「ワルキューレの騎行」は、サウンド的に不自然さを感じるところが多く、不安になりました。指回しが大変なので、周りのことはかまっていられないのだと思います。一方で、ワルキューレの第1幕の後半は、以前よりも音楽が流れるようになり、好感触でした。
後半は、魔笛です。個人的にはこちらの方がたくさん問題を抱えています。オーケストラで演奏するようになって、モーツァルト、ベートーヴェン、ブラームスの3人は、特に難しさを感じるようになりました。この3人の中でベートーヴェンは比較的演奏回数が多いので、仲良くなれそうな感触はあるのですが、今回演奏するモーツァルトとは、まだそこまでの関係をきずけていません。私の好きな作曲家ベスト3の一人であるにもかかわらず・・。今回の演奏会で、聴くだけでなく、演奏するのも得意になりたい、と思っています。
結果として、今日の練習でもモーツァルトとは仲良くなれませんでした。序曲の出だしからハーモニーを壊してしまい、パニックに。その後もソロでもTuttiでも、常にテンポが遅れぎみになってしまいました。ああ、みっともない!どこかに気の緩みがあるのでしょう。
2012年10月21日(日)
団員による協奏曲の演奏会、本番当日です。珍しく、夜の公演です。日中、別会場で全曲のリハーサルを行いました。
午後6時にホールへ入館。急いでステージに椅子を並べて、音だし練習無しに午後7時開演。コントラバスを主役にしたグランパルティータ、チェロ独奏のコルニドライ、尾高尚忠のフルート協奏曲、クラリネットによるオペラアリア集、そしてモーツァルトのホルン協奏曲第3番。ソリストの皆さん、舞台経験が豊富で、堂々たる見事な演奏でした。演奏会全体がアットホームな雰囲気で、普段なかなか味わえない感覚で楽しかったです。
2012年10月20日(土)
12月の演奏会から、ワーグナーの練習です。
前半は、神々の黄昏。この曲は、金管楽器主体に書かれていますね。ホルン、ワーグナーチューバ、トランペット、バストランペット、トロンボーン、チューバが主役です。楽器が揃えば、きっとかっこよくきまると思います。
後半は、ワルキューレ。こちらは逆に、弦楽器と木管楽器が主体です。フルートも吹き応えがあります。特に有名な「ワルキューレの騎行」は、かなりの指まわしの技術力が必要です。あまりの早いパッセージに、他のパートからは「ワルキューレの苦行」と呼ばれています。でも、今日の合奏は周りの音も比較的よく聴こえ、今までの合奏で、一番楽しく出来ました。また、弦楽器がよくまとまっていたと思います。
2012年10月13日(土)
4週連続のダブルヘッダーです。午後コマでは10/21の演奏会のうち、3曲の練習を行いました。
夜のコマは、10/21のGPです。曲順に、止まらずに演奏されました。1曲目は、コントラバスと管楽器でグランパルティータ。難しい曲だと思うのですが、とても安定した演奏でよかったですね。モーツァルトですから、フルートは除外されます。2曲目は、チェロ独奏によるコルニドライ。管楽器がもっと安定するといいのですが、なかなかうまくいきません。少し物申したいことはあるのですが、結果的に1番フルートがちゃんとしないことには、何を言っても説得力がないですからね。頑張ります・・。
3曲目は、尾高のフルート協奏曲。変拍子も慣れてきたようで、フルートとオーケストラのバランスも良くなってきました。4曲目はクラリネットのソロによる、オペラアリア集。こちらも調子は上向きです。最後5曲目は、ホルン協奏曲第3番。これは安心をして聴くことができます。
2012年10月6日(土)
今日も先週に引き続きダブルヘッダーでした。が、第1試合である午後コマに出番がありましたが、都合により参加できず。また、夜のコマは弦楽器の分奏でしたので、全く楽器を演奏することが出来ませんでした。残念。
2012年9月29日(土)
午後コマと夜コマ練習の、ダブルヘッダーの日です。個人的には反省点の多い練習でした。
午後コマは10/21の演奏会の曲で、ソリストが参加しての練習です。1曲目は尾高のフルート協奏曲。ざっと1曲通した後、部分的に練習。主に、ソリストとオケの音楽の感じ方のすり合わせに重点がおかれていました。変拍子での微妙な拍の感じ方を揃えるのは難しいですね。曲はとてもいいです。
2曲目はホルン協奏曲。こちらは、いくつか難関があるものの、音符を追いかけるという意味では易しいのかもしれません。ただ、モーツァルトらしくなるかないかは、ちょっとしたニュアンスを意識することで、大分変わってくると思います。
ようやくフルートが出番の3曲目は、コルニドライ。この曲は重大な問題をかかえています。練習番号Eからの各楽器の音程・響きがまるで水と油で、聴くに堪えないサウンドが生まれています。上のメロディをフルートが担当しているので、とても責任を感じます。自分が率先して、もっと音楽の流れをつくっていくようにしなければならないのですが。このままではまずい。何とかせねば・・。
場所を変えての夜コマの部。12/9の演奏会より、ワーグナーのワルキューレです。こちらは雰囲気がガラッと変わりまして、大オーケストラによる肉食系の音楽です。今日は第1幕のジークムントとジークリンデが兄弟だと知る場面と、第3幕のヴォータンがブリュンヒルデを勘当する場面を練習しました。
楽譜に書いてあることをしっかり演奏することはもちろんですが、歌い終わりや、場面転換の音楽では、テンポがかなり揺れるので、そういうところは注意が必要です。これはシンフォニーにはないもので、毎回、指揮者がどのようなテンポでくるのか、楽しみです。
2012年9月22日(土)
10/21に行われる、協奏曲の演奏会の練習です。ソロ無し、オケのみで4曲練習をしました。
1曲目は、ブルッフのコルニドライです。情熱的な場面もありますが、全体的には静かで美しい曲。ということは、演奏する側には、繊細さが求められます。今日の練習では(も)弱音の演奏で萎縮して、実のない音を発してしまいました。要個人練習。
2曲目は、尾高尚忠のフルート協奏曲。フルートのオケ伴奏はありません。この作品は本当に素晴らしい。フルート吹きの間では有名な曲ですが、もっと演奏される機会が多くなってほしいと思います。少し厄介なのが、楽譜の版です。最初に作曲されたのが室内楽編成で「作品30a」と呼ばれるもの、もう一つは後に2管編成に書き直された「作品30b」と呼ばれるもので、両方とも作品として残っています。
オーケストラが実際に演奏する場合には、パート譜をレンタルする必要がありますが、これは「30a」が入手しやすいですね。ところが、販売されているCDやピアノ伴奏譜付のフルートソロ譜では、「30b」の方が圧倒的に世の中に多く出回っているという現実があります。今回演奏するのは「30a」ですが、私がCDで聴いていた演奏は、名手ランパルが演奏する「30b」でした。
練習を聴いていみて、少し曲の雰囲気になれる必要があるかな、と思います。自分が演奏に参加できないのは残念ですが、是非この素晴らしい作品を素晴らしい演奏で聴いてみたいです。
3曲目は、オペラアリア集で、カルメンとトスカ、ポギーとベスの3曲。特にカルメンとトスカは、大好きなオペラなので、吹いていてとても気持ちがいいですね。トスカはまだオペラでの演奏経験がないので、近いうちにピットに入って演奏してみたいです。
4曲目は、モーツァルトのホルン協奏曲第3番。雰囲気を作るのが難しそうです。つま先歩行が求められているのにしっかりかかとまで足がついてしまっている印象です。でも段々と良くなるでしょう。音はとても美しいです。
2012年9月15日(土)
前半はモーツァルトの「魔笛」です。前回の合奏で、周りとテンポ感のずれ(遅れ)があり、そこを修正するために、少し前向きな演奏を心がけました。多少は修正されましたが、まだ自然な音楽にはなっていないですね。曲のボリュームや技術的な難しさはワーグナーに軍配が上がりますが、その曲の雰囲気を表現する難しさでは断然にモーツァルトですね。前回の繰り返しになりますが、自分の演奏を隠してくれるものがなく、全てがさらけ出されてしまいます。非常に神経を使います。モーツァルトとワーグナーの個人練習の割合は、8:2くらいでちょうどいいかもしれません。
後半はワーグナーの指輪より「神々の黄昏」の譜読み。この曲は1995年に一度演奏をしていますので、今回が2回目です。抜粋されている場所も、オーケストラ単体で演奏するときの定番である、「ジークフリートのラインへの旅立ち」と「葬送行進曲」で同じです。曖昧な記憶では、多少カットをする場所が違うような気がしますが・・。
この曲では4本のワーグナーチューバやバストランペットなど、普段見かけない楽器が使われます。合奏も楽器がきちんと揃えば、もっとこの曲に相応しいサウンドが響くことと思います。
2012年9月8日(土)
いよいよ12/9に演奏するワーグナー、リングの練習開始です。リングといえば、上演に4日間を要する大作。序夜:ラインの黄金、第一夜:ワルキューレ、第二夜:ジークフリート、第三夜:神々の黄昏に分かれています。今回12/9の演奏会では、「ワルキューレ」と「神々の黄昏」の抜粋を演奏いたします。
今日は、ワルキューレの譜読みです。演奏する前から、あまりの譜面の黒さに、あちこちで悲鳴が聞こえてきそうでした。しかし、練習中は集中していて、最後まで無事に通すことができましたね。よかった!
12月の演奏会はオーケストラだけでなく、歌手の方々にも御出演いただきます。第1幕の前奏曲と第3場のジークムントとジークリンデが再会する場面。有名な第3幕のワルキューレの騎行とラストのヴォータンがブリュンヒルデを勘当する場面と、盛りだくさん。素晴らしい演奏会になってほしいですね。
リングのお話。今まであまり良く分からなかったのですが、私はこれで大筋を理解することができました。
2012年9月1日(土)
7月のマーラー終了後の夏休みも終わり、練習が再開しました。9月から12月にかけて演奏会が3つ続き、例年のスケジュールと比較すると、かなり過密スケジュールになっています。一つ一つ落ち着いて練習をしていきたいと思います。
今日は、モーツァルトを2曲。前半は、10/21に演奏するホルン協奏曲第3番。この曲はフルートの出番はありません。
後半は、12/9に演奏する魔笛。今日は序曲のみの練習です。オーケストラとしては過去に演奏をしていますが、私は初めて吹きます。モーツァルト、聴くのは大好きですが、演奏をするとなるとこれまた難しい・・。自分のフルートの演奏の全てがさらけ出されてしまう、そんな感じがいたします。何も自分を守ってくれるものはありません。
いつものことですが、自分がイメージしている演奏と実際に客席で聞こえている演奏とのギャップを、早くうめていきたいと思います。
これまでの特別企画
・No.34 マーラー:交響曲第1番「巨人」 アマオケ練習日記
(2012年7月)
・No33 ベートーヴェン:交響曲第9番「合唱」 アマオケ練習日記
(2012年4月)
・No32 カヴァレリア&ドヴォルザーク8番 アマオケ練習日記
(2011年11月・12月)
・No31 サン=サーンス:交響曲第3番「オルガン」 アマオケ練習日記
(2011年6月・7月)
・No30 ベートーヴェン:交響曲第9番「合唱」 アマオケ練習日記
(2011年2月)
・No29 ブラームス交響曲第1番&箏協奏曲初演 アマオケ練習日記
(2010年12月)
・No28 ティル・オイレンシュピーゲル&英雄の生涯 アマオケ練習日記
(2010年7月)
・No.27 コープランド&バーンスタイン&ガーシュイン アマオケ練習日記
(2009年12月)
・No.26 メンデルスゾーン生誕200年プログラム アマオケ練習日記
(2009年7月)
・No.25 ヴェルディ「レクイエム」 アマオケ練習日記
(2009年2月)
・No.24 ムソルグスキー:組曲「展覧会の絵」アマオケ練習日記
(2008年12月)
・No.23 ブルックナー交響曲第7番 アマオケ練習日記
(2008年7月)
・No.22 天地創造&シンデレラ&チャイ5アマオケ 練習日記
(2007年12月)
・NO.21 ベートーヴェン:交響曲第3番「英雄」アマオケ練習日記
(2007年7月)
・No.20 ショスタコーヴィチ:オラトリオ「森の歌」アマオケ練習日記
(2007年2月)
・No.19 コダーイ「ハーリヤーノシュ」アマオケ練習日記
(2006年12月)
・No.18 マーラー交響曲第2番「復活」アマオケ練習日記
(2006年7月)
・No.17 歌劇「カルメン」&「バラの騎士」組曲
アマオケ練習日記
(2005年12月)
・No.16 ツェムリンスキー交響詩「人魚姫」 アマオケ練習日記
(2005年7月)
・No.15 マテキフルート工場見学記
(2005年4月)
・No.14 Ph.ハンミッヒ木管フルート ノマタチューンナップ記
(2005年2月)
・No.13 ベートーヴェン交響曲第9番「合唱」 アマオケ練習日記
(2005年2月)
・No.12 新世界より&キャンディード アマオケ練習日記
(2004年12月)
・No.11 ロイヤルコンセルトヘボウ管弦楽団2004年日本公演レポート
(2004年11月)
・No.10 幻想交響曲&ラヴァルス アマオケ練習日記
(2004年7月)
・No.9 ハイドン交響曲全104曲 完全制覇日記
(2003年11月より)
・No.8 イスラエルフィルハーモー管弦楽団2003年日本公演レポート
(2003年12月)
・No.7 シカゴ交響楽団2003年日本公演レポート
(2003年10月)
・No.6 マーラー交響曲第5番アマオケ練習日記
(2003年7月)
・No.5 ギルバート・キャプラン
(2002年8月)
・No.4 月に1度はコンサートへ行こう企画2001年総括
(2002年3月)
・No.3 ウィーンフィルハーモニー管弦楽団2001年日本公演レポート
(2001年10月)
・No.2 マーラー交響曲第3番アマオケ練習日記
(2001年7月)
・No.1 ベルリンフィルハーモニー管弦楽団2000年日本公演レポート
(2000年11月)