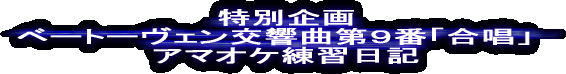
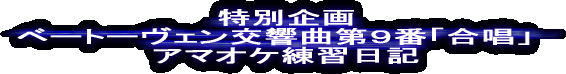
2005年2月20日(日)午後2時開演
市川市文化会館大ホール
ワーグナー:ニュールンベルクのマイスタージンガー 前奏曲
ベートーヴェン:交響曲第9番二短調「合唱」
指揮:岩村 力
市川交響楽団
2月20日(日) 最終回
いよいよ本番当日。いつものように、9時にホールに入り音出し。10時から第九を楽章順に、その後マイスターの練習をしました。ステリハは、個人的には修正がきかないほどピッチが周りと合わず、苦労しました。でも、それほど気にしていませんでした。なぜか、何とかなるだろう、と思っていました。今までの練習の時の感覚が残っていたからかもしれません。
昨日の課題であったテンポの確認、午前中のリハで全てチェックしました。うまくいったところもありますが、まだ怖いところもありました。指揮を見たほうが合わせやすいところ、周りを聞かないと合わないところ、色々です。私の技量でできる準備は、全てしました。
午後2時開演。マイスターが始まりました。この曲の練習時間は少なく、ステリハまで不安定な演奏でした。正直なところ、前プロから外れてくれないかなあ、と思ったこともあります。ところがところが、出だしから実に安定感のある演奏で、しばらく出番のないPicc担当の私は、聴き入ってしまいました。間違いなく、本番が一番の出来でした。演奏者である私が、安心して「聴ける」演奏でした。
休憩後の第九。午前中のステリハでは、ピッチがあわせることが出来ずにいましたので、とにかく舞台袖でのチューニングは、細心の注意を払いました。第1楽章、実際に音を出してみて、ピッチは私の感覚の許容範囲内に収まっていました。よかったよかった。木管のアンサンブルもそれなりに決まっていたように感じました。テンポを常に意識をしながら演奏をし続けたのが、今回は良かったように思えます。第1楽章、とても集中力の高い演奏だったと思います。
第2楽章、この楽章はリズムです。やや不安定なところも数ヶ所ありましたが、何とか崩壊せずに進みました。昨日の問題点であった491小節目からの四分音符、なんとかのこった、という感じです。相変わらず安定感はありませんでしたが、なんとかテンポキープをしようとしがみつきました。実際のテンポと体感テンポに差があり、ここは本当に難しいところです。
第3楽章、この楽章になり気持ちが落ち着きました。肝心の木管の美しいメロディはいいアンサンブルはできませんでしたが、その後はとても気持ち良く吹くことができました。体力面のペース配分もうまくいったと思います。ピッチもなんとか、許容範囲に収まっていました。
第4楽章、前の3つの楽章のテーマが順番に出てきますが、フルートにとってはかなり怖い場所です。特に第3楽章のテーマのところは、神経を使いました。それでもなんとかクリア。バリトンのソロで始まる歌も、なかなかいい出来でした。トルコマーチから二重フーガへ、順調にそしてエネルギッシュに曲が進んでいきました。最後は、指揮者岩村氏のパワー全快、オーケストラも火の玉になり突進!
今回で6回目の第九でしたが、間違いなく今日の演奏が一番感銘度の高い演奏のように感じられました。私はよく楽章と楽章の合間に客席を見るのですが、私が見る限りだれも寝ていませんでした。演奏側と聴く側が同じ気持ちを共有できた、一番嬉しいことです。ソリストの4人も本当にバランスが良く、ブラボーです。
しかしなんといっても今回の立役者は、指揮者の岩村氏だと思います。過去2回、氏の演奏会(アマチュア団体)を聴き、音楽が一切停滞することないその技量には、大変感銘を受けていました。そして今回、自分が岩村氏の指揮で演奏できるチャンスに恵まれました。私はこの演奏会に、珍しく1stに立候補をしました。それは、この難曲である第九を何とか克服したい気持ちと、岩村氏の棒で音を出してみたい、という2つの理由がありました。細かいことは多々ありましたが、私の出来うる限りの準備はしたつもりですので、このような大成功の演奏会に終わり、充実感でいっぱいです。
今回は練習を全て当日の会場である大ホールで行うなど、環境的にもとても恵まれていました。そういう環境を与えていただいたホール関係者、そして指導をしていただいたトレーナー諸氏に、深く感謝をしたいと思います。ありがとうございました。
2月19日(土)
前日のGPです。6時開始予定でしたが、事前に練習をしたかったため、5時前にホールに着きました。ホールでは、合唱の発声練習が行われていました。見慣れない私としては、かなり奇妙な光景に映りました。

今まで練習をしてきた中で、私一番の問題点は、演奏中にテンポが分からなくなることでしょう。今日は、楽章別にテンポが分からなくなる箇所をチェックしておきました。練習順に確認していきます。
第4楽章・・①763小節目からのAllegro ma
non tannto ②814小節目からのTempo Ⅰ
第2楽章・・①491小節目からの四分音符
第1楽章・・①253小節目から ②339小節目から ③511小節目からのソロ
第3楽章・・テンポに関しては特になし
第4楽章の①は、大分テンポが安定してきました。もちろん乱れることはありますが、少しずついい感じになっています。②はまだ指揮者との探りあいの段階です。明日のリハで要最終確認。
第2楽章の①は最悪です。今日は試しに指揮を見ないで自分の中にあるイメージと、周りを聞きながら演奏をしてみました。結果は空中崩壊でした。ここは暗譜をして、以前やっていたように指揮者を見ることで合わせる事にしました。
第1楽章の①は、まだ探りあいですが、なんとかつながってはいます。ここも要確認です。②は指揮を見ないで弦を聞いて入ることにしました。遅れ気味にも聞こえますが、以前の早すぎる時よりはましかなということで、このままでいくつもりです。③はとにかく後ろ、後ろに入ること。これに尽きます。
明日はいよいよ本番です。いろいろ問題点を列挙しましたが、オケ全体としては日に日にまとまってきていると思います。早めに寝て体調は万全にして・・。最後に、フルートの座席から撮影をした写真を掲載します。


2月13日(日)
連日の練習、しかも今日は朝10時から午後4時半までのロング・スケジュールです。
9時にホールに到着し、音だし。それから、木管の1番吹きだけ集まって大ホールで分奏。気になるところを、数箇所チェックしました。10時から予定通り、オーケストラ練習が第1楽章から開始されました。出だしはなかなかいい感じで進んでいきました。しかし、やはりというか、テンポをとりきれない部分が数ヶ所あり、その場の音楽の流れを止めてしまう危険性が・・。やり直す機会が何回かあったので、きちんとしたテンポで吹けるように、すこしずつくせをつけることができました。この楽章は、カウントを数えながら演奏をすることが必要かな、と思います。
次に第3楽章。ここはマエストロの指揮で久しぶりに演奏したのですが、振り方が大きく変わったため、少し戸惑いました。個人的にも、ピッチが周りとあわせることが出来ず、苦労しました。あれだけピッチの癖を事前に確認をしているのに、合奏になるといまだにできないでいます。なんとも情けない・・。
午後から合唱合わせの第4楽章。ここは合唱が主体になりますので、あまりオケは指摘されることはありません。合唱終了後、第2楽章の練習をしました。昨日指摘した、再現部の手前、かなりまずいです。今日は、どうして合わせることができず、吹くのを止めてしまいました。とうとう、ここまできました・・・。
残り時間で、前プロのマイスタージンガーを練習しました。ちょっと、まずいのではないでしょうか、この演奏では。どうなることやら。もう今は、クタクタです。

休憩中のオーケストラ・・
2月12日(土)
いつもの6時開始ではなく、本日は7時開始でした。ラッキーでした。というのは、その前に所用で車で少し遠方(電車では行けない所)へ行かねばならず、高速道路を突っ走っても6時過ぎに到着予定だったからです。
私はなんとか無事に時間前に到着したのですが、肝心のマエストロが到着していませんでした。スケジュールの調整で、行き違いがあったとのこと。約40分遅れで練習が開始されました。合唱は6時開始でしたので、トータルでは1時間40分遅れということになります。
さて、本日は初の合唱との合わせ。そうですね、声は結構出ていたと思います。第4楽章は、なかなか気持ち良く進みました。というか、合唱が入ったおかげで、オーケストラの細かいところが消されただけなのかもしれませんが。
ただ、他の楽章、特に第2楽章はいまだに大きな問題を抱えています。再現部の手前の箇所、どうしてもテンポがつかめません。ここは、根本的に楽譜の見方等を変えなければいけないかもしれません。
2月5日(土)
遅刻をして練習に参加をしました。ろくに音だしもせず、全体のチューニングにも参加せず、それでうまく合奏に入れる技術を持った人はいいのですが、私はそうではありません。きちんと事前準備をして、初めて周りと同じレベルになる、と思っています
そんなわけで、今日は音程がずっととれなく、苦労しました。先週は違っているのが分かれば、音程を修正できました。自分でも何か居心地が悪く感じられ、周りの方々はさらに気分が悪かったのでは、と思います。ごめんなさい。
第9の全楽章(通し)とマイスター。今日はもうこのくらいで勘弁をしてください・・・。
1月29日(土)
先週に引き続き、今月2回目の大村先生のレッスンを受けてきました。今までは、ほぼ月に1回のペースでしたが、来月は受けられそうにないのと、先週の第九のレッスンが途中になってしまっていたため、急遽受けることにしました。アンデルセンOp.21の5曲目は、先週やり直しになった曲。今回も成長が今ひとつで、不完全なまま先へ進むことになりそうです。今の次点で、この曲の雰囲気をつかみきるのは無理、と判断されたのでしょうか。先週も指摘された、音域によって響きが変わってしまうことが、改善されていませんでした。もう一度基礎練習から、指導を受けました。
一番の問題は、低音域の吹き方にあるようです。今は、唇が緩みすぎていて、かつ息だけたくさん入れようとしている状態。改善する方法としては、①唇にもう少し緊張感を持たせる、②ある1点を狙うつもりで息のスピードを速くする、③息の量はそれほど多くなく、を教えてもらいました。言葉は違うかもしれませんが、ニュアンスとしてはこのような感じです。意識を変えていきたいと思います。
さて、その後急いで第九の合奏に間に合わせようとホールへ行ってみると、なんと管楽器の分奏に変わっていました。大ホールで管分奏なんて、なんと言う贅沢な環境。でも、この変更は私にとっては嬉しいものでした。初め合奏で曲の全体像を掴んだら、細部を確認するために分奏。それからもう一度全体合奏を行うことが、いい練習方法の一つだと個人的には思っているからです。当初の練習予定では、一度も分奏が入っていなかったのです。
分奏ではかなり細かい練習をしたので、第1楽章と第4楽章だけで終わってしまいました。それでも、他のパートとのからみや、アーティキレーションの確認ができたので、とても有意義な時間でした。第1楽章は、ベートーヴェンらしい力強さを忘れずに、休符もまた音符の一つだと認識することが大事。第1楽章の練習といえば、以前指揮していただいた山下一史さんの練習を思い出しました。師匠であるカラヤンから相当影響を受けたのか、特に第1楽章にはこだわっていました。第4楽章は、メロディを他のパートと一緒に吹くことが多いので、やはりピッチをきっちりあわせる事が大事だとおもいます。
できれば、第2楽章と第3楽章も別の日にやりたのですが、時間的に無理でしょう・・・。
1月22日(土)
練習前に、大村先生のレッスンを受けてきました。アンデルセンOp.21の4曲目と5曲目。4曲目はあっさりOK。何の問題もなかったようです(本当かな?)。逆に5曲目は大変苦戦し、次回までにもう一度さらい直しです。「マルカート&スタッカート」の曲ですが、私が吹くと「スピッカート」の曲になってしまいました。要は、スタッカートのキャラクターの問題で、もう一度曲のイメージをし直しです。
それから、低音域から中音域、そして高音域への移行の際、響きが極端に変わるようです。そこを指摘されました(こういう指導を待っていたのです!)。先生は、モイーズの練習の仕方を例に、ロングトーンと音階練習の方法を教えてくれました。私の癖は、音が高くなると、それに連れて音が”開いてしまう”ことがあるようです。その後、余った時間で第九のレッスンも少しだけ、してもらいました。

文化会館大ホールの客席
なぜか壁を撮影してしまった
さて、岩村先生による第2回目の第九の練習です。もう今日は、何も申し上げることはありません。オケ的にはどうだったかは分かりませんが、少なくとも個人的には散々の内容でした。10日の初マエストロ練習の方が、よっぽどうまくいっていたような気がします。合奏中のピッチの修正はできない、途中で指揮のテンポとオケのテンポ、どちらも分からなくなって一人だけ勝手なことをやっている、等々・・・。挙げたらキリがありません。何でなんだろう。自分がここまでひどいのは、今までにはなかったです。んー、こまった、どうしよう。悩む悩む・・・。まあ、来週にはなんとかなっているでしょう(物事を深く考えずに問題を解決)。肝心の練習は、第1楽章から楽章順、通し練習中心でした。それから、マイスタージンガーを残り時間で練習をしました。
実はこの練習中に、「マテキフルート」を吹かせてもらったのです。大きなフルート専門店へいっても、なかなか見ることができないこの楽器を、ついに試奏しました。銀製の楽器でしたが、リップが14金。それにクラウンも金だったような気がします。H足部管のインラインリングキー、それにEメカ付きの楽器でした。実に美しい楽器で、欲しくなってしまいました・・。やっぱりインラインの楽器は、私には無理です。G音の時に、フニャ、となってしまいます。オフセットのリングキーの必要性を、再認識しました。どこに行けば「マテキ」を手に入れられるか、販売店を教えてもらいました。やはり、普通の店ではありませんでした。機会があれば、行ってみようと思います。
1月15日(土)
諸事情により、遅刻をして練習に参加しました。1stを吹くのに遅刻をするというのは、代理に吹いてくれる人がいるとはいえ、あまり気持ちのいいものではありません。第1楽章の途中からの参加、約40分の遅刻でした。
第1楽章、体力的に一番きつい楽章です。途中参戦のためか、個人的にはあまり指摘を受けることなく終わりました。第2楽章、この楽章はとにかく、リズムとテンポをキープすること、これにつきます。3拍子の箇所もそうですが、特に2拍子になったときにあらわる4部音符の下降系+上昇系のリズム、これには細心の注意が必要です。気をつけないと、ドンドン速くなってしまいます。弦と指揮者を見て、しっかりとアンサンブルをしたいところです。第4楽章は、時間の関係で少しだけ行いました。ここでは、ピッチ(ハーモニー)に乱れが気になるようです。透明感のある音を創りだせる木管サウンド、目指すものはこれです。
最後に前プロであるマイスタージンガーの初見を行いました。第九は約2年に一度のペースで演奏していますので、なんとなく勘が残っています。しかし、マイスターはそういうものがないので、かなりまとまりのないものになってしまいました。でも、今後も練習時間はしっかりと組まれているようですので、本番までにはきちんと仕上がるのでは、と思います。
1月10日(月・祝)
今年初のオケ練習、しかも初マエストロ練習です。
舞台設営の関係で、午後6時少し過ぎて練習が始まりました。音を出す前に、マエストロから楽器の配置換えの要望がありました。通常の市響の並びは、ホルンは上手、ティンパニは下手に並びます。しかし、今回はホルンが下手、ティンパニが舞台中央に構えることになりました。
さて、練習は第4楽章、第2楽章、第1楽章、第3楽章の順に進行。木管にとっては第1と第3楽章が体力的にきついので、ちょっと嫌な順番です。マエストロのテンポは、大変オーソドックスなテンポ。しかし、全く飽きることなく演奏をすることができます。演奏会本番へ向けて、期待が高まります。
今日はマエストロの指揮をしっかり見て、とにかくついていくのがやっとでした。まわりの楽器との連係なんて、考える余裕がありませんでした。ただ、このきつい曲をアシスタントなしで吹ききれたことは、今日の目標は達成です。あっ、もちろん、楽章の終わりのほうはもうヘロヘロでした。
12月18日(土)
2月の第九の初練習、また今年最後の市響の練習でもあります。私自身、この曲は6回目の演奏になります。ピッコロ2回、2ndフルート2回、そして今回は1stフルートで出演、2回目の1番です。実は第九の木管の1stは、マーラーやブルックナーよりも、遥かに体力を必要とする曲です。6年前に一度1番を吹く機会がありましたが、その時はほとんど休みのない楽譜にびっくり。疲れ果てながら演奏をした記憶があります。今回は珍しく、私自身が第九の1番を希望しました。前回の演奏よりも、もっといい演奏をしたい・・。その気持ち一つで立候補をしました。2月20日は、おいしいお酒が飲めるよう、練習を重ねていきたいと思います。
1回目の練習は、恒例により全楽章の通しです。練習指揮は、前演奏会の指揮者、金丸氏。第1楽章、チューニングをしたはずですが、私のフルートがまわりのピッチとかなり違うことに気がつきました。そういえば、足部管をいつものC足ではなく、H足にしているので、その辺りを注意しなければならなかったのです。H足は、C足に比べると特に第3オクターヴ響きがとてもいいのですが、ピッチのコントロールが少し難しくなります。高い音がよりピッチが高くなり、低い音がより低くなる傾向があるのです。しばらくC足で吹いていたので、その辺の感が戻っていませんでした。時間が経てば、解決していくと思います。
第2楽章は、指使いで多少混乱しているところがあります。これは、完全に個人練習で克服できることです。美しいメロディーの第3楽章、これは第1楽章同様、休みの少ない楽章で大変疲れます。第4楽章、出番も多いですが、休みも多いので何とか体力的には持ちました。
第1回目の練習ということで、まだまだ問題点は多いのですが、私自身は合奏をとても楽しめました。合奏をしているうちに、木管同士でピッチが少しずつあってきたり等、今日できることは出来たかな、と思っています。今日私が克服できなかったことは、第3オクターヴのD音とFis音のピッチ。これは最後まで全くまわりとブレンドしていませんでした。何とかしないと・・。
これまでの特別企画
・新世界より&キャンディード アマオケ練習日記
(2004年12月)
・ロイヤルコンセルトヘボウ管弦楽団2004年日本公演レポート
(2004年11月)
・幻想交響曲&ラヴァルス アマオケ練習日記
(2004年7月)
ハイドン交響曲全104曲 完全制覇日記
(2003年11月より)
・イスラエルフィルハーモー管弦楽団2003年日本公演レポート
(2003年12月)
・シカゴ交響楽団2003年日本公演レポート
(2003年10月)
・マーラー交響曲第5番アマオケ練習日記
(2003年7月)
・ギルバート・キャプラン
(2002年8月)
・月に1度はコンサートへ行こう企画2001年総括
(2002年3月)
・ウィーンフィルハーモニー管弦楽団2001年日本公演レポート
(2001年10月)
・マーラー交響曲第3番アマオケ練習日記
(2001年7月)
・ベルリンフィルハーモニー管弦楽団2000年日本公演レポート
(2000年11月)