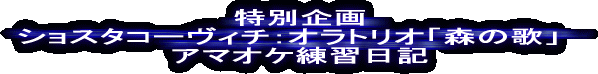
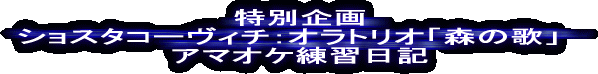
2007年2月18日(日)午後2時開演
市川市文化会館大ホール
ボロディン:中央アジアの草原にて(2nd Flute)
ボロディン:イーゴリ公より だったん人の踊り(1st
Flute)
ショスタコーヴィチ:祝典序曲(Piccolo)
ショスタコーヴィチ:オラトリオ「森の歌」(Piccolo)
指揮:岩村力
市川交響楽団
(終了いたしました)
2月18日(日)
本番当日です。ホール開館と同時に、楽屋入り。早速、一人でステージで音だしです。これは本当に気持ちがいい。とにかく、本番に向けて、自分が今できうることを最大限発揮できるように準備をすること。これに尽きると思います。今出来ないことがあれば、次回以降の課題にするしかないでしょう。
10時より、リハーサルを開始。本番と同じ曲順で、練習が進みました。中央アジア、音程とアクセントの確認。んー、もうひといきか。だったん人、出だしのフレーズ感とPからのアンサンブル。昨日よりは、良くなっています。お互いが聞く耳を持てるようになってきた、と感じました。休憩中に木管数名に声をかけたところ、皆さん私と同じ感触を持っていました。これがアンサンブルですね。次に、祝典。前半の木管のフレーズ、少し私のピッコロが走り気味でしたので、基本に戻り、ビートを感じながら演奏をしました。結果は○。最後は森の歌。第5曲目が、個人的なポイントにしていましたが、まあまあかな・・。もう少し合うといいけどな・・・。昨日がひどかったですからね。途中で指が全く回らなくなってしまっていましたから!マエストロの実に効率の良いリハーサルの進行で、予定時間を大幅に前倒しで終了いたしました。本番で最大限の力を発揮するための、マエストロの配慮だったと思います。
今回演奏した4曲のスコア
14時の開演。天気が良くなかったにもかかわらず、たくさんのお客様に来ていただきました。前売りの段階で、既に1200枚のチケットが売れていたそうです。こういった環境で演奏できることは、何よりもうれしいことです。さて、中央アジアから、演奏が始まりました。全体的にちょっと硬いか・・・。技術的にはそれほど難しくないものの、シンプルなつくりのため、全てが露出されてしまいます。とても緊張を強いられる曲です。続いて合唱団が入場して、だったん人です。合唱は、今日はよく声が出ていましたね。オーケストラも、それに触発されて、いい感じで演奏できたと思います。マエストロの力量は、ここでいかんなく発揮されていたともいます。クライマックスへ向けての高揚感の素晴らしさ!前回の第九も、こういう感じでした。また、この曲は個人的にとても課題が多く、色々考えるきっかけを与えてくれた曲だったと思います。練習の間、降り番で私にアドバイスをしていただいたAさん、ありがとうございました。
20分の休憩の後、祝典序曲です。オーケストラ全体で、とても苦労した曲です。テンポの変わり目で多少乱れたものの、これまでの練習を考えると、安定した演奏だったと思います。今日で終わるのは、もったいない。私も結局、全ての指回しをクリアすることはできませんでした。しかし、ちゃんと吹いているように思われるように、少し工夫(ハッタリ?)したつもりです。バンダを加えてラストのファンファーレも、ゴージャスな響き(マエストロの言葉より)だったのではないでしょうか。
そして、メインの森の歌。なかなか演奏される機会のない曲です。今回の演奏会は、本当にいい機会でした。個人的な課題であった5曲目も、許容範囲に収まったように思います。子供たちは、相変わらず素晴らしい音楽を披露していました。なんと生き生きとした音楽!聴きにきてくれた友人も、子供たちの歌を聴いて驚いた、というコメント。皆さん、この子達の歌声には、感銘を受けたようです。そして、なんといってもラストの7曲目です。マエストロもものすごい力が入っていましたね。曲中のルバートも、練習のときとは大きく異なりました。でも、本番ならではの雰囲気にピッタリのテンポ設定だったのでしょう、オーケストラも合唱もそれを自然に受け入れて、効果が良く表れていたと思います。練習時からの緻密な指導、そして本番での力の発揮のさせ方、マエストロの力量にはただただ脱帽です!(終)
2月17日(土)
本番前日のGPです。4曲、全て通しました。明日の午前中、練習する時間があります。まだ、猶予があります。全ては、本番当日です。早く寝ます。
2月11日(日)
マエストロ練習です。結局私は最後までマエストロとも、そしてオーケストラとも音楽を共有することができませんでした。困った、困った。譜読みを始めてから、ちょうど1ヶ月が過ぎ、曲の面白さと同時に、難しさも感じはじめています。1回ここできれいにリセットをして、新たな気持ちで1週間後の本番を迎えたほうが得策かな、と思いました。それでは、リセット開始。1、2、3、はい、終了。これで、気分一新です。
「森の歌」から練習開始。子供たちは相変わらず元気です。聴いていて、楽しいですね。音楽のスピードも若干前向きかな?5曲目の合唱の入り、やはり迷いが出てしまいました。なぜだろう、きちんとここは修正ができたはずなんだけどなあ。録音を聞き返してみたのですが、ここは3つのテンポが発生していました。オーケストラと合唱、そしてその間で迷っている高音木管郡。迷うはずです。では、ピッコロはオーケストラ(ホルン隊)に寄り添いたい、と思います。ここは、オーケストラだけを聴いたほうが、うまくいくかもしれません。7曲目のバンダ、演奏中のステージではほとんど音は聴こえませんが、客席では聴こえているようです。あれだけ距離が離れているので、テンポの感じ方が難しいでしょうね。その後、順不同で練習が進みましたが、1曲目が少し音楽が停滞しているように感じました。
続いて「祝典序曲」。この曲の面白さの1つに、スピード感があると思います。今日のマエストロのテンポは、曲の面白さを引き出す見事なテンポ設定だったように感じました。曲の良さを感じるテンポと演奏する側の都合によるテンポ、時にはなかなか合致しないこともあります。過去には演奏する側の都合だけを優先させてしまったな、と感じる演奏会もありました。そういう時は、やはり悔いが残るものです。今回は、マエストロのきびきびとした、見事なテンポ設定をキープしたいですね。ふーっ、指がまわりきらない・・・。
最後は「だったん人」。出だし、1週間前よりは良くなってきていると思います。細かいところを修正する必要はありますが、やはりフレーズを大きくとらえることと他の楽器への引渡しを意識することが、大きなポイントだと感じました。オーケストラ全体としてはまとまってきて、いい感じになりつつあります。個人的に吹けないところも、オーケストラ全体でかき消してくれて、助かっています。それでも、今日になっても改善されていないところ、しかも隠れようのないところがありました。練習番号Pからの、木管の動きです。その前の練習番号Oからのテンポをイメージしながら吹いているつもりなのですが、うまくいかないですね。木管の中でも、テンポの感覚が一致していないのが、さらにまずい。どうも笛が遅れ気味のようです。笛ってことは、オレか・・・。こういうところでテンポをキャッチできず、音楽を共有できないこと、アンサンブルをやっていて一番味わいたくない感触です。
今落ち着いて振り返ってみると、どの曲もオーケストラ全体としては、まとまってきていると思います。この流れは、持続したいものですね。当日は、普段の公演とは違い有料公演となりますが、是非多くの方々にお越しいただきたいと思います。詳しくは、こちらへ。
2月10日(土)
昼間、フルートのレッスンを受けてきました。レッスン室に入ってすぐに、師匠の楽器がいつもの14金ではなく、銀の楽器であることに気がつきました。14金は、修理に出しているとのこと。でも代わりの銀の楽器、これが只者ではありませんでした。なんと、アルバート・クーパーの楽器です!頭部管の「クーパー・カット」で有名な、あのクーパーです。トーンホールが通常の楽器と高さが違うこと、Eメカ、Cisトリルキー、そしてFisキー(初めて見ました)などがついていること、そして大型の機械を一切使わない完全な手作業だからできる精密なつくりのこと、などなど。面白い楽器でした。
今日は、C.J.AndersenのNo.22(写真左上)とNo.23、そしてビゼーの「間奏曲」(カルメン、写真右上)とメンデルスゾーンの「春の歌」、です。No.22とNo.23、このエチュードの中では比較的やさしい方だと思いますが、ボロボロでした。No.22、アーティキレーションが不明瞭で、全く音楽になりません。No.23、音の読み間違えが多数あり、曲になりませんでした。駄目だしをもらいながらも、2曲ともパス。そんな日もあります。名曲の2曲は、いつものように、さらに致命的な問題がありました。大きなフレーズで音楽をとらえていないため、途中で流れが停滞、もしくは途切れてしまうのです。カルメン、春の歌、両方同じ問題を抱えています。
残りの時間で、だったん人の出だしのソロを見てもらいました。吹き終わるなり、駄目だしです。この曲も、音楽を大きなフレーズをとらえていないため、音楽が途中で止まっているようです。しかもこのフルートの後には、クラリネットが続きます。きちんと受け渡しをしてあげないと!これでは、アンサンブルになりません。レッスンを受けるようになってから、①アーティキレーションのあまさ、②フレーズを大きくとらえる(1小節ごとカウントをとるような音楽にしない)、この2つを指摘され続けています。全て独力でやろうとしていた時(この時期のほうが圧倒的に長い)は、何が原因で自分の笛のレベルが上がっていかないのかが分かっていなかったので、それが分かっただけでも前進しているのかな?指摘され、自分で気がつき、いろいろやってみる。実際の演奏に反映されるようになるまで、あとどのくらいかかるか・・・。
夜はオケの練習。祝典序曲、中央アジア、そしてだったん人の順に、オーケストラだけで練習をいたしました。祝典序曲。この曲の私の課題は、きちんとビートを意識しながら、演奏をすること。意識はできたと思います。それにしても、大変な曲です。といっても、中学生・高校生の吹奏楽では、このくらいは平気でさらっています。若さってスゴイ!もちろん、B管やEs管の楽器が演奏しやすい調性に直されていますけどね。アマオケでは、あまり演奏する機会はありません。木管楽器、がんばって指をまわしましょう。金管楽器、まずは体力。弦楽器、この曲はエチュードです(!?)。続く中央アジア、これはハーモニーの確認をしました。こんな感じかな、という感触はつかめました。
個人的に問題の多い、だったん人。出だしのフレーズ、ぶつ切れにならないよう、大きく大きく音楽をとらえて、そしてクラリネットへ受け渡すように。演奏を終えて、そして録音を聞き返してみましたが、まだ自分がこうありたい、と思うものと距離があるように感じます。問題は一つだけ(フレーズ感)ではなかったのかな。自然な流れを感じるような音楽を演奏したい。自分が自然に感じたものがそのまま演奏に現れれば、理想だとは思います。でも今のところ、自然な音楽を表現するために、色々不自然な行為をしないとそこまでたどり着けないのが、もどかしい・・・。
明日は、マエストロ練習です。
2月4日(日)
合唱あわせです。今日は、昨日までにチェックしたことが、どのくらいできるようになるのかの確認をしたく、合奏に臨みました。昨日このページに書いたものを、コピー&ペーストします。
「だったん人」
①出だしの吹き方が不自然。コントロールされていない演奏、支えのない音。(結果→?)
②練習番号Pからの細かい動きで、周りの演奏を聴いていないのが、演奏に現れている。(結果→△)
③練習番号Pからの八分音符2つスラー、のパターンに鋭さがない。(結果→?)
「森の歌」
①5曲目の合唱の入りからテンポが行方不明になる。(結果→○)
今日の収穫は、森の歌の5曲目です。完璧にできるようになったら◎をつけたいのですが、そこまでは至らず。ただ、少しずつまわりの音が聞こえるようになったので、テンポもこういうことろを注意すればいいのかな、というのが分かってきました。体感のテンポで演奏してしまうと、先へ行ってしまいます。高速道路から一般道路に出たとき、どうしてもスピードをだしてしまう、あの感覚です。むしろ、テンポにブレーキがかかっている、と思うとちょうどいいかもしれません。
だったん人も、②については、多少まわりの音が聞こえてきましたので、1週間前よりも進歩はしているかな、と思います。①と③については、意識をして演奏をしていますが、はたしてどのように客席で聴こえているのかが、分かりません。録音をすればよかった・・・。来週チェックしようと思います。
合奏が始まる前、ピッコロの試奏をしました。詳しくは、こちらへ。
・トップへ戻る
2月3日(土)
この1週間、子供たちの歌う「どんぐりさん」が、頭の中でループし続けていました・・・。さて、今日はお休みで、明日が練習日という変則日程。ということで、今まで練習したところを振り返りながら、明日以降の練習に臨みたいと思います。
「中央アジア」
①弱音でのアクセント、ハーモニーの確認。
「だったん人」
①出だしの吹き方が不自然。コントロールされていない演奏、支えのない音。
②練習番号Pからの細かい動きで、周りの演奏を聴いていないのが、演奏に現れている。
③練習番号Pからの八分音符2つスラー、のパターンに鋭さがない。
「祝典序曲」
①常にビートを感じながら演奏を!
「森の歌」
①5曲目の合唱の入りからテンポが行方不明になる。
以上が、先週まで練習をして、録音を聞き返してみて気になったところです。その中でもだったん人、特に①は問題が大きいなあ、と思いました(写真左上)。なんというか、場違いな吹き方とでも言いましょうか。これが実際に演奏をしていて感じていなく、録音を聞き返してみて初めて分かったのが恐ろしい・・・。他のところでは、演奏しているときの感覚と実際に客席で聴こえているであろうもの(録音)が、それほど大きな差がないので、おそらくこういう弱音での演奏に問題があるのでは、と思います。演奏者のしっかりとした命令・コントロールがないので、楽器も困ってしまっているんだろうなあ。
ということで、久しぶりにだったん人の愛聴盤を取り出してきました。スヴェトラーノフ指揮のNHK交響楽団(写真右上)、99年のライブ録音です。フルートはパウエル社の木管を操る神田氏。以前、N響アワーで放送されていましたので、確認済みです。んー、自然な音楽だ・・・。練習が始まって1ヶ月経っていませんが、少し追い込みをかける時期になってしまいました。
・トップへ戻る
1月28日(日)
激務でした。午後から夜間にわたる、約5時間半の練習。少々疲れましたが、色々と発見があり、とても充実した時間でした。
昨日同様、中央アジアから練習開始。マエストロの指揮、とても自然な音楽に感じられました。いいテンポでしたね。このシンプルで美しい曲が、マエストロの適切な味付けによって、より素晴らしい曲になったと思います。ハーモニー一つ整えることで、そしてアクセント一つ加えることで、こんなにも曲の雰囲気を変えてしまう、マエストロの力量に脱帽です。
続いて、オケだけによるだったん人。個人的には、この曲が一番練習が必要でしょう。出だしや練習番号Cの前、そして練習番号Pのところ、などなど。問題なのは、指回しの難しいところで、周りの音を聴けないこと。完全に耳を塞いでしまっています。これでは、いい音楽はできません。周りの音も聴きながら美しい音楽を奏でられるようにする。美しい音楽をつくるためには、美しい音を出す練習だけでは限界があると思います。やはり、テクニックの克服が必要になってきます。だったん人の後は、これもオーケストラだけで、森の歌の練習がありました。ここで、30分の休憩。
休憩後は、テノール+バスのソリストに合唱団を加えて、森の歌の練習が行われました。この曲、通常の3管編成のオケに、ソリスト2名+混声合唱+児童合唱、そしてトランペット6+トロンボーン6のバンダまで必要な、とても大掛かりな曲です。今日は初めての歌合せでしたが、主役は児童合唱でした。この子達はスゴイ!!声も出ているし、何よりも素直に音楽を楽しんでいるのが、ビシバシ伝わってきます。音楽がはじてけています。実に新鮮です。こういう音楽が人をひきつける音楽なんだなあ・・・。本当に見習わないといけません。子供たちがあまりにも素晴らしかったので、オーケストラも混声合唱も、もうちょっと頑張りが必要になってしまいました。順番は色々でしたが、全ての楽章を練習しました。続いて、合唱付でだったん人の練習。これも森の歌同様、体力的にかなりきつい曲です。
合唱との練習はこれで終了ですが、オーケストラはまだ練習をする曲があります。そうです、祝典序曲です。ここまでくると、運動会のようですね。テンポの速い曲で、指回しはまだクリアできていませんが、なんとなくこうしたらできるようになるのかな、という感触はあります。それよりも、指が回った後で果たして周りとアンサンブルができるのか、今日の合奏をやってみて心配になってきました。これは、どんなテンポでもできるように、つまりアンサンブルができるようにしておかなければなりません。地道に、メトロノームでしょう。
これで今日の練習は終了いたしました。MDで録音をしておきましたので、これからは、イメージしている音と実際に客席で聴こえている音のギャップを埋めていきたいと思います。
・トップへ戻る
1月27日(土)
中央アジアと祝典序曲の譜読みです。
まず中央アジア。ゆっくりとしたテンポで、一つ一つの音を確認しながら譜読みが進められました。シンプルで静かな場面が多いので、音程やリズムの正確さが要求されます。それほど、技術的には難しくはない曲だとは思いますが、明日のマエストロ練習で、どのような雰囲気がつくられるのか、楽しみです。続いて、祝典序曲。これも、かなり遅いテンポで練習をしました。このテンポなら、指は十分にまわりそうです。とてもピッコロが目立つようにかかれた曲なので、演奏中どうしても余分な力が入ってしまうなあ・・・。
私のピッコロ演奏の一つの問題点ですが、この目立つようにかかれた場面で、目立つような演奏ができないこと、だと感じています。この曲に限ったことではないのですが、オーケストレーションが薄いときには問題がないのですが、少し音が重なる場面になるととたんにピッコロの音が消されてしまう。んー、ピッコロなのに何故だろう。何年も前から、自分でも気になっていました。中でも、2002年の第九、2004年の幻想、そして2006年のマーラー復活では、このことが原因でストレスさえ感じていました。祝典序曲でも、これらの時と似たような感触があります。やっぱり、響きの薄さだろうなあ・・・。
高音域の音は、とりあえず出すことができます(正確にはあてることができます)。H、C、そしてさらに上のCisも。特別な意識をしなくても、比較的楽に鳴らせます。でも、おそらくそれが十分な響きを伴っていないのでしょうね。だから、周りの音に消されてしまうのだと思います。この楽器を響かせることに関してですが、以前はフルートにも同じような感触がありましたが、今はそれがなくなり良い方向に解決をした、と自分では感じています。ピッコロでも、なんとかしたいなあ。フルートと同じ方法で解決するかは今のところ不明で、かつその方法がかなりリスクを伴うものなので、少し悩むところです。今回は、指の練習+豊かな響きの練習、をテーマといたしましょう。
明日は、マエストロ集中練習+初の合唱合わせです。
・トップへ戻る
1月20日(土)
今日は弦楽器のみの練習のため、管楽器はお休みです。でも、私にとっては都合が良かった・・・。暗くなるまで、ここで音楽とは全く関係のない理由で拘束されていれば、練習があったとしても、大遅刻をしていましたので。来週は、土日続けての練習予定です。
1月14日(日)
今回のマエストロ、岩村力先生の初めての練習です。私がマエストロの指揮で演奏するのは、今回が2回目。前回はベートーヴェンの第九でしたが、この70分に及ぶ大曲を、一瞬たりとも飽きさせない見事な音楽づくりで、大変感銘を受けました。マエストロの私のイメージですが、実はロシアのイメージが強いのです。NHK交響楽団の定期でのプロコフィエフをはじめ、ハチャトリアンやチャイコフスキーをプログラムにいれているのを、たびたび見ているからです。今回は、ボロディン2曲にショスタコーヴィチ2曲。まさにロシア三昧で、楽しみですね。また、今回はオーケストラ主催の演奏会ではないので練習日程が不規則ですが、左下の写真のように、本番のホールで練習ができます。練習場所は、とても恵まれています。
森の歌から練習開始。いいですね、マエストロの棒さばき。シャキッとしていて、音楽が常に生きています。1曲目から7曲目まで、途中ほとんど止まることなく通しました。テンポも、おそらく本番と同じテンポなのではないでしょうか。オーケストラも、今日はとても集中していて、マエストロの指示を聞き逃すまい、という気持ちが出ていたように感じられました。初日から、とてもいい雰囲気でした。後半はだったん人でしたが、大変な曲ではありますが、これもいい雰囲気で合奏が進められたと思います。
さて、今日試したかったのは、先週問題になったショスタコーヴィチでのピッコロ高音対策、耳栓の効用です。右上の写真、これを使ってみました。箱には、高周波のノイズを効果的にカット、交通量の多い交差点の騒音が静かなオフィス並みに、と記載されています。7曲目で実際に使ってみると・・・、これがすごい効き目!!右耳だけ耳栓をしたのですが、いくら高音域のトリルを吹き上げても、全く耳に支障がありませんでした。
ところが、新たな問題も発生しました。カットしてほしい音だけが聞こえなくなっただけでなく、聞きたい音まで聞こえにくくなってしまったのです。そうですね、ちょうど薄い壁1枚隔てた隣の部屋で合奏を聞いているような、同じステージにいるのに自分だけ別の場所にいる、なんとも不思議な感覚でした。方耳だけでも、こうなってしまうのですね。せっかくオーケストラの力強いサウンドを体感できる曲なのに、耳栓のおかげでそれができなくなってしまいました。今日は説明書に書いてある通り、きっちり耳の奥まで入れていましたので、次回は少し浅めに入れてみようと思います。
楽器だけでなく、耳栓の練習も必要になってきました。
1月6日(土)
さあ、1ヵ月半後の演奏会に向けて、今日から練習が始まりました。私自身が果たしてこの4曲を、1ヵ月半で消化できるかどうか不安もありますが、より良い練習方法を模索していきたいと思います。また、今回はショスタコーヴィチがメインですが、オケで吹き始めて15年目にして、初のショスタコーヴィチです。これも、今回の楽しみ。
そのショスタコーヴィチ、「森の歌」から練習が始まりました。全体がほぼ迷子にならず、最後まで通りました。曲の雰囲気はまだまだですが、初回の練習にしては、上々な滑り出しだったと思います。オーケストラ全体として一つ気になるのは、変拍子(1つ振りの3拍子+2つ振りの4拍子)の感じ方。かなりテンポを落としての練習でしたが、変拍子かつ音符が細かいので、時々音楽が崩れそうになる場面がありました。こういうところこそ指の練習を早く終わらせて、指揮を見る余裕+まわりを聴きながら演奏する必要があると思います。個人的には、出番の多い5曲目で、今日くらいのテンポならなんとか指がまわる感触を得ました。このテンポから徐々にテンポを上げていく練習をしていきます。
多くのピッコロ吹きは、曲によっては耳にコットンを詰めて演奏をするようです。最近日本でも人気があるプラハ交響楽団のソロピッコロ奏者、フィンダ氏もそういうことを言っていました。私自身は、どういうわけかピッコロの特徴の一つである劇的で鋭い音を出すことができないのですが、今までなかなかこのことが理解できませんでした。この曲はピッコロを担当いたしますが、初めて「耳栓」の必要性を感じました。なるほど、ショスタコーヴィチを演奏すると必要になるのか・・・。最後の曲で、最高音域のトリルが長く続くので、そこで自分の耳にかなりのダメージを受けるのです。フィンダ氏曰く、難聴になった人もいる、とか。本番のステージでは、いつもピッコロ用に用意するクリーニングペーパー+ガーゼー+掃除棒に加え、耳栓も用意しなければ。楽器はコンパクトですが、荷物は結構多い・・・。
後半は、だったん人です。こちらも、初回の練習にしては、まあまあだったと思います。個人的には、まず指回しをクリアしなければなりません。来月が本番ですから、それなりにスピードをあげて取り組んでいかないと・・・。
これまでの特別企画
・⑲コダーイ「ハーリヤーノシュ」アマオケ練習日記
(2006年12月)
・⑱マーラー交響曲第2番「復活」アマオケ練習日記
(2006年7月)
・⑰歌劇「カルメン」&「バラの騎士」組曲
アマオケ練習日記
(2005年12月)
・⑯ツェムリンスキー交響詩「人魚姫」 アマオケ練習日記
(2005年7月)
・⑮マテキフルート工場見学記
(2005年4月)
・⑭Ph.ハンミッヒ木管フルート ノマタチューンナップ記
(2005年2月)
・⑬ベートーヴェン交響曲第9番「合唱」 アマオケ練習日記
(2005年2月)
・⑫新世界より&キャンディード アマオケ練習日記
(2004年12月)
・⑪ロイヤルコンセルトヘボウ管弦楽団2004年日本公演レポート
(2004年11月)
・⑩幻想交響曲&ラヴァルス アマオケ練習日記
(2004年7月)
・⑨ハイドン交響曲全104曲 完全制覇日記
(2003年11月より)
・⑧イスラエルフィルハーモー管弦楽団2003年日本公演レポート
(2003年12月)
・⑦シカゴ交響楽団2003年日本公演レポート
(2003年10月)
・⑥マーラー交響曲第5番アマオケ練習日記
(2003年7月)
・⑤ギルバート・キャプラン
(2002年8月)
・④月に1度はコンサートへ行こう企画2001年総括
(2002年3月)
・③ウィーンフィルハーモニー管弦楽団2001年日本公演レポート
(2001年10月)
・②マーラー交響曲第3番アマオケ練習日記
(2001年7月)
・①ベルリンフィルハーモニー管弦楽団2000年日本公演レポート
(2000年11月)