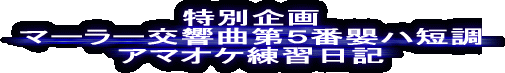
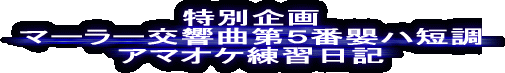
| 7月20日(日) 最終回 大好きなマーラーの交響曲、私にとっては、第1番、第3番、第4番に続いて4曲目になります。それまでは前期の作品でしたが、初めての中期の作品への挑戦でした。実はこの曲、3月1日の日記にも書きましたが、曲を複雑に感じ今一理解できないところがあって、あまり好きではありませんでした。しかし、演奏会を終えた今、やっぱりマーラー、素晴らしい曲ではありませんか! 前プロのマリンバ協奏曲、リハーサルまでソリストとオケのテンポ感覚に差があり、少し苦労していました。しかし本番の集中力で、その差はほとんどなくなり、とても気持ち良く吹くことができました。マリンバ協奏曲なんて、こんなユニークな曲が世の中にはあるんのですね。マーラー5番の前プロ、ということでもとてもいい選曲だったと思います。 いよいよメインのマーラー5番。過剰な緊張感もなく、平常心でステージに立つことができました。でも、今一演奏に集中することができずにいました。なんというか、他の楽器と距離、特に弦楽器との距離を感じてしまい、自分の中で一体感を感じることができなかったのです。当然、演奏時間も長く感じました。他の演奏者の中には、演奏時間が短く感じた人もいるので、これは私自身の集中力の問題でしょう。第5楽章になって、やっと集中することができ、これ以降は音楽をする喜びを感じていました。特にラスト3分間の盛り上がりはかつてないほどで、この時点で私はこの曲が好きになっていました。 聴いていただいた方からは色々な感想を頂きましたが、その中で特に印象に残ったのは、マーラー5番をここまで飽きずに聴かせてくれる演奏はなかなかない、というものです。私がこれまでにライヴでマーラー5番を聴いたのは、アシュケナージ指揮チェコフィル、井上道義指揮新日本フィル、アルブレヒト指揮読響、など。もちろん、アマオケの演奏も聴いたことがあります。しかし、部分的な素晴らしさは感じたものの、どの演奏も「一曲」飽きずに聴かせてくれるものはなかったのです。これが私が5番を好きになれない理由でした。ですから、先ほどの感想は、私にとっては、最高の喜びなのです。 次に演奏するのは第何番になるでしょうか。一番好きな第2番かな。楽しみです。(完) |
|
| 7月19日(土) 市川文化会館大ホールでのゲネプロ。初めて最初から最後まで、マーラーを通しました。通すと、結構いろいろなことが起きますね。まず無傷では最後まで行き着きません。突然メロディーが消えたり、ずれて入ったりと・・・。私個人もそうですが、最初のホールでの練習は、それまでの会場と音の聞こえ方が違うので、よく戸惑います。でも、今日はいつもよりその戸惑いが比較的少なかったですね。周りの楽器の音がよく聞こえましたから。マリンバも通し練習。まだソリストとオケで、テンポ感が違うところがありますが、大分その差は縮まってきました。 3月8日の日記で書いた、足部管をC管にするかH管にするかについて。結局そのままH管を使うことにしました。低音域のピッチの調整が大変ですが、それも練習でなんとかカバーできそうです。 さて、あす20日がいよいよ本番です。知人が、いつになくたくさん来てくれる予定です。楽しみです。 |
|
| 7月12日(土) 20分ほど遅れて練習に参加しました。こんな直前になって、1stが最初からいないなんて・・・。遅れて楽器の準備をしている時、客観的にオケの演奏を、わずか30秒ほどでしたが、聴くことができました。うん、なかなかいい仕上がり具合ではないでしょうか。 私個人の調子は、というと、これが良いのか悪いのかよく分からないのです。自分はここまでできればOKかな、と思っても、周りはそれ以上のことを求めているような、そんな感じです。先週の録音を聴いていても、そんなに音楽の流れが悪いとは思えないし、だから余計に今の状況が理解できていない。自分の自信のない個所に対して、過剰反応しているだけかな?本番1週間前なので、そう考えるようにします。 今日は全楽章から、問題のある個所をピックアップして練習が行われました。私に該当するところは、ピッチを注意するところが3箇所ほどと、フレーズの感じ方を直すところが1箇所。ほとんどは、演奏中に意識をすることで直せるところです。気を抜かずに演奏しないと。 マーラー5番の練習も大詰め。残すところ、ゲネプロのみとなりました。 |
|
| 7月6日(日) 朝10時から夕方4時半までの特別集中練習。何回ぶりだろう、こんなに気持ち良く吹けたのは。楽器もメンバーもきっちり揃っていたのも良かったですね。 マーラーは楽章順に練習が進みました。苦手の第1楽章、木管のアンサンブルも今までの中では一番良かったと思います。録音を聴き返してみて、もちろん?のところもありますが、少しずつまとまってきているのが分かりました。他の楽章も、とても気持ちよく吹けました。毎回同じ注意を受けているのに、いまだに直らない個所があることは、とても問題ですが。 最後はマリンバ協奏曲。初のソリストとの練習。まず、楽器を見てびっくり。すごいでかい。デジカメを持っていって撮影しなかったことを後悔しました。ソリストの演奏もこれまたびっくり。一音一音、こんなにエネルギーを使って叩いているなんて。見ているだけで圧倒されました。最初は、オケとソリストのテンポの感じ方に差がありましたが、徐々にまとまってきました。 今回は全身で音楽を感じるような、そんな演奏会になりそうです。マーラー5番の他団体の演奏は何回か聴いていますが、こんな面白い組み合わせのプログラムは、かつてなかったのではないでしょうか。7月20日は、是非市川文化会館へお越しください。 |
|
| 6月28日(土) 珍しく家で、合奏前に練習をしました。自分がどんな吹き方をしているのかを確認したく、MDで録音しながらです。苦手な第1楽章と、この後練習のある第5楽章をとりあえず。 プレイバックを聴いてびっくり。こんな非音楽的な吹き方をしていたとは。特に第1楽章の木管のアンサンブルの部分は悲惨そのもの。これでは気持ち良く合わせることなんて不可能でしょう。なんとか自分で直せるところは直しましたが、後は実際に合奏をしてみてどうなるか。第1楽章の次の合奏は、7月6日です。 さて、今日の合奏は第5楽章から。かなり細かい指示があり、この楽章だけで練習時間の大半を使いました。フルートにとって、部分的に指使いが難しいところはありますが、第1楽章と違って、音楽的にはそれほど難しくはないです。ラストのファンファーレは何度聴いてもかっこいいですね。ここまで飽きずにもってくるのはとても大変なのですが・・・。 弦楽器のみの第4楽章のあと、マリンバ協奏曲を練習しました。来週は、マリンバのソリストの方がいらっしゃる予定です。どんな技を披露してくれるのか、楽しみです。 |
|
| 6月21日(土) 絶不調・・。本番1ヶ月前に訪れた極度のスランプ。メンバーも楽器もほぼ揃い、演奏する条件としては、何も問題なかったはずなのに。 最初のチューニングの時から、アレ?、という感じで、周りと音が合っていない。でも、このところ演奏中に修正することが出来るようになったので、何とかなると思っていました。しかし今日はそれができなかった。ショック。吹いていても、そのことが気になって、とても音楽を楽しむことができませんでした。見せ場である木管のアンサンブルが台無し。きっと周りも合わせづらくて、困っていただろうな。 第1楽章と第2楽章、そして5分間くらい第3楽章を練習しました。はあ、今日のことは忘れて、また来週から新たな気持ちで頑張ろう・・・。 |
|
| 6月14日(土) 今日も途中から参加しました。前半はマリンバ協奏曲の練習。前にも書きましたが、第3楽章のピッコロがかなりの難所。第2楽章は休みなので、この間に何度も指回しの練習をしていました。まだ怪しい音はありますが、なんとか吹けた?かなと思っています。でも、もう一度やれといわれたら、出来ないかもしれません。 後半はマーラーの第3楽章。先週よりも若干テンポを上げて練習をしました。途中で演奏が止まってしまうことはないのですが、でもやっぱりもう一歩、という感じです。ところどころの小アンサンブルも、吹いていて今一すっきりとした気分になれません。難しい曲ですね・・・。 |
|
| 6月7日(土) 今日も遅刻かな、と思いましたが、最初のチューニングだけ間に合わず、合奏からは無事に参加しました。本当は事前にある程度吹き込んでおいて、チューニングをきっちりしておかないと、私の場合は非常に怖い。今日も最初は周りと音程が合わず、戸惑いました。でも珍しく、すぐ修正できました。 早川先生による第3楽章の練習。とても細かく指導していただきました。本番では1つ振りするそうですが、今日はテンポを落として、一つ一つの音符を確認していくような練習。特に、付点の感じ方について注意がありました。先生曰く、ウィーン風に、と。 この曲で最も演奏するのが難しい楽章だと思いますが、今日の練習で、大分楽章の全体像が見えてきたような気がしました。これからは、第3楽章の練習が毎回のようにあるので、なんとかこの難解な楽章を、本番までにはお客様に聴いていただけるような状態にまでなってほしい、と思います。 |
|
| 5月25日(土) 本番の指揮者、早川正昭先生による練習。珍しく最初から練習に参加しました。それが当たり前のことなんだけど・・・。 前半は第1楽章の練習。実はこの楽章、吹くのが一番苦手。木管トップのアンサンブルが何度かあるけど、吹きにくい音域で、しかも決して吹きやすくないフレーズなんだよね。きっちり出来たからって、TpソロやHrソロのように目立つわけではないし、かといってきちんと吹けないと曲全体の緊張感を失いかねない。とてもいやな場面。ここは要練習です。 休憩後は第2楽章と第5楽章。3月15日の日記にも書きましたが、第2楽章は私の一番のお気に入り。曲全体は複雑だけど、吹きにくいフレーズもないし、とにかく自分が演奏していて熱くなれる。早川先生のテンポも実にいいですね。少し早めのテンポで、どんどんオーケストラを巻いていきます。今の仕上がり具合では、ついていくのがきついですけどね。第5楽章も第2楽章同様、いいテンポで吹きやすいです。 |
|
| 5月17日(土) 今日も途中から参加。早川先生によるマリンバ協奏曲の練習。ちなみに自作自演です。やはり、先生のおっしゃることは説得力があります。それはそうです、作曲者が言っているのですから、他に考えようがないですよね。 今まで私がイメージしていたよりも、速めのテンポで、すっきりとした印象を持ちました。早くソリストと一緒に演奏したいですね。 後半はマーラーの第4楽章。ということで、管楽器は練習なし。 |
|
| 5月10日(土) 最後の5分しか練習に参加できませんでした。1stを吹くのに、こんな態度ではどうにもならない。本当にもう。こういう時って、一生懸命吹いたときより、何倍もの疲労感がある。一体、何のためにやっているんだろう。 |
|
| 5月3日(土) 前半はマーラーの第4楽章ということで、管楽器は出番なし。後半は、マリンバ協奏曲。 この曲、ピッコロが実にやばい。マーラーに比べれば・・、なんて思っていたけれど、先週書いた第3楽章のソロが大変。もう2割くらいテンポが遅ければ、きちんと指が回るけど、指定のテンポだと、全くはが立たない。ゆっくりからさらうしかないけど、まいったまいった。 全体的には打楽器が入ったおかげで、前回よりもまとまった演奏になっていたと思う。後は自分のピッコロをどうにかすれば、うまくいくでしょう。 |
|
| 4月26日(土) 前半は前プロのマリンバ協奏曲の譜読み。作曲者は早川正昭先生、つまり自作自演である。現代曲のわりには、まあまあ分かりやすかったですね。第3楽章で、マリンバとピッコロの見せ場があるので、ここはよく練習しなければ。 後半はマーラーの第5楽章。四分音符の3連譜から通常の8分音譜への流れなど、リズムの練習を中心に時間を割きました。今日は練習にいなかったメンバーが、管楽器を中心に多かったので、個人的には今一練習に集中できませんでした。 |
|
| 4月19日(土) 本番の指揮者、早川先生の合奏だったが、諸事情により全く参加することができなかった。腹立たしい限りである。 |
|
| 4月12日(土) 第2楽章、第3楽章の練習。かなり細かいところまで練習しました。今日は、とくにコメントすることはありません。別に調子が悪かったわけではないけどね。 |
|
| 4月5日(土) 本番の指揮者、早川正昭先生による初めての合奏。とても有意義な時を過ごしました。個人的な準備(30分前からウォーミングアップ)もし、かつ他のメンバーもほぼ揃っていたので、いい結果を出せたのだと思う。 今回使用するマーラー5番の楽譜は、最近、国際マーラー協会が出版した2002年版といわれる最新版。一番の大きな違いは、第3楽章でオブリガート・ホルンが、指揮者の隣で演奏すること。まさにホルン協奏曲!今日の合奏で、実際にやってみましたが、なかなかおもしろい。 早川先生曰く、「市響で世界初演するつもりだったが、ラトル+ベルリンフィルに先を越されてしまいました。しかし、日本ではおそらく初演になるでしょう。」。今後の合奏が、ますます楽しみになってきました。 |
|
| 3月29日(土) 諸事情により遅れて練習に参加。こういう日は本当にうまくいかないですね。私は、合奏開始の30分前から準備をし、きっちりチューニングをして初めて周囲と同じレベルになるのに。 第1楽章からの練習でしたが、周りとピッチが合わず、調整もきかず困惑しました。こういう時って、音楽を楽しむどころではなくなってしまうんですよね。本当にもったいない。遅れて練習に参加することがやむを得ない以上、途中参加でも周りと合わせることができる術を身に付けないと。 休憩後の第2楽章は、ピッチの問題は解決できました。前回同様、ピッチの感覚はおかしくなっていないようです。自分では曲に入り込めたつもりでしたが、実際に外に聞こえてくる音は、あまり気持ちがこもっていないようです。特にマーラーの音楽の激しさについては、かなり表現されていないようです。また課題というか、悩みが一つ増えました。 |
|
| 3月22日(土) 前半は出番のない第4楽章だったので、後半の第5楽章の練習から練習に参加。今日は実に気持ち良く吹けました。前回持ち直したピッチの感覚も、バッチリ。でも、この位ピッチが合っていないと合奏にならないよね。 合奏のできが良かったわけではないが、個人的には今出来ることを最大限に発揮できたということで、とても充実した気持ちである。まだまだ指が回らないところも多々ある。曲がつながらないところもある。それでも曲にのめり込めたという充実感は、滅多に味わえないことである。 これで全体の譜読みは終了。次回からもう少し掘り下げた練習になるだろう。周りについていけるよう、個人練習ももう少し積んでおかないと。 |
|
| 3月15日(土) 実は去年の6月くらいから、周りとのピッチが合わず悩みつづけていた。今日も出だしはその状態だったが、しばらくしてから周りと合うようになり、久しぶりに気持ち良く吹くことができた。先週と違い、遅刻をせずに会場に到着したことが、自分を落ち着かせそうさせたと思う。 第2楽章から練習開始。第3楽章と並んで、この曲のなかで最も複雑な楽章の一つ。私はこの曲で一番面白い楽章だと思っている。曲の雰囲気やテンポの変化が絶妙でなんともいえない。後半は先週できなかった第3楽章の最後を練習。 今会場で録音したものを聴き返しているが、自分の吹き方はその曲の雰囲気に合っていない。一言で言うと、音の立ち上がりがあいまいで鋭さがない。これは昔からの癖で、輪郭が曖昧になることが多々ある。自分で分かっていながら今まで治せないでいる。これから毎回録音をして聴きかえすことで、自分に改善を促していきたい。 |
|
| 3月8日(土) 今日は練習会場の駐車場が満車で入れず、仕方なく別の有料駐車場に。その駐車場へ行き着くまでに渋滞にはまり、結局30分遅れで練習に参加しました。第1楽章と第3楽章の練習でしたが、こんな状況でうまくいくわけがなく、演奏していていい気持ちにはなれませんでした。 私は曲により、足部管を使い分けています。音程が安定していて扱いやすいC足、そしてよりパワーのある響き(吹奏感)を得られるH足部管。おおよそ交響曲ではC、管弦楽曲ではHを使うことが多いですね。マーラーの場合は交響曲ですがH足を使いたいと思っています。 ところがこの曲、低音域での小アンサンブルが非常に多い! 私の癖もありますが、H足部管で演奏すると、低音域のピッチがかなり低くなってしまいます。フルートが目立つのはこういうところで、中高音域は他の楽器に消される可能性が・・・。となると、低音域重視でC足部管を選ぶのが賢明かもしれません。 どちらを使うかは、これから何回か練習をしていくうちに決めたいと思います。もちろん、このHP上にも載せる予定です。 |
|
| 3月1日(土) 7月20日の本番へ向けて、マーラーの交響曲第5番の練習が始まった。1月にもこの曲の練習が2回あったが、他の本番の「降り番組」のみでの、当然メンバーが揃わない状況での練習だったため、日記は割愛いたします。 日記を書いておいてなんですが、実はこの曲、素直に受け入れられる曲ではないんですよね。なにかこう、複雑で理解できない部分が多い。プロオケもアマオケも盛んにこの曲を取り上げるけど、なぜこんなに演奏頻度が高いのかが分からない。もちろんマーラーは大好きで、この曲も部分的には受けいれらるけど・・。練習を重ねていくうちに、少しずつ変わっていくことを期待します。 さて、今日は諸事情により、遅れて練習に参加しました。1stを吹くのに、こんな状況ではまずい。内容は全体の通し。やっぱり難しい。今日は以上。 |
|
| これまでの特別企画 ・月に1度はコンサートへ行こう企画2002年総括 (2003年1月) ・ギルバート キャプラン (2002年8月) ・月に1度はコンサートへ行こう企画2001年総括 (2002年3月) ・ウィーンフィルハーモニー管弦楽団2001年日本公演レポート (2001年10月) ・マーラー交響曲第3番アマオケ練習日記 (2001年7月) ・ベルリンフィルハーモニー管弦楽団2000年日本公演レポート (2000年11月) |
|