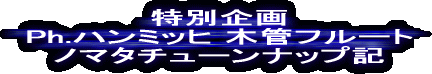
(2005年2月5日作成)
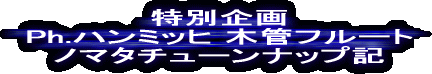
(2005年2月5日作成)


(左 リッププレートを取り付け全身本漆塗り 実に美しい! 右 キーの磨きもぴっかぴっか 新品以上の仕上がりです)
3ヶ月の修理期間を経て、ハンミッヒ木管フルートのチューンナップが完成しました。ケースを開けた瞬間、管体に塗られた本漆のあまりの美しさに、楽器を組み立てるのを忘れてしばらく見入ってしまいました。このページでは、チューンナップの内容と、その過程(私の楽器の場合)をご紹介いたします。
〜 チューンナップの主な内容 〜
・管全体に漆塗り ・リッププレート取り付け ・トーンホールアンダーカット
・タンポ、フェルト交換 ・キー磨き ・全体調整
チューンナップ、って何!?(2004年8月中旬)
1998年4月に衝動買い同然で購入した、Ph.ハンミッヒの木管フルート。木に触れる感触がなんとも心地よく、気に入っていました。ただ、その感触のよさは、吹きにくさを伴うものであったので、どうしても使う場面は限られてしまいます。音色は気に入っているんだけど、もう少し吹きやすくならないのだろうか・・・。
購入から6年以上たった去年8月、フルート関係のHPを検索したところ、偶然
Nomata FLute SAの野亦氏のHPにたどり着きました。そこで、初めてチューンナップ、という言葉を目にしたのです。ピッコロや木管フルートが、修理をする感覚で生まれ変わる、という内容。これなら、私の今の悩みを一発で解消してくれるかもしれない、そう思ったのです。
しかし、すぐには行動できませんでした。変わるといわれても、どのくらい変わるものだろうか、本当に吹きやすくなるのか、と。サンプルの楽器を試奏できればいいのですが、そういうものはありません。どうすればいいか、迷いながら何度も野亦氏のHPを眺めていました。
チューンナップを決断!(2004年10月中旬)
HPを発見してから2ヵ月、チューンナップを本気で考えるようになりました。博物館の楽器ならいざ知らず、演奏目的の楽器であれば、常に調子のいい状態できちんと吹けるものでなければ意味がない。そう思い、早速野亦氏にメールで連絡。チューンナップの内容について、代金支払方法、楽器を届ける方法など、6点ほど質問をしました。野亦氏からの返信は、それはもう実に丁寧で、かつ詳しいものでした。氏がどうして木管フルートのチューンナップを始めるようになったのか、それを解決するための楽器づくり(改造)の研究、漆の効用などの話しを聞いているうちに、是非自分の楽器を預けたいという気持ちになりました。事前にサンプルの楽器を吹くことはできませんが、きっとこのチューンナップはうまくいく、そう思いました。
何度かメールでやりとりをした後、楽器をNomata
Flute SAのある愛知県豊橋市へ、宅急便で送りました。ちょうど大型台風が上陸している時で、雨が降りしきる中、コンビニまで楽器を持っていきました。翌日野亦氏より、無事に楽器が届いたとの連絡。実際に野亦氏が試奏をして、楽器をチェック。その時点で、オーバーホールなど、修理内容について細部を相談をしました。
チューンナップ作業を開始!(2004年11月初旬)
11月に入ってすぐに、チューンナップを開始してもらいました。野亦氏のメールによると、管体に塗る漆の作業が時間がかかるのだそうです。ですので、とにかく管体からキーやポストをばらすことから始まります。トーンホールのアンダーカットをして、管全体を磨き、キズを修正。その後、管体についている楽器を黒く見せる染料を除去するために、アルコールで洗浄をします。これは、漆がよく硬化するために、やるのだそうです。以上が下準備。
いよいよ漆塗り。これもいっぺんにできることではなく、まず生地を整えるために下塗り。漆は、1回塗ると4〜5日くらいおいて硬化をさせます。下塗りは、その作業を3回くらい行うそうです。下地が整うと、今度は本塗りに入ります。これと平行して、頭部管のリッププレートもつくり始めます。
途中経過!(2004年12月初旬)
1ヶ月経過。この時点で、胴部管の漆塗りが完了。頭部管も下塗りが終了し、リッププレートを取り付け始めているところ。しかし、足部管は下塗りすら、終わっていませんでした。頭部管や胴部管より木の目が粗く、なかなか目止めができないそうです。私の楽器だけではなく、ハンミッヒはだいたいそうなのだそうです。
足部管に問題あり!(2004年12月末)
まだ足部管が出来上がりません。頭部管は、リッププレートをつける関係で、他の部分より時間がかかるのですが、それでももうじき仕上がる雰囲気。胴部管に至っては、すでにキーにタンポを組み込んである状態。どうしても、足部管の目が止まらないようです。暮れ・正月を返上で、作業に打ち込む野亦氏。
やっと楽器が組みあがる!(2005年1月中旬)
漆塗りがやっと終わり、キーを組み立て、ともかく楽器が1本になりました。これから調整です。ところが、当初の思惑通りには行かず、あまりよく楽器が鳴らなかったそうです。通常のハンミッヒの管厚は4mmですが、私のハンミッヒは3.5mm強。野亦氏も、ここまで薄い管の楽器は、初めて見たそうです。おそらく、そのようなことが原因ではないかと。それから、細い管でも鳴らせるように、頭部管の歌口の削り直しを始めました。最終調整、すこし手間取っています。
最終調整が完了&楽器が到着!(2005年1月末)
調整期間約2週間。ようやく楽器が、野亦氏のイメージしたとおりのものになったようです。野亦氏は、修理した楽器が完成すると、その楽器のイメージにあった曲を吹くそうで、私の楽器は、モーツァルトのフルート四重奏だったとのこと。最後にNomata Flute SAのエンブレムを取り付けて、見事完成。
翌日我が家に届き、早速ケースを開けてみる・・・。漆の見事な美しさ、新品以上にきれいになったキー、全てが驚きでした。楽器を組み立てるのも忘れて、しばし眺める。その後早速試奏。明らかにチューンナップする前より吹きやすくなっていました。音量、レスポンス、キーバランス等々。
楽器性能も格段に向上し、漆による美しい仕上げ。これはやらない手はないです!
これまでの特別企画
・新世界より&キャンディード アマオケ練習日記
(2004年12月)
・ロイヤルコンセルトヘボウ管弦楽団2004年日本公演レポート
(2004年11月)
・幻想交響曲&ラヴァルス アマオケ練習日記
(2004年7月)
ハイドン交響曲全104曲 完全制覇日記
(2003年11月より)
・イスラエルフィルハーモー管弦楽団2003年日本公演レポート
(2003年12月)
・シカゴ交響楽団2003年日本公演レポート
(2003年10月)
・マーラー交響曲第5番アマオケ練習日記
(2003年7月)
・ギルバート・キャプラン
(2002年8月)
・月に1度はコンサートへ行こう企画2001年総括
(2002年3月)
・ウィーンフィルハーモニー管弦楽団2001年日本公演レポート
(2001年10月)
・マーラー交響曲第3番アマオケ練習日記
(2001年7月)
・ベルリンフィルハーモニー管弦楽団2000年日本公演レポート
(2000年11月)