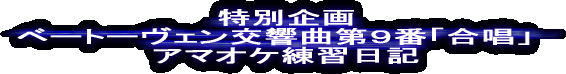
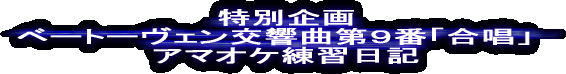
2011年2月19日(土)~20日(日)
市川市文化会館大ホール
チャイコフスキー:弦楽セレナーデより第1楽章
チャイコフスキー:スラブ行進曲
指揮:堺 武弥
市川交響楽団
(終了しました)
********************
2011年3月27日(日)午後2時開演
市川市文化会館大ホール
ベートーヴェン:交響曲第9番二短調「合唱」
指揮:船橋洋介
市川交響楽団
(公演が中止になりました)
~ この公演は中止になりました ~
2011年3月12日(土)
大地震翌日の第九の練習です。今も余震が続いていますので、今日は任意参加の合奏になりました。さすがに半分くらいの集まりでしたが、各パート平均して参加をしていましたので、合奏にそれほど不便は感じませんでした。
今日は急遽(練習会場に到着する直前に)1stを吹くことになり、しかも遅れて参加をしました。第2楽章、第1楽章の順番で、練習指揮者による、音楽の流れを大切にするとても充実した内容でした。テンポ変化指示のないところでも、場面によってじっくり演奏したり、流れるように演奏したり。理屈ではなく、感性の世界です。こういう音楽性があると、もっといい演奏が出来るようになると思うのですが・・。
2011年3月5日(土)
今日は第九の分奏です。管楽器は、贅沢にも、本番と同じ会場である大ホールで練習が行われました。今日は1st
Fluteの代奏です。いい時に代奏のチャンスが巡ってきました。演奏活動を続けていると、このように時々良いことがあります。
第4楽章から。出だしからNGの嵐。音の刻み始めが裏拍のため、パートによってタイミングが微妙にずれてしまい、音楽にベートーヴェンらしさが失われていました。もっと厳格に演奏をしなければ・・・。
散々フルートで演奏した直後に、ピッコロの出番。本番ではピッコロを演奏するのに、今日はいつもにも増して酷かった。十分な準備をした時でさえ簡単に演奏できるマーチではないのに、1番とピッコロを兼任なんてやはり無理がありました。フルートとピッコロは、違う楽器として考えた方が扱い易いことを再認識。落ち込みましたが、分奏はどんどん進んでいきます。
第4楽章の後は、第2楽章、第1楽章の順に練習が進みました。オーケストラで演奏してみると分かるのですが、第1楽章の集中力、そして曲の内面から湧き上がるようなパワーは、ちょっと他の作曲家では味わえない感覚です。やっぱりベートーヴェンは凄い!
本番ではフルートを吹かないので、周りの人には迷惑をかけてしまいましたが、今日はとても楽しむことが出来ました。ベートーヴェン、否が応でも熱くなります。
2011年2月26日(土)
今日から、3月の第九公演へ向けて練習を再開します。2回目のマエストロ練習。
第4楽章からスタート。初めて合唱を入れて練習をしました。ピッコロも、今までの中では、一番気分良く演奏が出来ました。が、出番が2箇所しかないので、頑張って演奏しようと余分な力が入ってしまい、楽器の響きを止めてしまう演奏だったのが大きな反省点。自然な脱力状態を目指しているのですが、そういう状態がくるのはいつの日か・・。
2011年2月20日(日) 本番2日目
”音楽祭”2日目は、大ホールでの各団体の演奏会が、メインになります。
今日は反響板をつけて練習
今日は9:00ジャストに、弦楽セレナーデからリハーサルが始まりました。約30分間の練習です。その後、スラブ行進曲の練習を約1時間練習。予定ではそのまま練習終了でしたが、パート練習が急遽追加になりました。フルートでは、3点ほどマエストロより特に練習するように指示がでましたので、1時間ほどそこを集中的に練習しました。
昼食の後、13:00より各団体の演奏がスタート。演奏曲目は以下の通りです。
13:00~ ①吹奏楽 A.リード:春の猟犬、 A.リード:交響曲第3番
14:00~ ②ジュニア・オーケストラ ハチャトリアン:「仮面舞踏会」組曲
15:00~ ③ジュニア・オケ+吹奏楽+合唱 シベリウス:交響詩「フィンランディア」、ヴェルディ:歌劇「アイーダ」より凱旋行進曲
16:00~ ④60周年スペシャル・オーケストラ(Sオケ) チャイコフスキー:弦楽セレナーデより第1楽章、チャイコフスキー:スラブ行進曲
(左)吹奏楽の演奏風景、(右)ジュニア・オケ+吹奏楽+合唱の演奏風景
出演するのは④だけですが、①から③は客席で聴くことが出来ました。共通して感じたことは、どの団体も一体感がある演奏だった、ということ。
さて、④のSオケの出番になりました。弦セレ、出だしの響きがとても良く、とても集中力のあるいい演奏だったと思います。続いて、管楽器が加わりスラブ行進曲。普段の演奏ではあまりない、若々しさを感じる演奏でした。強奏で演奏しやすい音符ではどんどん前に走る所は、ご愛嬌ということで・・・。でも、とても楽しい演奏でした。
2011年2月19日(土) 本番初日
2月公演は、2日間文化会館を全館貸しきって行われる”音楽祭”です。期間中、協会に所属する全団体(吹奏楽、2つの合唱団、ジュニア・オケ、シニア・オケ)が演奏するのはもちろん、公開リハーサル、ロビーコンサート、講師の先生によるリサイタル等、多彩な内容になっていて、市民の皆さん、御来場いただいたお客様と一緒に楽しめるような、そんな企画になっています。
2日間公演の初日は、公開リハーサルの日です。公開、といってもこちらはいつものように本番前日のGPと一緒ですので、気分的に変わりはありません。
反響坂がないままで弦セレの練習
今日は通常の演奏会よりも早く、8:30にホール入り。舞台設営をして、開会式です。開会式終了後、弦楽セレナーデの練習。本番が近づくにつれて、段々と響きが良くなってきました。続いて、スラブ行進曲。フルートは、先週課題にあがった箇所はもちろん、他にも2つ3つ課題が見つかりました。
お昼の後は、パート練習です。文化会館の1つの部屋を占領して、2時間近く集中的に練習をしました。音程、楽器の響きから音楽の感じ方まで、スラブ行進曲を題材に、密度の濃い練習が行われました。
パート練習後は再び全体合奏で、16:00に終了。18:00からは小ホールでのミニコンサートです。前半は団員による弦楽四重奏。結成から10年以上経過していますので、音楽的に素晴らしいことはもちろん、あうんの呼吸で生まれる音楽は、聴いていて心地の良いものです。
後半は、講師の先生によるチェロ・リサイタル。コダーイの無伴奏チェロソナタより最終楽章、そして現代曲であるソッリマのアローンが演奏されました。超絶技巧も見事ですが、重音の響きがあまりに豊かなのに、驚きました。
リサイタル終了後、明日の舞台設営をして1日目は終了。あっという間でしたが、振り返ってみると12時間近く、文化会館にかんづめでした。
2011年2月12日(土)
2月の演奏会の練習日です。今日は、スラブ行進曲のセクション練習。前半は管楽器の分奏です。管楽器だけとはいえ、一般公募メンバー+団員ですから、その人数の多さに圧倒されますね。
.jpg)
.jpg)
練習内容は、分奏ならでは細かな練習、縦線合わせ、音程合わせを中心に行われました。フルートの難しいところは、上の写真の部分。特に2ndはあまり普段使わないフィンガリングが出てきます。ホルンのシンコペーションとのアンサンブルが大切なところですが、十六分音符のフィンガリングに余裕がないため、アンサンブルの前に個々の練習が必要になってきました。
後半は、パート練習。先ほど問題になった4小節間を集中的に練習しました。テンポを落とし、一つ一つの音と指使いが確認できるところからの練習です。1小節だけ取り上げたり、2小節づつに分けたり、また4小節でつなげたり。数え切れないくらい、しつこく繰り返しました。
音はしっかりしているのに指が回らない人、逆に指は回るけどしっかり楽器を響かせられない人、自信を持てさえすれば吹ける人・・。色々な人がいます。どういう言葉をかけてあげれば、その人とってプラスになるのか。悩みながらも、一般公募メンバーが少しずつ上達していく姿に、感動を覚えました。
2011年2月5日(土)
2月の演奏会、2回目のマエストロ練習です。前半はスラブ行進曲。各パートごとに表情を付けることと、ニュアンスをそろえる指導がありました。改善された箇所もありましたが、マエストロが首をかしげる場面もあり、まだまだだな、という印象です。
フルートは一般参加者が1名お休みでしたが、先週お休みだった2名は参加されたため、これで全員の方とお会いすることが出来ました。皆さん緊張されているようで、和気藹々とはいきませんが、全員が楽しんでオーケストラで演奏が出来るようにしたいと思います。がんがるー。
後半は弦楽セレナーデ。客席から聴いていました。こちらはスラブより難しいのかな。そんな印象を受けました。でもいい曲です。レスピーギのリュートと同様、弦楽器がうらやましいと感じる曲の1つでもあります。
2011年1月29日(土)
今日は2月の演奏会の練習です。前回1/8の練習は欠席しましたので、私は一般参加者と初めてお会いしました。フルートは小学生、中学生、高校生、主婦と幅広く、6名の方が応募してくれました。残念ながら本日は2名の方が欠席。
前回は分奏でしたが、今日は全体合奏、マエストロ練習です。前半はスラブ行進曲。最初から最後まで通しました。後半を中心に返し練習。あっという間に終了時間がきて、少し物足りないと感じてしまいました。
後半は、弦楽器のみによる弦楽セレナーデ。管楽器は場所を移動して、パート別の練習です。まずは、楽譜の書き込み。今回使用する楽譜は、練習番号も小節数も記載がなく、合奏ではちょっと使いにくい。フルートは今回ピッコロも含めると4パートありますので、各パートでずれないよう番号の書き込みは慎重に行いました。残り時間5分ほどで、スラブのパート練習をして終了。一般参加の皆さんは、よく練習をしてきています。感心感心。
2011年1月22日(土)
今日は「第九」のマエストロ練習の初日でした。さぞかし充実した練習が行われたことと思います。
19:00過ぎに練習場所とはかけ離れた場所から、車で一般道+高速道路を使って移動。途中からJR線、そして営団地下鉄と乗り継ぎ、最寄りの駅に到着したのが練習終了時間の5分前。もしかしたら、ピッコロの出番の50%を占める最後のフィナーレだけでも吹くことが出来ないかと思い、そのまま練習会場へダッシュ。
到着すると、まさにフィナーレの直前部分を練習していました。急いで楽器を組み立てるものの、練習はどんどん進み、結局音を出さずに終わってしまいました。少しだけマエストロの指揮振りを見られたし、今日のところはこのくらいで勘弁してください。
2011年1月15日(土)
第九の第1楽章、第2楽章、第3楽章の練習です。ピッコロの準備をしていたのですが、出番はなし。1stフルートを重ねて吹いていました。本番のステージでは、ピッコロだけにするか、ピッコロの出番以外はフルート1番のアシストをするか、迷い中。
練習会場が十分な暖かさではなく、管が冷えきっていて、楽器を十分に鳴らせなかったですね。そんな状態なので、音程もいつも以上に???。マズイですねえ。
何度も演奏している曲ですが、これまでの練習では、まだ曲の感触がつかめません。楽譜の版の違いで影響が出ているとは考えにくいし。来週が本番の指揮者なので、そこで何とか感触をつかみたいところです。あ、来週はまた遠方で拘束されて、練習はおあずけ・・・。あー、あー、あー、あー。
2011年1月8日(土)
あけまして、おめでとうございます。今年も宜しくお願いいたします。
今日は2月の演奏会の初練習です。この演奏会は通常の演奏会と違い、小・中・高校生を中心とした一般応募の人たちと一緒に演奏をし、一緒にオーケストラを楽しもう、という演奏会です。私が入団してからは初めての企画であり、どきどきしながらも、楽しみにしている演奏会です。曲はオーケストラ全体で演奏するのが、チャコフスキーのスラブ行進曲。弦楽器だけで演奏するのが、同じくチャイコフスキーの弦楽セレナーデの第1楽章。曲の分かりやすさからいえば、2曲とも良い選曲だと思います。
パート別の練習が行われたはずですが、私ははるばる遠方へ追いやられてしまったため、練習に参加することができず。あー、あー、あー、あー。切腹。
2010年12月18日(土)
3月の「第九」、第1・第4楽章の練習です。
まずは第1楽章。音程、リズム、ハーモニーなどを細かく指導していただきました。細かく練習した後は最初から楽章の終わりまで通しました。とても有益な練習だったと思います。個人的には遅刻して参加をし、場にそぐわない音を出し、音楽を演奏する気持ちが整わないうちに練習が終わってしまいました。今日は練習に参加しない方が良かったかも・・・。第4楽章も同様。あーあーあーあー。さっさと家に帰りました。
2010年12月11日(土)
先週演奏会が終わったばかりですが、早速次回の演奏会へ向けて練習が始まりました。2月と3月に演奏会がありますが、今日は3月の「第九」の練習日です。私個人としては、7回目の第九。過去6回の内訳は1st2回、2nd2回、Picc2回で、7回目の今回はPiccで出演予定です。
今回の第九でこれまでと大きく異なることは、楽譜の”版”の違いです。今まではブライトコプフ版でしたが、初めてベーレンライター版を使用します。ざっくりな言い方をしてしまうと、ベートーヴェンの自筆譜に忠実なのがベーレンライター版、自筆譜を参照しながらも曲の前後から整合性がとれなものについて修正してしまったのがブライトコプフ版、と言えるかもしれません。
さて、練習は第1楽章から第4楽章まで、部分的にはかえしましたが、ほぼ通しの練習を行いました。練習の後半、ようやくPiccの出番となる第4楽章中間部のマーチでは、指揮者が一つ振りで振り出したのでびっくり。すぐに頭の切り替えが出来ず、目を閉じファゴットとクラリネットの音だけを聴いて、音を出しました。2つ振りだと決めてかかっていたので・・・。思い込みはいけませんね。
これまでの特別企画
・No29 ブラームス交響曲第1番&箏協奏曲初演 アマオケ練習日記
(2010年7月)
・No28 ティル・オイレンシュピーゲル&英雄の生涯 アマオケ練習日記
(2010年7月)
・No.27 コープランド&バーンスタイン&ガーシュイン アマオケ練習日記
(2009年12月)
・No.26 メンデルスゾーン生誕200年プログラム アマオケ練習日記
(2009年7月)
・No.25 ヴェルディ「レクイエム」 アマオケ練習日記
(2009年2月)
・No.24 ムソルグスキー:組曲「展覧会の絵」アマオケ練習日記
(2008年12月)
・No.23 ブルックナー交響曲第7番 アマオケ練習日記
(2008年7月)
・No.22 天地創造&シンデレラ&チャイ5アマオケ 練習日記
(2007年12月)
・NO.21 ベートーヴェン:交響曲第3番「英雄」アマオケ練習日記
(2007年7月)
・No.20 ショスタコーヴィチ:オラトリオ「森の歌」アマオケ練習日記
(2007年2月)
・No.19 コダーイ「ハーリヤーノシュ」アマオケ練習日記
(2006年12月)
・No.18 マーラー交響曲第2番「復活」アマオケ練習日記
(2006年7月)
・No.17 歌劇「カルメン」&「バラの騎士」組曲
アマオケ練習日記
(2005年12月)
・No.16 ツェムリンスキー交響詩「人魚姫」 アマオケ練習日記
(2005年7月)
・No.15 マテキフルート工場見学記
(2005年4月)
・No.14 Ph.ハンミッヒ木管フルート ノマタチューンナップ記
(2005年2月)
・No.13 ベートーヴェン交響曲第9番「合唱」 アマオケ練習日記
(2005年2月)
・No.12 新世界より&キャンディード アマオケ練習日記
(2004年12月)
・No.11 ロイヤルコンセルトヘボウ管弦楽団2004年日本公演レポート
(2004年11月)
・No.10 幻想交響曲&ラヴァルス アマオケ練習日記
(2004年7月)
・No.9 ハイドン交響曲全104曲 完全制覇日記
(2003年11月より)
・No.8 イスラエルフィルハーモー管弦楽団2003年日本公演レポート
(2003年12月)
・No.7 シカゴ交響楽団2003年日本公演レポート
(2003年10月)
・No.6 マーラー交響曲第5番アマオケ練習日記
(2003年7月)
・No.5 ギルバート・キャプラン
(2002年8月)
・No.4 月に1度はコンサートへ行こう企画2001年総括
(2002年3月)
・No.3 ウィーンフィルハーモニー管弦楽団2001年日本公演レポート
(2001年10月)
・No.2 マーラー交響曲第3番アマオケ練習日記
(2001年7月)
・No.1 ベルリンフィルハーモニー管弦楽団2000年日本公演レポート
(2000年11月)