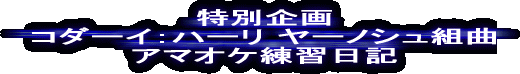
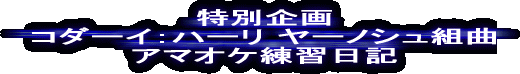
2006年12月24日(日)午後2時開演
市川市文化会館大ホール
J.シュトラウス:こうもり序曲
モーツァルト:交響曲第25番
ブラームス:ハンガリー舞曲集
コダーイ:ハーリ ヤーノシュ組曲
指揮:早川正昭
市川交響楽団
(終了いたしました)
12月24日(日)
本番当日です。練習は午前10時からですが、いつも私は午前9時に、ホールが開くのと同時に楽屋入りします。もちろん、この時間に来る団員はほとんどいませんが、約2000人のホールで堂々と一人で音出しができる、貴重な時間帯なのです。リハーサルは、モーツァルトの25番から始まりました。
続いて、こうもり序曲。昨日練習できなかったところは、この練習で確認することができました。フルート&クラリネットのユニゾンなのですが、なんとかなりそうです。少し、コツをつかむことができました。ハンガリー舞曲、これはやはりテンポの変化の確認が中心になりました。そして、メインのハーリヤーノシュ。主役のツィンバロン、ナレーションを入れて通し練習。午後1時過ぎまで、長めのリハーサルでした。
今回も打楽器は大きな仕掛け
こうもりとハーリヤーノシュで登場する、チャイム
予定通り、午後2時に開演になりました。ステージに上がって客席を見渡しましたが、今回も前回に引き続き、本当にたくさんのお客様に来ていただきました。ありがとうございます。1曲目のこうもり、今までの中で間違いなく本番の演奏が良かったと思います。音楽を楽しみながら演奏をすることがができた、からです。ソロのところで、少し体が硬直してしまいましが、まあ、今の私の力からすれば、あんなものでしょう。また、9月23日の日記に、音楽に使えるダブルタンギングをマスターしたい、と書きました。結論としては、まだマスターしていません。が、以前よりもいい感触をつかんでいます。ダブルそのものが全くできていないのではありません。ある特定の音形になったときに、崩れてしまうのです。その音形も、分かっています。後は、こつこつと練習をするのみです。2曲目はモーツァルトですので、楽屋で休憩をしていました。
休憩後は、ハンガリー舞曲集。演奏は、何とか指揮に食らいついていけたかな?お客様のアンケートを拝見すると、ツィンバロンの次に好評だったのは、この曲集でした。日本人うけするのかもしれません。この曲集は、アンコールで単発で演奏されることはあっても、プログラムで、しかもまとめて演奏されることはそう多くはありません。演奏した私も、貴重な経験をすることができたと思っています。
メインのハーリヤーノシュ。曲を演奏するだけでなく、音楽物語ということで、ナレーション付で進行いたしました。演奏する私も楽しめましたし、お客様も楽しまれたようです。これは、大正解だったと思います。そして、主役のツィンバロン。独特の音で、いいですね。うっかりしていて、写真を撮るのを忘れていました。目の前に楽器があるのに、もったいない。次にこの楽器と共演をするのは、いつになるのか・・・。打ち上げで、ツィンバロン演奏者である崎村潤子さんとお話しすることができ、ホームページを教えていただきました。アンコールのクリスマスフェスティバルも、なかなかの好演だったと思います。
さて、話は変わりますが、フルートを今の楽器に変えて1年数ヶ月が経ちました。音色に魅力を感じつつも、まだまだ自分の思うようにコントロールできていないなあ、というのが実感です。そんな中でも、頭部管の入れ具合(抜き具合)は今回の演奏会で、ほぼ固まりつつあると感じています。前の楽器と比較すると、かなり違うので驚いています。私がここのオーケストラで演奏するときには、このあたりがちょうど良い、というのを見つけました。
次の演奏会は、ショスタコーヴィチです!
12月23日(土)
前日のGPです。こうもりから練習を開始しました。かなり細かい練習が行われ、自分が試したいところが時間が足りなくない、カットされてしまいました。あーあ、明日にかけるしかないか・・・。続いて、ハンガリー舞曲。テンポの変化の激しい曲、まだテンポを共有できていない箇所があります。まだまだ、明日までには時間があります。
休憩後、ハーリヤーノシュ。初めて、主役のツィンバロンが登場いたしました。今まで、客席からステージにある楽器を見たことはありましたが、間近で見るのは初めてです。印象は、上にふたをしたら、ダイニングテーブルになりそう。ちょうど私もダイニングテーブルを持っていないので、ちょうどいいかもなあ。食事のときはふたをして、ふたをとれば即演奏可能状態。これはなかなかいいアイディアかもしれない。それはさておき、肝心の合奏ですが、ツィンバロンの影響もあり、いつも以上に演奏が引き締まっているように感じました。
明日も早いので、この辺で・・・。
12月16日(土)
オケの練習の前に、フルートのレッスンを受けてきました。10月より新しい師匠に師事していますが、月に1度、いいペースでレッスンを受けています。今日のレッスンは、C.J.Andersen
Op.21の20番と21番、そしてフォーレの子守唄とアルルの女のメヌエットです。
20番は、吹いていてとても楽しい曲です。エチュードではありますが、譜読みをしている時からどうしたら素晴らしいフルートの小品になるのかを、考えながら吹いていました。もちろん、パス。21番、テンポを少し落とし、落ち着いて吹いてみました。20番ほどではありませんでしたが、なんとか吹ききりました。これもパス。全部で24曲あるこのエチュード、そろそろ終わりが見えてきました。次は、T.ベームのカプリスに挑戦しようかなあ。
エチュードは順調に進んでいるものの、いわゆるフルートの名曲は、毎回問題が多すぎます。フォーレは8分の6拍子。横に音楽が流れていきません。全て縦割りの、不自然な音楽。あちゃー、これはひどい!師匠にも、毎回指摘されています。ただ、この悪いくせについては少しずつ自覚が出てきましたので、師匠に指摘され続けることで、より自然な音楽になっていくでしょう(そうありたい)。アルルは、何回か人前で演奏をしたことがあるので、フォーレほど問題は大きくありませんでした。
さて、オケの練習。前半は、モーツァルトの25番。もちろん、笛は休みです。モーツァルトに私の持っている笛(昔のではなく現代の)を見せることができたなら、きっとフルートを積極的に使ってくれたことでしょう。後半は、ハーリ・ヤーノシュ。打楽器もピアノも勢ぞろい。この曲は、編成がかなり偏っています。6曲で構成されていますが、それぞれ編成が異なります。つまり出番のある曲とない曲がありますので、ベートーヴェンやブラームスのシンフォニーと同じ気持ちで練習に臨んでいたら、ちょっと面食らってしまうでしょう。それでも、楽器が揃うと、曲も大分いい方向に向かっているような気がいたしました。
泣いても笑っても、あと1週間!
12月10日(日)
日曜日の特別練習です。午前中から夕方まで、オーストリア&ハンガリーの音楽漬けです。
モーツァルトの25番から練習を開始。出番なし。続いてハンガリー舞曲を番号順に練習しました。第1番はよく演奏される曲ですが、オーケストラのメンバーが過去に演奏した癖がついてしまっているような気がしました。私もこれまでに2回演奏しています。マエストロの解釈がメンバーに浸透するまで(過去の演奏の癖を忘れる)には、まだ時間がかかりそうです。第2番は、あまり演奏されない曲です。それゆえ、マエストロの解釈が自然と受け入れられるのでしょう。今日の練習で、第2番はテンポが大分固まってきました。この2曲の練習模様は、本当に対照的です。演奏経験の豊かさが、逆に曲の完成を遅らせているような気がいたしました。
ユニークな第3番、いい曲ですね。演奏をしていて、スリリングな気分になります。5曲の中で、特異な雰囲気をもつ魅力的な曲です。個人的には、今回の演奏会の曲で、1番気に入っています。続いて第4番、これも第2番同様、あまり演奏される機会がありません。マエストロの解釈も、自然とメンバーに浸透しているようです。第2番と同じ傾向です。最後は第5番。頻繁に演奏される曲ですが、なんとかマエストロ独自の解釈についていっているような気がいたします。
午後は、こうもりから。まず、出だし7小節目の音で、音が違うということで指摘を受けました。私が使用しているパート譜(カルマス版!)は「D」音。また、もっているミニチュアスコアは「E」音。実際の演奏を聴いてみると、クライバー指揮バイエルン歌劇場の映像では「E」音で演奏されていますが、小沢征爾指揮ニューイヤーの演奏では、はっきり「D」音で演奏されています。特に後者では、キュッヒル隊長率いるウィーンフィルが、ここぞとばかりこの「D」音を強調しているかのように感じます。また、東京文化会館の音楽資料室のオペラのスコアを閲覧したときには、「D」音になっていました。演奏も両方存在し、楽譜(スコア)も両方存在する。普段は、カルマス版のパート譜さえ疑っていれば解決していましたが、今回はそう単純ではありませんでした。今回は「E」音で演奏いたします。
さて、練習ですが、ワルツのリズムのとり方の練習が中心でした。マエストロによる、図を使った分かりやすい「音楽講義」によって、ワルツのリズムが整えられていきました。フルートが、ここのワルツに出番がないのが残念です。マエストロの求めるリズムが自然に感じられるようになったら、この音楽はきっと演奏している人も、聴いている人も楽しめることでしょう。
ラストはハーリ・ヤーノシュ。特異な編成ゆえ、ほとんど全ての楽器が揃わないと、なかなかこの曲の良さは分からないような気がいたします。でも、今ある楽器だけでも練習が必要なところは多々ありました。どのパートも、難しそう・・・。
本番2週間前になりました。これから、追い込みをかけていきます!
・トップへ戻る
12月9日(土)
マエストロ練習です。前半は、ハンガリー舞曲を全5曲、たっぷり練習をしました。主に、テンポ設定が中心の練習のように感じました。変化をつけないとなんとも面白みを持たない曲ですので、演奏中はアンテナを張りまくりです。CDで聴くような演奏に比べると、それでも変化のつけ方は緩やかなほうかな、と思います。しかし、あまり聴きなれないマエストロ独特のテンポ設定があり、個人的にもなかなかそれを消化しきれていません。早くオーケストラ全体で、マエストロの要求するテンポ設定・音楽に応えたいものです。
後半は、ハーリ・ヤーノシュ。演奏会当日は、なんとナレーション付で音楽が進行しますが、今日はその合わせ練習も行われました。そうですね、この曲はこういうお話があった方が楽しめる、と思いました。そしてピアノも今日から入りました。この曲のピアノは重要ですね。ピアノが加わることで、今まで練習をしていたのと別の曲のように感じてしまうシーンがあります。曲が曲だけに、全ての楽器が揃わないと、本当の曲の良さは見えてこないのかな、と感じました。
明日は、日曜日の特別練習です。
・トップへ戻る
12月2日(土)
今日は、合奏がないため、私の出番はありませんでした(合奏があっても遅刻をしていたので、よかったかも)。練習の出番が少ないので、合奏の中で「気がつき」、「修正」をしていくことがなかなかできません。個人練習の中で、そういう状況をイメージしていかないと・・・。
今回の演奏会の私のパート割ですが、こうもりが1st
Flute、モーツァルトは笛なし、ブラームスが2nd
Flute、そしてコダーイが2nd Flute(全員Piccolo持ち替え)です。私としては、ピッコロの出番が少なく、極めて珍しいパート割です。このところの曲、人魚姫、カルメン、ブリテンの青少年、マーラー復活と、立て続けにピッコロを担当していました。もちろん、ピッコロは好きで吹いていたのですが、せっかくフルートをマテキにしたので、フルートでも楽しみたくなりました。
1番フルートとピッコロ、どちらが魅力的なパートか。返答に困りますね。どちらも魅力的ですし、それぞれの楽しみがありますので。1番フルートはなんといっても、木管の1番同士、特にオーボエと一緒に音楽を創っていけるところです。フルートとオーボエのオクターヴユニゾンは、楽しみの一つ。ピッコロは、オーケストラという枠の中にありながら、かなり自由を与えられているパート、という感じがします。これをファゴット吹きの人に話をしたら、コントラファゴットを吹くときもそういう感覚がある、とのことでした。立場が似ているのかも。
フルートを吹く人の中には、ピッチのことなど、色々なマイナス面を理由にあげて、ピッコロをあまり好んで吹かない人がいるようです。でもですね、よく見てみると、フルート吹きの多くはフルートを吹くついでに、あるいは持ち替えがある場合のみピッコロを吹いていることが多いのです。つまり、フルートとピッコロを対等に、同じ時間練習したのなら、ピッコロに対してもっと違った感想が出てくるのかな、と思っています。
・トップへ戻る
11月25日(土)
2回目のマエストロ練習です。前半は、モーツァルトの25番。客席でじっくり練習を見学しました。モーツァルトって、演奏をするのは難しいんだなあ。でも、マエストロの適切な指示を演奏側が理解したときには、モーツァルトの素晴らしさが演奏に現れていました。練習あるのみ、です。
後半は、こうもりから。前回の練習で、曲全体のおおよそのテンポは分かったつもりでした。が、テンポの変化の激しい曲なので、今日になってもこのテンポで曲が壊れてしまうところが数箇所ありました。マエストロのテンポ設定は、かなり独特ですが、説明を聞くと納得してしまう設定なのです。この曲は私は1番フルートを吹きますので、なおさらテンポの理解は必要になってきます。
1番を担当するときに大切なことがあります。それは、まわりを聴くことも大切ですが時には自分の音楽のペースに合わせさせること、です。今日はそれができなかった!私自身が色々さぐってしまい、「基準」がぶれてしまいました。これでは、周りの方はアンサンブルがやりにくいですよね。今日の私の大きな反省点です。
さて、メインのハーリ・ヤーノシュ。初のマエストロ練習でしたが、んー、いい言葉が見つかりません。もう少しまとまりがあっても、良かったのになあ。いまひとつ、私も含めて全体がこの曲に入り込めていないように感じます。それを強く感じたのは、2曲目のウィーンの時計台。長調の明るく楽しい曲、のはず。でも、出てくる音楽は決して明るくなく、楽しさが感じられるものでもなく・・・。演奏している人がそう思っているなら、客席で聴いている人は、そういうものを感じてしまうだろうなあ。こういう演奏だけは、決してやってはいけない!
ハーリ・ヤーノシュを、もっと聴いてみよう・・・。
11月18日(土)
今日は、弦楽器の分奏のため、管楽器はお休み。練習したい・・・。
前回7月の演奏会のDVDが、1ヶ月ほど前出来上がりました。もうすでに何回繰り返して見たでしょうか、すでに脳に焼き付いている場面もあります。
左はDVDとジャケット、右はテレビ画面を撮影しました。何回見ても聴いても、いい曲ですね。オーケストラの仕上がりも、6ヶ月間みっちり練習をすると、ここまで精度が上がるのかな、と思いました。いつもの3ヶ月、もしくは1ヵ月半で本番の時とは、明らかに違いが感じられます。ただ、この6ヶ月間の練習期間というものは、おそらく私が入団して初めてのこと。本当に恵まれた期間だったのだと思います。私としては、1番好きな曲を長期間練習することができて、良かったですけどね。
ただ、毎回このように長い練習期間をとれるわけではありません。限られた時間の中で、最大限の努力をして演奏会に臨むことは、毎回同じこと。短い練習期間のときには、それなりの意識と方法で、頭を切り替えていきたいと思います。
11月11日(土)
本番のマエストロ、早川正昭先生による初合わせです。私自身がマエストロの指揮で演奏をするのは、今回で4回目。1994年には、マエストロのお嬢様(NHK交響楽団)との共演で、ピエルネのハープ協奏曲。2003年には、マエストロが作曲したマリンバ協奏曲の自作自演。毎回のように、特徴のある演奏会でした。今回も、ハンガリー舞曲の第2番、第4番、第5番は、マエストロの手による編曲版です。
今日の前半は、モーツァルトの25番。笛は降り番。後半から、合奏に参加をしました。
さて、シュトラウスのこうもり。合奏が始まって、少し戸惑いました。通常CDなどで聴いている演奏と、大分雰囲気が違うなあ・・。でも、マエストロの解説を元に楽譜を見直してみると、それが実に楽譜に忠実。毎回のことですが、研究者としてのマエストロに、敬服いたします。指揮そのものだけでなく、こういった楽譜の解釈やそれに至るプロセス(歴史的背景など)を聞くのを楽しみにしているのは、私だけでしょうか。肝心の合奏ですが、マエストロの新鮮な解釈になんとか食らいつこうとしている、そんな状況です。これからですね。
次は、ブラームスのハンガリー舞曲集。今回の演奏会では、第1番から第5番の5曲を演奏いたします。今日は、その番号順に合奏が進みました。どの曲も熱い熱い音楽なのですが、その中で第3番はちょっと趣が違います。室内楽的な場面もあり、演奏をしていて音を、そして響きを楽しむことができるのです。いい曲だなあ。他の曲では、オーケストラ全体での表情の変化はありますが、室内楽的な響きのする場面はありません。第3番は、プログラミングという意味でも、いい選曲のような気がいたします。
・トップへ戻る
11月4日(土)
オケの練習はありましたが、全体合奏ではなかったので、ちょこっと練習をして帰宅しました。
オケの練習の前、フルートのレッスンに行ってきました。先週に引き続いてのレッスンですが、11月はこの日しか行けそうになかったので、2週連続になりました。曲はC.J.AndersenのOp.21より、18番と19番。18番はほぼ問題なくクリアしました。19番もクリアはしましたが、自分では消化不良に感じています。原因は、「B♭」「A♯」の指使いにあると感じています。
多くの人は、フルートを吹き始めた時、この音は右人差し指のキーを押さえるのを最初に覚えるのかもしれません。しかし、私はブリチアルディキーを押さえる方で最初に覚えました。吹奏楽の曲の場合、Es-durやB-durが多いので、このブリチアルディキーだけで困ることは余りありません。ところが、オケになるとあらゆる調の曲が出てきますので、この指使いだけでは色々と問題が出てきます。「新世界より」の2nd
Fluteの第1楽章のソロでは、ブリチアルディキーで演奏しようとすると、かなり困難ですね。私もオケで吹くようになって、必要性を感じて右人差し指を少しずつ使うようになりましたが、今でも意識をしない限り、癖でブリチアルディキーを使ってしまいます。このキーが悪いわけではないのですが、その場に合った指使いができるように、自然な使い分けができるようになりたい、と思っています。ということで、この19番のエチュードも、この音で少し苦労しました。
今回よりエチュードだけでなく、所謂フルートの名曲もレッスンしてもらうことになりました。今日は、フォーレの「シチリアーノ」と「子守歌」の2曲です。エチュードよりも、こちらの演奏の方が問題が大きかったですね。まず、音楽を全て縦割りで感じてしまっていることが問題。特にこの2曲は、横の流れが大切な曲です。これでは、あまりのセンスのなさに、演奏を聴かされているほうが苦痛を感じてしまうでしょう。
この指摘は、実は初めてではありません。以前にも、室内楽の演奏をしていて、音楽を縦線きっちり演奏するところと、流れを大切にするところを区別したほうがいい、という指導を受けたことがありました。その時は、おそらく自分で消化しきれなかったのでしょう。でも、今日はどうしたら曲が自然な流れになるのか、を細かく指導してもらいましたので、今後はいろいろな場面で、音楽の流れを意識した表現を目指したい、と思います。
今日は、大きな収穫のあった日でした。
10月29日(日)
モーツァルトのレクイエム、本番の日です。もちろん、私は出演しません。が、所属するオーケストラの演奏を客席で聴く機会はめったにないことなので、お客として聴きに行きました。
前回のマーラー復活は、オーケストラが主体の演奏会で、今日のモーツァルトは、合唱主体の演奏会です。オーケストラは、本格的に練習を開始したのが9月から。練習は一度も見に行きませんでしたが、練習期間の短さから、少し仕上がりが心配でした。でもそんな心配は、演奏を聴きはじめて、すぐに吹き飛びました。結構揃っているじゃん。前回、6ヶ月間練習をしたマーラー復活とは比較できませんが、限られた時間内で、最大のパフォーマンスを発揮していたように感じました。必死になって、さらったんだろうなあ・・・。
さあ、次は12月の演奏会です。これからは、練習に参加できなくてストレスを感じることも、なくなるでしょう!
10月28日(土)
明日は、モーツァルトのレクイエムの本番。ということで、今日は前日のゲネプロです。笛の出番はありません。しつこいですが、明日も出番はありません。なぜなら、モーツァルトだからです。ベーム式のフルートがモーツァルトの時代に誕生してくれていたら、もっとフルートの出番が増えただろうなあ。
1ヶ月ほど前、私の笛の師匠の送別会のことを書きましたが、今日は新しい師匠による初レッスンでした。曲は、今までの続きでAndersen
Op.21の第16番と17番です。この2曲は、Op.21の中では比較的易しい曲ですが、あまりうまくいきませんでした。初レッスンということもあり、体全体に余計な力が入っているのが原因でした。いつも力んでいる右手はもちろん、今日は口までも!それでも、2曲はとりあえずパス(本当にあんなものでいいのか不安)。2曲とも共通する注意点は、アーティキレーションをはっきりさせること、でした。
フルートのレッスンは、それほど時間をかけず、今後のレッスン内容や、フルート談義などを話している時間が多かったですね。師匠が使っているこだわりのフルートについて、リングの穴の大きさが通常より大きいこと、H足部管の小指キーのサイズがC足部と同じサイズであること、ブリチアルディキーが限りなく管体によっていること、などなど。そして同じように、ピッコロのことについても、色々教えていただきました。やっぱりドイツタイプの楽器が良いのかなあ。また同郷(?)ということもあり、共通の知人も多く、そして自宅も近いことことから、話がどんどん広がっていきました。
さあ、これからのレッスン。前の師匠の教えを土台にして、さらに新しい師匠で腕を磨いていきます!
10月21日(土)
ようやく12月の演奏会の練習日になりました。オケの中で音を出すのは、1ヶ月ぶりです。ここまで、本当に長かった・・・。前半はモーツァルトの25番なので、笛は休み。
後半は、ハンガリー舞曲集から。今まで、何度か演奏会のアンコールで、演奏したことはありました。今回は、プログラムの中で演奏をいたします。演奏をするのは、第1番から第5番の5曲。初めての音出しだったのですが、さすがはブラームス、面白かったですね。また各曲の編曲は、第1番と第3番がブラームス自身、そしてその他の3曲は、なんとマエストロ早川の編曲版!
5曲のハンガリー舞曲。どれもジプシーの雰囲気が満載の、魅力的な曲です。その中でも第3番は、とてもいいですねえ。5曲の中では、特異な雰囲気を感じますが、本当にチャーミングな曲。以前、ラトル指揮ベルリンフィルがアンコールで演奏していたのを聴いた事があるのですが、そのとき以来、お気に入りの曲になっています。また第4番は、ブラームスの交響曲第3番を連想させるような、哀愁漂う曲。どの曲も素晴らしいです。
続いてハーリヤーノシュ。今日は、楽器がそろっていたので、合奏していて楽しかったですね。ハーリは、以上。
・トップへ戻る
10月14日(土)
今日も、そして明日もモーツァルトの「レクイエム」。またしても、笛は休みです。来週は、ようやく12月の演奏会の練習コマがあります。これほど長くオケの中で吹くことができないでいると、ストレスを感じてしまいます。オケの練習がないのなら、12月の曲をちょっと予習しておきましょう。
喜歌劇「こうもり」のDVDを鑑賞しました。もちろん、指揮はカルロス・クライバーです!この映像、数年前にも見てはいるのですが、こうもりではなく、クライバーが目当てで見ていました。久しぶりですが、クライバーはいつ見ても格好いい!流れるような、そして美しい音楽!こんな演奏ができたらなあ・・・。テレビ画面の映像を、デジカメで撮影しました。
肝心の物語も、今まではあまりよく知らなかったのですが、解説書とDVDの映像で、一通り理解できました。序曲で登場するフレーズが、オペラのどの場面で使われるのかも、だいたいイメージできました。実に単純明快な、分かりやすく、そして楽しい作品ですね。聴いている人に、その楽しさが伝わるような演奏がしたいものです。
10月7日(土)
今日もモーツァルトのレクイエムの練習日。また出番なし。10月の演奏会が先なので、しょうがないですね。毎週のように続いている、モーツァルトの「イジメ」にもめげず、今日もHPを更新します。それにしても、早く合奏に参加したい・・・。

このHP作りに欠かせないもの、パソコンを最近新しくしました。左が新しいVAIO、右が今まで使っていたVAIOです。6年前に購入したもの(OSはWindows
98 SE)を今まで使っていたのですが、ハードディスクから今まで聞かれなかったような異常音がでるようになり、替え時と判断。3台目のパソコン(1台目はマック)ですが、3台ともノートブックです。
今回は当初、スペック的に優位なデスクトップ型の購入を考えていましたが、結局断念しました。どうしてもあの大きなものを、部屋に置く気にはなれないのです。大きなものといっても、アルトフルートやパスフルート、そしてダブルコントラバスフルートだと、平気で置いてしまうでしょうねえ。
9月30日(土)
モーツァルトのレクイエムの練習日。よって私は休みです。モーツァルトは笛が嫌い・・・。
練習が休みでしたが、私の笛の師匠を囲んで飲み会があり、参加をしてきました。実は師匠がかなり遠方に引越しをされてしまうため、もうレッスンが受けられません。今日は、師匠の送別会だったのです。いつもは、1対1のレッスンだったため分からなかったのですが、門下生がこんなにたくさんいたとは!師匠とも、そして初めてお会いする門下生の方とも、とても楽しく話ができて、良かったです。
9月23日(土)
今日は、12月の演奏会の練習日です。前半はモーツァルトの25番。もちろん、フルートの出番はなし。後半は、こうもりとハーリヤーノシュ。
まずは、こうもりから。やはり、素晴らしい曲ですね。短い曲ですが、アンサンブルをしていて、とても楽しい曲です。曲の雰囲気は、まだまだ出来上がっていませんが。12月までには、少しでもウィーンフィルのもつ雰囲気に近づきたいですね。この曲の後半には、どうしてもダブルタンギングが必要なパッセージがでてきます。これを機会に、ダブルタンギングをマスターする(今はいい加減なダブルしかできない・・)ことが、今回の私の技術面での目標です。
ハーリヤーノシュ、楽章により楽器編成が大きく異なります。有名な第2楽章は、管楽器と打楽器のみ。第4楽章は、ピッコロ3本+トランペット+トロンボーン+打楽器の極端な編成。編成だけでなく曲の雰囲気も、「こうもり」のような自然な流れの音楽とは異なるので、少し頭を切り替えないとなりません。技術的な難しさよりも、曲の雰囲気を理解するほうが難しく感じます。
9月16日(土)
モーツァルトの「レクイエム」の練習日のため、フルートはお休みですが、少しばかりレクイエムのネタを。
モーツァルトと同じくらいよく演奏されるレクイエムの一つに、フォーレの作品があります。これは、モーツァルトと違い、フルートの出番があります。でもですね、あまりうれしさを感じない使い方なんですよね。写真をご覧下さい。
左が、フルートのパート譜の全てです。1ページのみ。右は、譜面の上部のアップです。1曲目、2曲目、3曲目が休み。4曲目の「PIE
JESU」で、ようやくフルートの出番です。さあ、どんなメロディが登場するか・・・。
左の写真が上2段、右の写真が下2段、全部で、4回の出番があります。そして、楽譜の下には、5曲目、6曲目、7曲目は休み、と記されています。レクイエム全体は30分強の曲ですが、フルートの演奏時間は、おそらく1分ないでしょう。2001年にこの曲を演奏する機会があり、ティンパニやホルンの譜面と見比べましたが、音符の数で完全に負けていました・・・。
どうして、こういう楽器の使い方を、するのでしょうね。どうしても、ここはフルートの音が必要だったのでしょうか。フォーレは、他の作品ではフルートにとても美しい作品を残しているので、この楽器が嫌いだったとはとても思えないのです。モーツァルトの時代と違って、楽器も現在使われている、ベーム式の楽器になっているはずですし。
フルートの出番のないモーツァルト、出番はあるけどほとんどが休みのフォーレ。どちらにしても、笛吹きとしては寂しい作品です。
9月9日(土)
今日は、12月の演奏会の練習です。ようやく、シーズンの幕開け!、といったところでしょうか。前半はこうもり序曲、後半はハーリヤーノシュを練習しました。
高校生の時、私の恩師が指揮をするということで、初めてアマオケの演奏会に行きました。それまではずっと吹奏楽をやっていて、管楽器のアマチュアの音は耳にしていたものの、弦楽器のアマチュアの音は聴いたことがありませんでした。CDではウィーンフィルやベルリンフィル、コンサートホールではN響や日フィル。私の弦楽器の音は、これらのオケのイメージしかなかったのです。演奏会の1曲目は、こうもり序曲。演奏を聴いていろいろなことを感じましたが(詳細は省略!)、私が初めてアマチュア・オーケストラの音、そして弦楽器の音を聴いた、思い出(?)の曲です。ちなみにそのオケとは、今私が所属しているオケです!
さて、こうもり序曲の練習。私も含めて、この曲を初めて演奏する方がほとんどでした。が、曲は皆さん良くご存知で、イメージは各々もっているなあ、と感じました。そのイメージが、本番までに方向がそろうことを願います。楽器の練習同様、オペラの物語を知っておくと、演奏の向上につながるかもしれません。私は、このオペラは「きちんと」見たことがなないので、DVDで鑑賞しておきたいと思います。やはり、クライバー指揮、でしょうか。
後半のハーリヤーノシュ。こちらの曲も演奏したことはないものの、よく耳にしていた曲です。私が中学・高校の頃、この曲やダフニスとクロエ、ドビュッシーの海、ローマ三部作、などは吹奏楽で演奏されることが流行っていましたので。でも、ハーリヤーノシュは、なぜか今一共感できずにいました。分かりやすいメロディーが部分的にあるものの、1曲通しては聴き通すことができませんでした。今日の初練習を終えても、あまりその印象は変わっていません。でも、練習をしていくうちのその曲の良さが見えてくる(例:ブルックナー8番)こともありますので、今後の練習に期待したいと思います。
9月2日(土)
今日から、いよいよ練習が開始、といきたいところですが、私の開始は来週から。私が出演するのは、上記の12月の演奏会ですが、オケとしては、その前の10月に演奏会があります。曲は、モーツァルトの「レクイエム」。当然、フルートは出番がありません。今日は、そのレクイエムの練習日なのです。練習がない、出番がない、というのはつまらないですね・・・。
モーツァルトは、私が大好きな作曲家の一人ですが、モーツァルト自身は、(当時の)フルートをあまり良く思っていなかったようです。音量が出ず、しかも音程も良くない。レクイエムに限らず、モーツァルトの作品にはフルートが使われていないものがかなりあり、冷遇されている、といってもいいでしょう。数年前、某大手フルートメーカのハンドメイド・フルートの広告で、こんなキャッチコピーが使われていました。
「誰よりもモーツァルトに聴かせたい」
私も、同感です。現代のフルートをモーツァルトがもし見てくれたのなら、きっとフルートの出番が増え、フルートの魅力を最大限に引き出す、素晴らしい作品を数多く残していたのでは、と思います。本当に、残念。
昼間は、明日の恵比寿での室内楽コンサートの練習をしてきました。明日の場所は、恵比寿麦酒記念館、開演は午後1時です!
これまでの特別企画
・⑱マーラー交響曲第2番「復活」アマオケ練習日記
(2006年7月)
・⑰歌劇「カルメン」&「バラの騎士」組曲
アマオケ練習日記
(2005年12月)
・⑯ツェムリンスキー交響詩「人魚姫」 アマオケ練習日記
(2005年7月)
・⑮マテキフルート工場見学記
(2005年4月)
・⑭Ph.ハンミッヒ木管フルート ノマタチューンナップ記
(2005年2月)
・⑬ベートーヴェン交響曲第9番「合唱」 アマオケ練習日記
(2005年2月)
・⑫新世界より&キャンディード アマオケ練習日記
(2004年12月)
・⑪ロイヤルコンセルトヘボウ管弦楽団2004年日本公演レポート
(2004年11月)
・⑩幻想交響曲&ラヴァルス アマオケ練習日記
(2004年7月)
・⑨ハイドン交響曲全104曲 完全制覇日記
(2003年11月より)
・⑧イスラエルフィルハーモー管弦楽団2003年日本公演レポート
(2003年12月)
・⑦シカゴ交響楽団2003年日本公演レポート
(2003年10月)
・⑥マーラー交響曲第5番アマオケ練習日記
(2003年7月)
・⑤ギルバート・キャプラン
(2002年8月)
・④月に1度はコンサートへ行こう企画2001年総括
(2002年3月)
・③ウィーンフィルハーモニー管弦楽団2001年日本公演レポート
(2001年10月)
・②マーラー交響曲第3番アマオケ練習日記
(2001年7月)
・①ベルリンフィルハーモニー管弦楽団2000年日本公演レポート
(2000年11月)