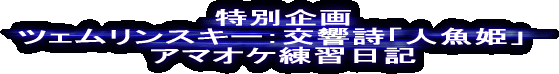
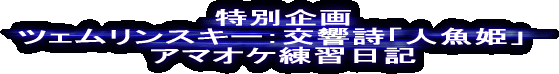
2005年7月17日(日)午後2時開演
市川市文化会館大ホール
グリンカ: 歌劇「ルスランとリュドミラ」序曲(1st)
ムソルグスキー: 交響詩「禿山の一夜」(2nd)
グラズノフ: アルトサクソフォーン協奏曲(降り番)
ツェムリンスキー: 交響詩「人魚姫」(3rd&Picc)
指揮:田久保裕一
独奏: 彦坂眞一郎
(アルトサクソフォーン)
市川交響楽団
7月17日(日)
いよいよ本番。いつもどおり、9時過ぎに楽屋に入り、音だし。少しだけステージの上でも音を出しました。下の写真は、練習前のステージ風景。
10時に人魚姫より練習を開始しました。前日のGPに続き、なかなか好調です。特に大きな問題はなさそうです。休憩後、ルスランと禿山のリハ。前日は今一まとまりに欠けましたが、ルスランは1日でかなりまとまってきました。禿山も少しずつまとまってきました。この日記にも初めから書いていましたが、今回のプログラムの中では、禿山が一番難しいと個人的には思っていました。ここにきて、やはりそうだな、という気がしました。最後にグラズノフの練習。彦坂氏のアンコールの練習も行われました。
さて、開演。まずびっくりしたのは、お客さまの多さ!今までの演奏会の中で、少なくとも私の記憶の中では一番多かったような気がいたします。第九以外でこれほど入るとは・・。これも地元出身のソリスト、そして指揮だけでなく宣伝にも熱心な指揮者あってのことでしょう。やはりお客さまが多いのは、うれしいことです。
1曲目のルスラン。なかなか落ち着いた、かつ熱のこもった演奏でした。順調な滑り出し。そして個人的に気にしていた禿山。今までの中では、一番まとまっていたでしょう。でも、もっともっとできるはずです。特にセクション内でのアンサンブルに関しては、改善の余地が多々ありますね。曲が曲だけに、効果音的な場面が多いのはそうなのですが、きっちりアンサンブルをしなければならないところもあります。
禿山が終わってすぐに楽器をかたし、急いで客席に向かいました。もちろん、グラズノフの彦坂氏の演奏を聴くためです。甘い甘い、彦坂氏の音色。フォルテでもピアノでも、ホール中を満たす素晴らしい音、演奏でした。伴奏の弦楽器も、難しい曲だなと感じさせる場面はありましたが、よくサポートをしていたと思います。彦坂氏のアンコール、これまた良かった!即興演奏でしたが、このアンコールだけでも、お客さまをひきつけてしまう、そんな魅力をもった演奏でした。
休憩後、いよいよメインの人魚姫です。個人的には、ピッコロのフォルテで演奏する場所を間違えたりと、最初は落ち着きがありませんでした。しかし、オケ全体としては、出だしからいい雰囲気で曲がスタートしました。混沌とした中にも、とても美しいメロディが聞こえるツェムリンスキーの音楽。他の曲よりも練習時間が多かっただけあて、完成度の高さとしては、4曲中ベストだと思います。指揮者自らの選曲ということもあり、田久保先生の指揮も、いつも以上に熱かったですね。rit.での粘り方は、あ、田久保先生だ!、と感じました。
こういう比較的無名の曲の時、結構寝ているお客さまが多いのですが、この曲はそうではありませんでした。皆さん、起きてきちんと演奏を聴いていました。これには驚きです。きっと、初めてでも分かりやすく、何かインパクトのある曲だったのでしょう。そういう私も、2001年に上岡指揮N響の演奏(ダイジェスト)を聴いて、全曲聴きたいと思い、CDを買いにいきましたので・・。
打ち上げも彦坂・田久保両氏に参加していただき、大変盛り上がりました。帰りも途中まで田久保先生とご一緒させていただき、大変楽しくお話しをさせていただきました。以上!
7月16日(土)
前日のGP。設営に時間がかかり、15分遅れで合奏がスタート。当日と同じ曲順で練習です。
ルスランと禿山、合奏開始ということもあり、今ひとつ一体感が欠けていたように感じられました。これもステージでの音の感覚に慣れれば、問題ないでしょう。明日のリハ、本番と順を追って良くなっていくと思います。彦坂氏のグラズノフも、同様です。当日、お互いの音を聞きあう余裕ができれば、解決できるレベルだと思います。
一方の人魚姫。今GPの録音を聴きながら、この文章をうっていますが、なかなかの仕上がりだと思います。こういうことを申し上げるのは少し気が引けるのですが、よっぽどのトラブルがない限り、かなり期待できる演奏になるのでは。非常に緊張感の高い練習、演奏だったと思います。
7月9日(土)
本番1週間前です。今日は、ハープが2台入りました(デジカメを持参するのを忘れました!)。いつもは、前日のGPから入るのが普通なのですが、今回はレアな曲なので、ということでしょうか。でも腕前はさすがです。1回で決まります。
さて、練習内容は、ルスラン+禿山+人魚姫の3本立て。かなりハードな練習です。ルスランと禿山は、さらっと終わってしまいました。今日は、MDで練習を録音していたのですが、個人的に改善すべき点が分かりましたので、来週のGPまでには少しマシになるかと思います。
練習の大半は、人魚姫に費やされました。ハープが入ると、この曲はガラッと雰囲気が変わります。特に、弦楽器の奏者にとっては、今まで引きにくかったところが、ハープが入ることで引きやすくなったとこが、多々あるのではないでしょうか。演奏していて、そんなことを感じました。テンポが不安定だったところが、ハープのリードでテンポが安定する、etc...。この2台のハープ、注目です。
・ホームへ戻る
7月3日(日)
午前10時から午後4時までの、マエストロによる特別練習。が、私は諸事情により、前半の練習に参加することができませんでした。前半は、私が1stを吹くルスランと2ndを吹く禿山。いずれも代奏をしてもらいました。相変わらず、合奏へ参加率が改善されません。あーあッ、まったく・・。
後半は、グラズノフから練習が始まりました。もちろん、ソリストの彦坂氏を迎えての練習です。
聴いていて、そして見ていて楽しめる演奏です。スリリングです。これは、私も当日は客席で聴こうと思います。禿山の演奏が終わったら、急いで楽器をかたして、客席へダッシュ!
本日最後の練習は、メインの人魚姫です。第1楽章から第3楽章まで、初めて通してみました。通すと、色々事故が起こりますね。仕上がり具合も、楽章別にはっきり分かれています。やはり、練習量の多かった第1楽章は、比較的良くまとまっています。今現在の問題は、第3楽章でしょう。演奏をしていても、緊張感が途切れる箇所があります。
問題点はありますが、全体的にはどんどん上向いていることは事実です。本番まであと2週間。いい演奏会になるよう、頑張りたいと思います。
7月2日(土)
S氏による管楽器分奏。私は練習に遅れて参加をしました。
まずはルスラン。わずか5分の曲ですが、1時間を費やしました。でも飽きずに練習できたのは、的確な指導があったからだと思います。場面場面による音楽の感じ方のアドバイスが、とても良かったです。フレーズの持っていき方、タンギングの使い分け方、等々。いい方向に変わりました。
次は禿山。これもとても丁寧な指導でした。できないところはテンポを緩め、ひとつひとつ音楽が出来上がっていく感触がありました。次回以降のマエストロ練習にきっと有益になる、そんな感じの分奏でした。
・ホームへ戻る
6月25日(土)
オケ練習の前に、大村先生のフルートのレッスンを受けました。今日は、AndersenのNO.8。このエチュードを練習された方は分かると思うのですが、見た感じ、とても難しそう・・。1曲ずっとトリルの練習になっています。私もとにかく音符を追うことに必死で、音楽の流れなどほとんど感じないままレッスンを受けてしまいました。そこは先生も分かっていたようで(!?)、一つ一つアドバイスをしてくれました。音符の感じ方、大きな流れでの中の音の強弱、等。あれよあれよという間に、素晴らしい曲になってしまいました。当然、来月もう一度さらい直し。そのほうが良かったです。訳がわからないまま先に進んでも、何の意味もないですからね。
さて、オケ練習。前半は人魚姫の全楽章を練習しました。なかなかいい感じで進んでいきました。細かいところはまだまだですが、曲全体は、だんだん一つの方向性を向いてきているような気がします。ただ、テンポの緩急については、指揮者の意図を汲み取れ切れていないなあ、と思います。今回に限らず、概ねオーケストラはあまりテンポの変化を求めず、一定のテンポで演奏したがる傾向があるように感じられます。でも、今回の指揮者の緩急を使ったテンポの方が、遥かに素晴らしい曲になると思います。当日演奏を聴いていただけるお客様はもちろん、最終的には演奏している我々もそう感じるはずです。漫然と演奏するのではなく、常にアンテナをはって、機動力のある演奏をしたいものです。
後半は降り番のグラズノスですが、ソリスト彦坂氏の初練習ということで、しばらく聞いていました。この地域近隣での吹奏楽経験者であれば、彦坂氏のことは多くの方がご存知だと思います。私も高校時代に吹奏楽部で、トレーナーとして来ていただいたことがあります。相変わらず、素晴らしい演奏、素晴らしいトークです。曲は、演奏によって面白くもなり、そうでもなくなる。彦坂氏の演奏を聞いて、そんなことを実感しました。
・ホームへ戻る
6月18日(土)
管楽器のみによる、人魚姫の分奏。指揮は、マーラー3番の時以来のS氏。リズム、ハーモニー等、分奏ならではの練習を行いました。なかなかいい練習でした。特にハーモニー合わせは、的確なアドバイスだったと思います。きっと指導者自身が、確かな音感を持っているからでしょう。再来週にもう一度分奏がありますが、このときは、ルスランと禿山の2曲が行われる予定です。個人的には、この2曲のほうが問題点が多いような気がします。
さて、今回の演奏会で使用する楽器についてです。このHPの表紙にも掲載しております新しい楽器ですが、今回の演奏会では使用せず、今まで17年以上お世話になったミヤザワフルート(その前に使用していた洋銀の楽器を合わせると23年!)で出演するつもりです。昨年、メンテナンスを出さなかったことが原因で、楽器の音が出なくなりました。今はオーバーホールをして健康な状態に戻りましたので、最後くらいはいい状態で音を出してあげたい。そういう感謝の気持ちを持って、今までの楽器のラストコンサートにしたい、と思っています。
6月11日(土)
いよいよ今日から、エンジンがかかってきました。

グラズノフの練習(代ソロつき)
前半はグラズノフ、代ソロを加えての練習でした。管楽器は降り番。
後半は、人魚姫。今までの練習とは、明らかに内容の濃さが違いました。前回までは、どんな曲なのか、とにかく楽譜を音にしてみる、という作業が多かったように思います。今日は、音量、バランス、テンポの変化等々、さらに曲の雰囲気がでる練習をしました。いい練習でした。本番約1ヶ月前になり、いよいよ、という感じです。
一番の心配事だった、出だしのフルートとピッコロのアンサンブル。今日はうまくいきました。いい調子になってきました。このまま本番へ向けて行きたいと思います。
6月4日(土)
なかなか楽しい、そして充実した練習でした。マエストロもオケも、お互いに慣れてきたのでしょう。
1曲目は、グラズノフですのでお休み。2曲目は、ルスラン。マエストロのことですから、きっとムラヴィンスキーのテンポなのかなあ、と思いきや、意外や意外、楽譜どおりのテンポ! CDを聞きなれていると、少し遅く感じるほどのテンポです。しかも、本番もこのテンポでやる(本当かな?)との事。この曲は、ムラヴィンスキー・テンポなら、ダブルタンギングを使う必要があるのですが、今日のテンポなら、なんとかシングルタンギングでいけます。ほっとしました。
3曲目は、禿山。この曲、難しいですね。音の強弱、テンポを守る、音程、等々。基本的なことをきちんとやらないと、形になりません。改めて、そういった音楽の基本の大切さを痛感いたします。いい教材です。
さて、明日は5日の日曜日。何かいいことがありそうです。それは、また後で・・・。
5月28日(土)
1月下旬以来、4ヶ月ぶりに大村先生のフルートのレッスンを受けました。本当は月に1ヶ月のペースで受けたいと思っているのですが、なかなかうまくいきません。いつものように、Andersen
Op.21を練習をしました。今日は、6番(下の写真)と7番です。
2曲とも、指の練習が必要な曲で、かつブレスの位置が曲の雰囲気を、ガラッと変えてしまう曲です。今回は、そのブレスの位置と、吹きながら歌うことの2つを、指摘されました。その指摘によって、ものも見事に曲が良くなりました。こういうときが、レッスンを受けて良かったな、と感じる瞬間です。余談ですが、最近の東京音楽大学の入試に、また一昔前の東京藝術大学(師匠が受験したこと)でも、このエチュードが使われているそうです。師匠曰く、受験前の半年間は、このOp.21だけを練習していたとの事。
さて、ようやくオケの練習の話しです。弦+木管+ホルンによる分奏。前半はグラズノフのため、お休み。後半は、人魚姫を練習をしました。出だしのPicc+Flのメロディ、相変わらずピッチが合いません。そこばかりが気になって仕方ありません。日によって、お互いのピッチの取り方が変わり(探り合っている?)、妥協点が見つけられないでいます。困った困った。
5月21日(土)
今日は弦楽器のみの練習、管楽器はお休みです。私にとっては、2週間連続でお休みになってしまいました。楽器が吹きたくても吹けない。フラストレーションが溜まります。
5月7日(土)
マエストロ練習、のはずですが、結局練習に行くことができませんでした。もうあかん、こんなこと。絶対にあかん、あかん( ←京都より西に行ったことのない人間が使う言葉ではない)。6時に練習が始まるというのに、7時過ぎまでここで拘束されていたら、それはもう無理だって。どうにもならない。ジェット戦闘機かヘリコプターを使わないと、練習終了前にすら間に合わない。戦闘機とヘリのいいところをとった、イギリスのハリアー戦闘機がいいかもしれない。これなら、垂直離着陸が可能な上、飛行スピードも抜群。1年に1回くらい使いたい・・。
下の写真が、本日の拘束場所です。
しかも、同じ施設の中では、こんなこともしています。オレが行きたいのは、こっちだ! もう、嫌がらせだよ。
ここの施設では、指揮者の大友直人氏とアランギルバード氏の二人が音楽監督になって、音楽家の卵を教育するオーケストラをつくっているんですよ。今日は、そのジュニアオーケストラのパート練習だったようです。
1年前の「ラヴァルス&幻想」の練習日記でも、今日と同じようなことを書いていました。きっと、来年も書くんだろうな。
5月7日(土)
本日・来週と、マエストロ練習が続きます。前半は、グラズノフのコンチェルト。ソリストの彦坂氏ではなく、代吹きソロで練習をしました。管楽器は出番がないので、日記は割愛いたします。
さて、後半は人魚姫。特に、第1楽章を集中的に練習をしました。先週も指摘しましたが、ピッコロが最初に出てくるフルートのピッチ合わせ、ヤバイですね。同じような形が繰り返し出てくるので、2回目以降は合わせられる事があるのですが、ここの場合は、初めからきちっとしていなければなりません。今困っているのは、ピッチを高く取ったほうが良いのか低くとったほうが良いのか、日よって変わってしまうということです。もう少し時間をかけて、どのように演奏するのがより良いのか、考えていきたいと思います。
その他の第1楽章は、ピッコロが目立つこともありますが、それほど難易度は高くありません。3番フルートとしてフルート内でハーモニーを作ることがたびたびあります。この場面では、とにかく1番フルートを支えることを考えなければなりません。1番フルートを聴けば、自分がどのような音量、タイミングで演奏すればよいのか、自ずと分かるはずです。今はまだ、模索中です。
4月30日(土)
木管分奏の日です。人魚姫をたっぷり練習しました。主にハーモニー合わせです。指揮者なしでやったため、何回か「行方不明」になるところがありましたが、それほど支障はありませんでした。
第1楽章では、まず最初に出てくる、ピッコロとフルートのピッチ合わせがポイント。これまで練習をしてきて、どうも私は音程を相対的に低くとってしまう癖があるようです。私の場合は、ここは高めにとればOK。第2楽章は、指回しをしっかりとすることでしょう。第3楽章は、高音域のロングトーンがあるので、かなりピッチが気になります。クラリネットをよく聞いて、入ること。以上。
4月23日(土)
今日の練習は、禿山+ルスラン+人魚姫の3本立て。かなりハードなメニューです。指揮は、練習指揮者の金丸氏(←かってにリンクを貼ってしまいました・・)。
まずは禿山。これ、結構難しい曲です。テンポ、リズムといった、音楽の基本的なことがしっかりしていないと、曲が今一しっくりとしません。今日もそうでした。弦の刻みを聞きながら、カウントをとりながら管ののばしの音を出さないと、ずれてしまいます。アンサンブルが成り立ちません。もちろん、それだけに囚われずに、音楽の流れは大切にしなければなりません。なかなか手ごわい曲です。
ルスランは初めての練習です。ムラヴィンスキー指揮+レニングラードのCDで、散々聴いていた曲ですが、楽譜を見ると意外にもテンポ指示は速くありません。ニ分音符=135。超快速のムラヴィンスキーは、完全にこの指示を無視しています。今回の演奏会では、ムラヴィンスキー・テンポにならないことを、祈ります。あのテンポは、聴いているだけで十分です。最後に人魚姫の第2、第3楽章を練習しました。時間がなく、ざっと通しただけです。
いつもならこれで終わりなのですが、珍しく居酒屋へ寄りました。時間の経つのを忘れるくらい、飲んで楽しみました。ぎりぎり終電に間に合わず、タクシーで帰宅。よほど楽しかったのでしょう。いつも以上にビールの摂取量が多く、タクシーの中で酔ってしまいました。もう少しで***でしたが、そこはオトナの理性(そういう問題か!?)でなんとか食い止めました。
ということで、また来週。
4月16日(土)
今日は、弦楽器練習のため、管楽器はお休みです。これだけでは、せっかくこのホームページを見ていただいた方に申し訳ないので、フルートのカタログをデジカメで撮影しました。ご覧になってください。
特に今日の練習内容とは関係なのですが、まあ、なんとなく載せたくなりました。私個人が趣味で作っているページなので、時々ご理解いただけない行為があるかもしれませんが、今後もよろしくお願いいたします。
4月9日(土)
マエストロ練習の2回目。私にとっては、初のマエストロ練習になりますが・・・。合奏前に、楽器の配置換えがあり、多少時間をおして練習が始まりました。
前半は、人魚姫。第1楽章は、パート別・セクション別に取り出して、かなり細かく練習をいたしました。どちらかというと、静かな場面でのやり直しが多かったように思えます。中間部の盛り上がる部分は、ざっと通して終了。第2、第3楽章も同様に進みました。管楽器は、今日はあまり指摘されることがありませんでした。
後半は、禿山の譜読み。なかなか難しいですね。フルートにとっては、人魚姫よりさらう必要があるかもしれません。
4月2日(土)
指揮者なしの、管楽器の分奏の日です。結局、パート練習になりました。人魚姫の第1楽章から順番に、ハーモニー、ピッチ、リズムを気にしながら確認。途中から、オーボエも一緒に合わせました。
パート練習だと、書くネタもこの程度になってしまいます。来週は2回目のマエストロ練習ですので、きちんと書けると思います。
3月26日(土)
今日は初のマエストロ練習、だったはずです。きっと、有意義な合奏になっていると思います・・・。
実は、練習に行くことが出来ませんでした。練習、というより外へ一歩も出ることが出来なかったのです。理由ははっきりとは申し上げませんが、写真を添付しますので想像をしてください。
これは、山歩き用のステッキですが、これを使わないと歩行が困難な状況です。今日はこのくらいでご勘弁を・・・。
もう1枚、これは「人魚姫」のパート譜です
3月19日(土)
前回分奏を行った後の合奏、なかなか充実した内容だったと思います。人魚姫の全楽章、どの楽章も細かく練習をしました。基本的には、出る場所できっちり入り、他のパートとの連係をスムーズにいくこと、が目的だったように感じられました。出来ない箇所はテンポを落としてゆっくりからさらい、ある程度できるようになってから通常のテンポに戻す。当たり前のことですが、これは個人練習でも合奏でも、大変有効な手段であることを再認識しました。
全体の流れは大分分かってきました。個人的に練習をしなければならない箇所も分かりました。来週は、初のマエストロ練習です。
3月12日(土)
今日も遅れて参加をしました。来週は、なんとか時間どうりに行けそうです・・・。今日は人魚姫の管楽器の分奏でしたが、指揮者なしでメンバーが円になって自主的にやるなんて、少なくても私が入団をしてからは初めてです。さすがに途中で苦しくなり、即席にカウントを出してもらう指揮者を立ててもらいました。
苦戦をしながらも、自分の音、周りの音を一つ一つ確認をしながら進むことができたのは、良かったと思います。あまり演奏されない曲ですが、慣れればそれほど難易度の高い曲ではない、と現段階では思います。
3月5日(土)
人魚姫の練習初日です。2002年の1月にこの曲のCDを購入していて、どんな曲かはおおよそつかんではいました(詳しくはこちらをクリックして、下の方にあるNo.56 2002/1/24 をご覧下さい)。が、まさか、この曲をアマオケで演奏する機会があるとは、思ってもみませんでした。
いつもどおり(!?)、遅刻をして練習に参加をしました。練習初日ですので、内容は当然譜読みです。前半は、まとまりにくいところを少しずつ止めながら、進めていきました。曲の印象は、全体的に混沌とした中に、ときどき美しいメロディが流れてくる感じです。第1楽章、結構ピッコロが目立ちます。第2楽章、少し指の練習が必要です。第3楽章、フルートの出番しかなく、ピッコロへの持ち替えがありません。
休憩後は、第1楽章から第3楽章まで、通して演奏をしてみました。ミスはあったものの、止まらずに最後まで無事到着! 初日の練習、順調な滑り出しです。
これまでの特別企画
・⑭Ph.ハンミッヒ木管フルート ノマタチューンナップ記
(2005年2月)
・⑬ベートーヴェン交響曲第9番「合唱」 アマオケ練習日記
(2005年2月)
・⑫新世界より&キャンディード アマオケ練習日記
(2004年12月)
・⑪ロイヤルコンセルトヘボウ管弦楽団2004年日本公演レポート
(2004年11月)
・⑩幻想交響曲&ラヴァルス アマオケ練習日記
(2004年7月)
・⑨ハイドン交響曲全104曲 完全制覇日記
(2003年11月より)
・⑧イスラエルフィルハーモー管弦楽団2003年日本公演レポート
(2003年12月)
・⑦シカゴ交響楽団2003年日本公演レポート
(2003年10月)
・⑥マーラー交響曲第5番アマオケ練習日記
(2003年7月)
・⑤ギルバート・キャプラン
(2002年8月)
・④月に1度はコンサートへ行こう企画2001年総括
(2002年3月)
・③ウィーンフィルハーモニー管弦楽団2001年日本公演レポート
(2001年10月)
・②マーラー交響曲第3番アマオケ練習日記
(2001年7月)
・①ベルリンフィルハーモニー管弦楽団2000年日本公演レポート
(2000年11月)