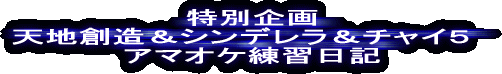
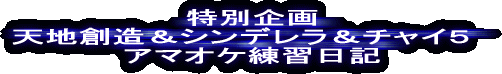
2007年10月21日(日)午後2時開演
市川市文化会館大ホール
入場無料
ハイドン:オラトリオ「天地創造」(2nd Flute)
指揮:山崎 滋
市川交響楽団
(終了しました)
2007年12月2日(日)午後2時開演
市川市文化会館大ホール
入場無料
プロコフィエフ: バレエ組曲「シンデレラ」より
(Piccolo)
チャイコフスキー: 交響曲第5番 (1st Flute)
指揮:山崎 滋
市川交響楽団
(終了しました)
2007年12月2日(日) 最終回
演奏会当日です。午前9時少し前に楽屋入り。音だしをして、9時30分より木管メンバーでチャイ5の集中練習。第1楽章の練習番号QからRです。
ここは、ファゴット → クラリネット → フルートの順番にソロの受け渡しがあるのですが、いまひとつすっきりしない。チームプレーが出来ていなかったのが原因ですね。このままでは、あまりの雰囲気のなさに、演奏している方も聴いている方も、「寒さ」を感じてしまいます。ロシアの寒さを通り越して、マイナス50度のシベリアの大寒波、という感じです。まずは、その寒さをモスクワのマイナス20度位に引き上げたい。そうすれば、相対的に音楽が暖かく感じられるでしょう。そこだけを何度も繰り返して演奏することで、雰囲気をつかむ。少しは、良くなったかな・・・。
シンデレラで12時の時の音を告げるチャイムと同じく活躍する銅鑼
午前10時より、チャイ5のリハーサル。昨日よりもホールの響きに慣れ、落ち着いて吹くことができましたね。今回のチャイ5、練習期間が短かったせいか、どこを見て聴いて、どこを基準・拠り所として演奏をしていいのか分からず、迷いに迷っていました。で、もう何も考えず、ただひたすら演奏することに徹しました。今回に限っては、それがプラスにはたらき、落ち着くことが出来たのだと思います。
続いてシンデレラ。今まではあまり問題にならなかった、ピッコロの音程が気になり始めました。音程に神経を使う箇所は2箇所。大きなソロのある第1組曲第4曲目のFis音と、終曲の3つのC音。普通に吹くとFisは異常に高く、Cは少し低め。バランスを考えながらチューニングをしてきたつもりですが、Fisがどうしてもフルートと合わない。結局、フルートにそこだけ高めにとってもらい、さらに私が全体的に低めにチューニングし、ソロが終わってから頭部管を入れて元に戻すことにしました。ぶっつけ本番で行う作業なので不安でしたが、今回はその方法をとってみることにしました。
午後2時、予定通り開演。シンデレラ、客席が永井さんの素晴らしい語りに引き込まれていくのが分かりました。ネズミを語り手とする、とてもユニークな台本。私も演奏の合間に、客席にいるような気分で聴いていました。ピッコロがお休みの序曲と終曲がとても美しい音楽なのですが、いつも以上に弦楽器の表現が豊かで気持ちの入ったいい演奏だったと思います。
2曲目からピッコロの出番があるのですが、やはり低めにチューニングしていたせいで、いつもと感覚が違い、戸惑いながら演奏していました。しかし、第4曲目ではそのピッコロとフルートのFisは、なんとか許容範囲内に収まり、直後のソロは落ち着いて吹くことができたと思います。その後、頭部管を入れ直していつもと同じピッチにしたつもりでしたが、最後のC音、いつもより低い音が響いてしまいました。慌てて2つめから思いっきり高めにとり、何とか修正・・・。十分に管を差し込んでなかったのでしょう。いやいや、練習でやってないことを本番で行うのは、とても危険です。良い子はまねをしないように・・・。
ピッコロで非汗をかいた後は、チャイ5の1stフルートです。冒頭の運命の動機、クランポン社製のA管クラリネット2本が、とても落ち着いた響き。いい音だ・・・。その前に座っている私は、特等席で聴くことができました。
第1楽章、これまでの練習よりは良くなってきたと思いますが、もう少しオケ全体が一つの塊になればなあ、と演奏しながら感じていました。というのも、私自身が落ち着いていなかったものですから・・・。木管セクションで直前特訓したところも、シベリアの大寒波、は何とか避けられたと思います。第2楽章、一番感情の起伏の激しい楽章です。この曲の後半から、少し手ごたえを感じ始めましたね。ああ、今日は尻上がりに良くなって行くかもしれない、そんな感覚がありました。最初は緊張していたものの、この頃から私も落ち着き始め、周りの音が良く聞えるようになりました。本番のステージでこの感覚をもてるのは、本当に久しぶりです。
この落ち着きがあれば、もう怖いものなしです。第3楽章からは、私は練習のときよりもさらにリラックスしていて、かなり強気で演奏していたように思います。あ、中間部の掛け合いでは、思いっきり音を間違えてしまいましたが・・・。そして第4楽章。全楽章中、最も熱く、そして最も集中していたように感じました。出だしの弦楽器もとても厚みがあり、ブラボ。テンポの切り替えでも、オケ全体が慌てることなく、きっちりと反応していましたね。ブラス隊も絶好調。いやいや、練習量が少なく心配しましたが、最後は集中力でオケが一体になり熱演になったこと、とてもうれしく思います。
これで今年の演奏会は全て終了いたしました。振り返ってみると、今年はとても大変な年でしたね。音楽の楽しさよりも、難しさやしんどさを味わった年だったと思います。7月のエロイカと10月の天地創造で、立て続けに失態を重ねてしまい、気分的にかなりまいってしまいました。深い森の中に迷い込んで、前へ進めど進めど出口は見えず、そして元に戻るにもその道も分からなくなっている。出口かな、と思って別の道を行ってみると、そこはさらに深い森に続く道であったり・・・。何をやってもうまくいかなかったですね。そういった中ではありますが、チャイ5の演奏中に、エロイカとハイドンの時には失っていた、「落ち着いて周りの音が良く聞えてくる」感覚、が戻りつつあったので、これから好転するきっかけになってくれれば、と思っています。(完)
2007年12月1日(土)
前日のGP。個人的課題として、以下の点を確認しながら、合奏に参加をしました。
【両曲共通】
・音にスピード感をつける
・音楽をもっと前に!
【シンデレラ】
①第1組曲4曲目、練習番号52からのソロ、スケールの指使いの確認
②第1組曲8曲目、第3オクターブのA音の発音と響き、スラーからタンギングに変更したほうが良いか
③第3組曲8曲目、C音の響きと発音、表情の確認
【チャイ5】
(第1楽章)
①練習番号B前の6/8拍子のソロ、付点のリズムとタイでつながっている音に注意
②練習番号F5小節目、Fisの入りのタイミングと響き
③練習番号H前後、あまりロマンティックにならないように
*この3つは後半にも調性が変わっただけの同じパターンあり
(第2楽章)
④練習番号Bから、スピード感をもつ
(第3楽章)
⑤練習番号F4小節前からHまで、慌てずユニークさをもって
(第4楽章)
⑥練習番号Hから、自然なテンポで
⑦練習番号Vの12小節前から、自然なテンポで
まずは、ナレーションを入れてのシンデレラ。①の指使い。結局、慣れているブリチアルディキーを使うことにしました。シャープが5つもある曲で、この指使いする人は、私以外にいるでしょうか。でも、結果がそちらのほうがいいので、そうします。今日一番の収穫でした。②は、A音の響き自体がいまひとつですね。タンギングをしたほうが縦線は合わせやすいので、そうしようかな。③は明日のステリハで、もう一度より良いものになるよう、確認します。
続いてチャイ5。①はここに書いた中でも、一番重症かなと思っています。あー、スッキリしない。明日は、関係者数名で早朝練習・・・。②はかなり修正できました。もう一息です。③は、今日はドライに吹きすぎました。もう少し、ちょうどいい場所があるはず。④はまあまあかな。⑤はユニークどころか、「崩壊警報」がだされてしまいました。⑥と⑦は、前回よりは多少進歩があったかな。
まあ、こんな感じです。
2007年11月24日(土)
本番1週間前。前半はチャイ5を全楽章練習しました。%$#!??*%!?、こんな感じでしょうか。えー、まだ1週間も練習できます。
後半はシンデレラ。これは面白い演奏会になりそうですね!!今回の演奏会では、ナレーション付きのシンデレラになりますが、その語りを担当される永井誠さんがいらっしゃいました。台本もなかなかユニークで、それをまた絶妙な語り口で物語を盛り上げていきます。聴いていて、思わず引き込まれそうになります。これなら音楽無しでも・・・、いやいやオーケストラの音楽がより楽しく聴けそうですね!
シンデレラのピッコロで一番大きなソロは、上の写真、No.4「仙女のおばあさんと冬の妖精」です。真中の七連符のスケールをもっときれいに吹きたくて、今までとは少し指使いを換えてみました。具体的には、Aisの音を今までは左親指でブリチアルディキーを素早く操作していましたが、一般的な右手人差し指を押さえるやり方に変更しました。シャープ系の曲では、本来はこれが正しい(?)指使いだとは思うのですが、学生時代にB-durやEs-durの曲ばかり吹いていた癖で、いまだにブリチアルディキーを多用しています。
七連符のスケールを吹いた後、指使いはどっちがいいのかなあ、なんて考えながらその後のFisを吹き続けていたら、迷子になってしまいました。本番では、余計なことを考えずに吹こうと思います。
・トップへ戻る
2007年11月17日(土)
前半はシンデレラ。この曲ではかなり目立つピッコロのソロもあり、初めはそういうところを気にしていたのですが、最近楽しみにしているのはそれとは別の場所です。
上の写真はシンデレラの終曲、第3組曲の8曲目、Amoroso「愛をこめて」です。「シンデレラは王子様と結婚して、幸せに暮らしました。」(ペローの童話)のシーンです。プロコフィエフらしい、とてもとても美しいメロディです。しかしピッコロは、この美しい音楽が奏でられている間、初めから32小節間ずっとお休み。そのメロディーが終わった後、弦楽器が最弱音でハーモニーを作っている時に、初めて出番があります。C音を3回。とても緊張を強いられる箇所ですが、この音をどんなイメージをもって演奏するかが、目下の関心事。「王子様との結婚はウソでした」、という演奏にはしたくないと思います。たった1つの音ですが、とても面白さを感じるところでもあります。
余談ですが、もしプロコフィエフがペローではなく、ハトが目をつついてしまうグリム童話を元に作曲をしたら、こういう作品にはならなかったはず。スキタイ組曲「アラとロリー」の第2曲目のような雰囲気の曲を作っていたかもしれません。
後半は、チャイ5。セクションごとの練習をしてから全奏を行うなど、細かいところまで確認できる合奏でした。私は、これは本当にありがたかった。第1楽章の大きな問題点は、①練習番号B前とR前の2つのソロ、②練習番号F後のFisの発音とT後のGisの発音、の計4箇所です。①は曲のイメージをもっとしっかりと持たなければなりません。毎回師匠からも、「どうしたらその曲の魅力が引き出されるかよく考えてから演奏しなさい」といわれてしまいますが、ここでもその弱点を露呈してしまいました。
練習は後2回。ちょっと、今のままではまずいなあ・・・。
2007年11月10日(土)
チャイコの第2、第3、第4楽章から。第2楽章で先週崩壊した場面、今日は安全運転で演奏してみました。結果は、先週よりはまとまった気がいたします。でも、本当は突進したい。もっといい方法はないかな・・・。第3楽章、やはり中間部ですね。ずっと3拍子なのですが、音楽のつくりが2拍子単位なので、混乱しやすい。しかも、フルートはダブルタンギングで吹きクラリネットはシングルタンギングで吹くため、それをそろえるのも一苦労。というか、今は自分のことで精一杯で、そろえるところまでいっていないのが実情。第4楽章は、ラストでかなり疲れて演奏に支障がでるので、472小節目から503小節目くらいまでは、少し力を抜いて演奏してみました。そうすると、何とか最後まで持つことが分かりました。
休憩後のプロコフィエフ、ここでも先週感覚がつかめなかった第3オクターヴのA音の確認。この音が多発するのは、8曲目の真夜中。シンデレラの魔法が解ける12時が刻々と迫ってくるシーンで使われています。楽譜ではスラーでの演奏ですが、今日はどうしたらこの音がきちんと響くかを確認したかったので、スラーを外しタンギングをして発音してみました。なるほど、こんな感じか・・・。大体雰囲気はつかめました。これ、本番でもスラーを外したほうが良いのかもしれないな。
ヨハネス・ゲルハルト・ハンミッヒ、使い始めてまだ4回目の合奏ですが、早くもこの楽器で演奏することにうれしさを感じています。こちらが息を吹き込むと、それに素直に反応してくれます。さらに今度はちょっと違う吹き込み方をすると、またそれに応じた反応が。いやいや、うれしくてうれいしくて合奏中ではありますが、頭の中はピッコロのことで一杯でした。相思相愛・・・・。この言葉が一番ふさわしいと思います。
一方のフルート、とても美しい音色をもった楽器のはずなのですが、なかなかその魅力を引き出せずにいます。約2年半経とうとする今でも、吹き始め当初に書いた、「何といっても音が素晴らしい。かなり馬力のある楽器で、コントロールをするにはちょっと訓練が必要かな、と感じています。」が、そのまま当てはまります。優秀な演奏者(素人さん)によってこのフルートの魅力が引き出された状態を知っていますし、自分自身も他のメーカの楽器にはない独特の音を持っていることを体感しているので、この楽器を選択。おそらく、ブランネンに匹敵するだけの能力をもった楽器だと思います。何とかそれを自分のものにしようと、色々試みているのですが、今のところ楽器から拒否され続けているなあ、と。7月のエロイカや10月の天地創造での失態、そして相思相愛のJGハンミッヒとの比較、などを考えてしまうと、余計に強くそれを感じてしまう今日この頃です。
2007年11月3日(土)
ようやく12月の演奏会の練習に専念できます。気がついたらもう1ヶ月をきっていますね。さあ、残り少ない練習期間でベストパフォーマンスを発揮するために、ガツガツやっていかないと。そして、演奏会当日のステージであがらないようにするための対策も考えなければなりません。
前半はチャイ5の第1楽章と第2楽章。今日は残念ながら、吹いていて不満の残る内容でした。笛の出だしからテンポを共有できず、寂しいかぎり。第1楽章は得るもの無し。第2楽章。こちらもやはり落ち着きのない演奏でしたが、積極的に仕掛けていって崩壊したので、まだ得るものはありました。
左の写真は第2楽章、その崩壊した場面です。120小節目から1stヴァイオリンとファゴットの旋律に、木管楽器がまとわりつくように対旋律を吹きますが、ここは4小節でひとかたまり。2小節の後「animando」があって「sostenuto」のパターンです。最初の2小節は何も指示がありませんが、笛吹きとしては突進したいところ。でも、そうすると主役のヴァイオリンとは対話ができません。当然ですよね、animanndoとは書いていないのですから。ここはぐっと気持ちを抑えて吹くようにしないといきませんね。でも、テンポは巻かないまでも、気持ちはそのくらいあるよ、という演奏はしてみたいところです。
休憩後はシンデレラ。前回練習したときは手の施しようがないほどばらばらだったのですが、今日は合奏をやるだけの価値はあるレベルまでになっていました。それでも、難しさを感じる曲であることには変わりありませんが。No.1の「序奏」はプロコらしい大変ロマンティックで美しい曲。全曲がこんな感じならさほど難しさを感じないのですが、続くNo.2の「シュールのステップ」では半音外してもそのまま進んでいってしまうような危険性のある曲です。こういう曲が怖い。
ピッコロは少しずつではありますが、楽器と仲良くなりつつあります。中音域の音程の癖が前の楽器と大きく違うのですが、合奏を繰り返しているうちになんとなく感触はつかめてきたような気がします。写真右上のNo.4「仙女のおばあさんと冬の妖精」はその中音域が多用される曲です。でも、高音域がいまひとつ感触がつかめずにいますね。特に第3オクターヴのA音。この音も前の楽器と感触が大きく異なり、どのくらいの息の圧力をかければいいのかが今日も分かりませんでした。今の吹き方だと音がまとまらず、きちんと楽器が響いていない状態です。
2007年10月27日(土)
通常のオケ練習の予定でしたが、急遽管楽器はお休みになりました。また来週。
2007年10月21日(日)
天地創造の演奏会当日。ここ数日続けているフルート3本の特訓のため、オケ練習開始時間より早くホールに到着しました。その特訓をした27曲目の楽譜を掲載いたします。
左上から1st、右に行って2nd、そして左下が3rdの楽譜です。ハイドンがフルートのために書いてくれた、大変美しい曲です。余談ですが、各パートの担当者をご紹介いたします。1stはパウエル(H足、リップ14金、Cisトリル付、シリアル4000番台)、2ndはマテキ(H足、Eメカ、全身彫刻)、そして3rdもマテキ(H足、Eメカ、リップ・クラウン14金)。似たような仕様の楽器ですが、微妙に違います。結構面白い組み合わせだと思うのですが、いかがでしょうか。ん?、そんなことに興味はない?そうですか、それは残念ですね。面白いと思うけどな。話を元に戻して・・・。前半は合唱団だけ練習でしたので、少し遅めのリハーサル開始。木曜日の練習よりは、幾分まとまってきたような気がします。
今回の演奏会で楽しみにしていたものの一つに、チェンバロがあります。このジャンルには欠かせない楽器ですね。とてもいい雰囲気。このチェンバロ、フルートとの相性も抜群なのです。フルートの伴奏によく使われるのはピアノですが、これはこれで悪くはありません。でも、チェンバロやハープの方が、より相応しいのです。これらの楽器の違いは何でしょうか。ピアノは弦を「叩く」、チェンバロとハープは弦を「弾く」。この違いです。私は一度もチェンバロと一緒に演奏をしたことはないのですが、近い将来、この楽器の伴奏でバッハのロ短調ソナタを吹いてみたいですね。そのチェンバロの写真を撮ろうとして休憩時間中探したのですが、どこにも見当たらない。舞台の下手にも上手にも、姿が見えませんでした。一体どこに隠していたのでしょうか。結局写真は撮れませんでした。
14:00開演。前半は、合唱だけの公演。休憩後、ハイドンの天地創造です。チューニングがうまくいかず、個人的には1曲目から探りながら演奏を始めてしまいました。でも、オーケストラはとても落ち着いていましたね。ゲネプロの時は不調だった5曲目、今日は良かったですね。音符をはしょることなく、一つ一つの音を楽しんでいたように感じました。13曲目、私は出番はありませんが、この曲は大変美しい。ステージ上で聴き惚れてしまいました。27曲目と同じくらい、好きな曲です。
さて、今日一番の大仕事、27曲目のフルート3本です。あがってしまいました・・・。出だしで唇が震えていて、意図しないヴィブラートがかかってしました。いかんいかん。これでは、7月のエロイカの二の舞になってしまう。あれだけは絶対に嫌だ!一瞬だけ顔に、ぐっと力を入れました。すると不思議なことに、唇の震えが止まったではないですか!よし、これでなんとかなりそう・・・。多少緊張は続いていたものの、何とか最後まで吹ききることができました。イメージどおりに本番で演奏することは、本当に難しいですね。主役の合唱は、大変素晴らしかったと思います。ソリストは言うまでもありません。
このところ続けて、ステージで緊張のあまりあがってします。何なんでしょうね。それまでは、ステージにたってひと吹きすると、落ち着いたものでした。一体どうなってしまったのか・・・。12月は以前のように、落ち着いてステージで演奏できるようにしたいと思います。
2007年10月20日(土)
明日は天地創造の本番ですが、今日は12月の演奏会の合奏です。
まずはシンデレラ。いやいやいやいや、ちょっとまずいんじゃない?どうしちゃったのかな。音楽的にどうこうなんて、まだまだですね。とりあえず、書いてある音符を追って音にすることから始めないと。私のピッコロも、他人の楽器を使って吹いているようで、何とも不思議な気分。プロコフィエフ、先が思いやられます。
後半は、チャイコの5番。プロコフィエフに比べると、かなり演奏しやすく感じます。第3楽章と第4楽章のみの練習でしたが、音楽のニュアンスを統一したりと、こちらは練習らしい練習ができたと思います。しかし、この曲、最後まで吹ききるとヘロヘロになります。意識がもうろうとする中、一生懸命指を回していますが、周りの音なんてほとんど耳に入らなくなってしまいます。ペース配分も考えないといけませんね。
さて、これから明日の準備をしないと。
2007年10月18日(木)
平日ゲネプロの変則日程。本番と同じ大ホールでの練習です。1時間40分強、全く休憩無しの練習はきつかた・・・。
第1曲目、実はこの曲、大変吹きにくい。出だしでいきなりのLargo。余程集中しないと、ズレズレ・ダレダレの曲になってしまう危険があるように思います。いまだに、音を出すタイミングを計りかねている箇所あり。あー、怖い怖い。2曲目は、まあまあかな。3曲目は2番フルートは休み。聴いていてとても楽しい曲。4曲目は、特に問題なし。
5曲目は、まずいですね。マエストロから再三再四、一つ一つの音を楽しむように、と指示が出ているのに、どんどん先へ進んでしまっています。単に音符をなぞっているようで、曲の本来の持ち味からかけ離れてしまっているように感じてなりません。もったいないですね。少しだけ「落ち着く・楽しむ」ことを意識するだけで、ガラッと雰囲気が変わると思うのですが。9曲目は、大分まとまってきたと思います。12曲目もOK。13曲目、とても美し曲。これは5曲目と違って、曲本来の良さが出ている演奏だと思います。14曲目もOK。ここで第1部終了。
第2部の23曲目、24曲目、25曲目、そして26曲目は、特に問題はないようと思います。そして第3部。フルート3本が主役の第27曲目。今録音したものを聴き返していますが、今までの中では一番バランスが良いかもしれません。もうひと頑張りです。30曲目のデュエット。出だしの不安定さが気になりますね。基本的な音程やリズムが乱れているのだと思います。だんだん落ち着いてきて良くはなっていくのですが。31曲目、32曲目は特に問題なし。
土曜日は12月の演奏会の練習、そして翌日の日曜日が、天地創造の演奏会当日です。
2007年10月13日(土)
オケ練習の前に、2ヶ月ぶりのレッスンに行ってきました。内容は、以下の通りです。
・T.ベーム:24のカプリスより 第7番
・T.ベーム:24のカプリスより 第8番(写真上)
・E.ノブロー:メロディー
レッスン前、新しいピッコロを師匠に見せて、吹いてもらいました。ロッシーニのセビリア、ラヴェルのダフニス、チャイコフスキーの4番などなど、次から次へとピッコロの曲を披露。オケで使える楽器だね、と一言。ほっとしました。直後のレッスン、こちらはほっとすることができませんでした。エチュード、相変わらず体全体に力が入ってしまい、自滅。事前練習の時に設定したテンポよりも、ずっと速いテンポで吹いてしまい、崩壊。師匠より、テンポを2メモリ落としていいから、とお情けが・・・。
このエチュードに限らず、このところ楽器とうまく付き合えていないような気がします。それを感じたのが、エロイカを練習をしていた今年の4月・5月くらいから。おかしいなと思って色々と細かい調整をやっていたつもりなのですが、自分では楽しみながらその調整をやっていたとはいえ、その期間が長すぎると、さすがに気持ちがまいってしまいます。おそらく、技術的なことというよりも、根本的に何かが欠けているのでしょうね。それに気がついて、少しまともになるのはいつの日か・・・。
ノブローのメロディー、こちらはいつもよりは順調にいったかな、と思います。今までの事前練習では、エチュードと名曲は、おおよそ8対2の割合で練習をしていました。今回からは、5対5にしてみましたので、その影響かもしれません。確かに練習量を増やすと、いつも見えなかったことが見えてきたような気がいたします。
オーケストラ練習は、ソリストを入れての天地創造です。本番1週間前ですからね。カラオケではなく、チェンバロ、合唱、ソリストが入ると、やっぱりいいものですね。大作曲家の作品をこうして演奏できることに、感謝感謝です。個人的には、前回に比べて良くなったところ、さらに修正が必要なところ、そして自分の力量ではどうにもならないもの、いろいろ発見がありました。さて、これから何ができるか・・・。
次回は18日(木)の変則日程での練習。
2007年10月6日(土)
天地創造のマエストロ練習。音楽のニュアンスを整える等、細かな調整が行われました。マエストロの要求にきちっと反応できるところも、反応できないところもありますが、反応できたところは、確実に良くなっています。本番まで残り2週間。一つ一つ丁寧にさらっていきたいところです。
個人的に一番力の入る第27曲のRECITATI。何回かこの曲を練習してきましたが、練習開始当初と比べて、少しずつ考え方が変わってきました。
①1番笛を弱音のまま目立たせるために、2番・3番笛は極力抑える。
↓
②1番笛を目立たせることには変わりないが、部分的には2番以下も目立つように吹く。
↓
③3人ともソリストのように、対等に吹く。
今日は、③のように演奏してみました。周りの反応をみると、今日の吹き方が良いのかな、と思います。耳元で聴く音と客席(正面)から聴く音は、全く同じという訳ではありませんので、このあたりの調整は難しさを感じます。練習期間が長いと、こういうことを試行錯誤しながら何度も試すことが出来るのですが、短いとある程度即決をしなければなりません。
明日は、半年に一回行っているフルートの調整の日です。
2007年9月29日(土)
マエストロ練習です。前半は、12月演奏会のチャイコフスキー5番。初回のマエストロ練習で楽しみなのは、どのように音楽をもっていくか、ということです。事前に予想してみて、それがドンピシャリ当たると、結構うれしいもの。違っていても、そちらの解釈が良ければ思わずうなずいてしまい、今後の練習の楽しみにもなります。今回のチャイ5、予想していたより、かなり落ち着いたテンポでした。初回練習だからでしょうか。おかげで、こちらも落ち着いて吹くことができました。そして、かなりリタルダンドをきかせますね。チャイコを演奏するときは、そのくらいやって客席ではちょうど良く聴こえるのかもしれません。
第1楽章、苦手の低音域が出てきます。もっと、充実した響きがでるように、そして曲で使い物になるように、基礎練習からやり直しです。第2楽章、テンポの変化に注意。第3楽章、とにかく現在位置を見失わないように、しっかりとカウント。第4楽章、ラストまで吹き続けると、かなり疲れます。指がもつれまくっていました。音が半音くらい間違っていても、それを許してしまう精神状態になっていました。あー、いかんいかん。
このチャイ5、私の愛聴盤は、定評のあるムラヴィンスキー指揮のレニングラードフィルです。他にも、カラヤンやストコフスキーも持っていたような気がしますが、現在行方不明・・・。しかし、何といってもこの曲で最も印象が強く残っているのは、小林研一郎氏が指揮する日本フィルの演奏です。もちろんCDではなく、コンサートホールで聴く音楽の話です。演奏会に足を運んで、心から感動をする演奏会に出会えることなんて、滅多にありません。あえて数字にしてみると、10回のうち1回あればいいほうかな、と感じています。では、なぜそんな感動の確率の低い演奏会に足を運ぶのか。例え9回無駄にしても、その1回の感動がとてつもなく大きく、それだけでも十分数多く足を運んだ元が取れるからです。
コバケンのチャイ5、今思い返しただけでも感動がよみがえってきます。その時の演奏を録音・録画し、後で見直しをしたら、もしかしたら演奏中のいろいろな粗が見つかるかもしれません。しかし、ホールで聴くコバケンの音楽は、そのようなものとは無縁。ひたすら感動の頂点へ向かって突っ走ります。演奏中感動のあまり涙を流したことが何回かあります。このコンビによる演奏、10回聴きに行ったら、9回は感動のある演奏会に出会えているような気がしますね。
そんなコバケンのチャイ5、こちらでノーカットで見ることができます。オーケストラは違いますが。こんな演奏をしてみたいものです。
後半は、10月演奏会の天地創造を練習しました。
2007年9月22日(土)
10月の演奏会、天地創造のマエストロ練習です。今日は、初めて合唱との合同練習を行いました。これまでに何回か練習をしてきましたので、曲全体は大まかにつかめるようになったと思います。個人的には、今日は、音程や音符の長さ等、音楽のニュアンスを1番フルートとそろえることを、課題としました。また、合唱団中心の曲とソリスト中心の曲とでは、吹き方を少し変えてみました。
3本フルートの見せ場である、No.27
Recitativ。これまでは、1番フルートを引き立たせることを意識していました。今日の練習を終えて、その方向性は間違ってはいませんが、部分的に2番3番フルートがより目立ったほうがいい箇所を発見しました。次回の練習では、そのあたりを意識して、さらにいいものにしたいと思います。せっかく、ハイドンがフルートのために、こんなに美しい曲を書いてくれたのですから。
後は、合唱との連携と、部分的に音の読み違いがあったのでしっかり読み直すこと。一人だけ、勝手に調性を変えていたところもありましたので・・・。
2007年9月15日(土)
12月演奏会、「シンデレラ」の譜読みです。「ロメジュリ」を演奏したときも同じ事を感じたのですが、音程やリズムの難しいところが隠れることなく、そのまま客席に伝わってしまいます。プロコフィエフの作品は、皆そうなのでしょうか。なかなか手ごわそうですね。
曲との格闘もありますが、今回は新しいピッコロとの格闘もあります。楽器屋さんで音だししているのとオーケストラの中で使うのとでは、感覚がまるで違いました。オケで吹くときは、慣れている楽器だとこの辺にいると居心地がいい、という感覚があるものです。ところが今日は全くそれがありませんでした。音程はもちろんですが、どのくらいの息の圧力をかければフォルテでちょうど良く響くのかも、まるで分からない状態。前の楽器と同じ圧力のかけ方ではちょうど良く響かないことは、今日の練習で分かりました。師匠が、「ピッコロだけは自分の楽器で癖を知り尽くした楽器でないと演奏できない。他人の楽器を使っての演奏は考えられない。」とおっしゃった事が、今日はよく分かりました。
左は、ピッコロのケースを開けた状態。裏地が緑色というのは、珍しいかもしれませんね。黒、ワイン、青などが一般的だと思うのですが、私はこの緑色は初めて見ました。少しだけ楽器の写真を載せようと思いましたが、全く音だしもせず、いきなりシンデレラで手荒に扱われたからでしょうか、ヨハネスはご機嫌ななめでしたので、今回は出演を見送りました。代わりに、ピッコロの必須小道具を掲載します。右側の写真です。
まずは掃除棒。今まではフルートと同様、掃除棒にガーゼを巻いていたのですが、ピッコロの場合は包帯の方が良い、という話を聞きましたので、今回からそうしています。そして、左上の袋に入った醤油挿し。これは、ベビーオイルです。これも今回から持ち歩いているものですが、管内が濡れている時に管の外側もオイルで、ほんの少しだけ濡らすことで、楽器が良い状態になるとのこと。まだ、試していませんが、本格的に12月へ向けての練習(私のピッコロの出番)が始まったら、使ってみようと思います。そして黄色いのが耳栓。その右にあるのが、クリーニングペーパーです。ピッコロの演奏を成功させるには、練習+演奏中の水滴取り、が必須です。
余談ですが、練習の休憩中に、フランスのルイ・ロットを吹くことができました。カバードキーでシリアルも不明、右小指で操作するレバーもティアーズドロップではありません。私のイメージする典型的なロットではなかったのですが、「Louis
Lot」の刻印はありましたし、Aisレバーのつくりはそれらしかったので、ロットの雰囲気はなくはありません。モダンの楽器に慣れていると、なんと息の入らない楽器だろうと思いますが、これはこれでセカンド楽器としては楽しむことができるかな、と思います。
2007年9月8日(土)
前半は、12月演奏会のチャイコスフキー5番です。オーケストラで吹き始めて15年超。マーラーの1番、2番、3番、4番、5番、ブルックナー4番、8番、ツェムリンスキーの人魚姫、ショスタコーヴィチの森の歌、等を経て、ようやく人生初のチャイコフスキー5番にたどり着くことができました。
このチャイ5、チャイ4やドヴォ8と並んで、学生オケで演奏される頻度がきわめて高い曲、と思われます。そのためか、幸いにも学生時代に社会人オケに入団する機会に恵まれた私としては、逆になかなかこの曲を演奏する機会がありませんでした。マーラーの復活のように、どうしても演奏してみたい曲、というわけではありませんが、多くの人が当たり前のように演奏している曲を自分が演奏できないでいることに、少し寂しさを感じていました。先述のチャイコフスキー4番とドヴォルザーク8番、こちらはいまだに演奏していない記録を更新中です。
さて、今日は初練習ですので、全体の譜読みです。初めて吹いてみて、そうですね、フルートは(も)結構難しいことをやっているけど、あまり活躍しているように聴こえない曲ですね。フルートに限って申し上げると、その点では、マーラーの5番と印象が似ていると思いました。指使いの難しいところも何箇所があるので、しっかりさらわないと。後半は、10月演奏会の天地創造を練習しました。
来週は、シンデレラの譜読み。いよいよ、ヨハネス・ゲルハルト・ハンミッヒのデビュー戦です。新しい楽器なので、木が割れないよう慎重に扱わないと。でも、曲がかなり激しいので、とても心配・・・。
2007年9月1日(土)
1ヶ月間の夏休みが終わり、ようやく練習再開。久しぶりのオーケストラです。
今日は10月の天地創造のマエストロ練習です。1曲目から、じっくり練習をしました。全体的に感じたことですが、音楽にゆとりがないですね。テンポの速めの曲では、音符を追いかけることに必死で、慌てている雰囲気がありありです。私自身も、曲の途中で現在位置を見失う場面が数回あり、反省。また、今回は2番を担当しますが、1番を吹く時と比べると、どうしても個人練習の時間が少なくなってしまいます。ローテーションの関係で、他の曲で1番を吹くことになれば、当然そちらを優先しますので。そこで影響が出てくるのが、一つ一つの音符に対する神経の行き届かせ方です。2番を吹くときはそれが、甘くなってしまいます。最低限、全体の演奏に支障がないようにしないと・・・。
・トップへ戻る
2007年8月4日(土)
オーケストラの練習はありませんが、笛のレッスンを受けてきました。ここ数ヶ月間、1ヶ月に1度のペースで順調に受けています。レッスンの内容も順調であればなおいいのですが、なかなかそうはいきません。
・T.ベーム: 24のカプリスよりNo.5(写真左)
・T.ベーム: 24のカプリスよりNo.6(写真右)
・ドンジョン: パン!
レッスン日が決まると、その日に向けて大雑把に練習予定を組むのですが、今回は十分な準備ができませんでした。レッスンとはいえ、練習の成果を師匠という人前で披露することには変わりはありませんので、準備はとても大事です。今日は、全くダメでした。練習不足の上、口や手に必要以上の力が入っていた・・・。こういう時って、不思議なくらい楽器をコントロールすることがができなくなり、音も汚くなる。適度な脱力の大切さを、またまた感じたレッスンでした。練習不足がばれてしまったのか、師匠のアドバイスも少なく、いつもよりレッスンが早めに終わってしまいました。
このレッスン中、ピッコロのことも相談をしました。これまで試奏してきた楽器で気に入った楽器について話し、師匠から「オーケストラで使うピッコロとは」、「どういう状態のものがいいピッコロか」、「どこのお店に行くか」などなど、色々なアドヴァイスを頂きました。これでさらに良いピッコロ選びができそうです。レッスンそのものはなんとも情けない内容でしたが、このピッコロのアドヴァイスは、今日の唯一の収穫だったように思います。
2007年7月28日(土)
10月の天地創造のマエストロ練習ですが、先週に続いて、遅れて練習に参加。モーツァルトと違い、笛をきちんと編成に入れてくれるハイドンですから、毎回の練習が楽しみです。
この曲で笛が一番目立つ曲は、第3部冒頭の第27曲「RECITATIV」。5~6分の曲ですが、その大半がフルートの三重奏で占められています。E-durのとても美しい曲!!吹いていてとても気持ちのいい曲なのですが、3本がさらに寄り添えるともっともっといい演奏ができると思います。他の曲はフルート2本なのですが、この27曲目だけ3本目のフルートが必要になります。ハイドンはなぜこんな非効率的な使い方をするのかなと思うのですが、どうしてもここはフルートの3本の響きを求めたかったのでしょう。せっかくハイドンがフルートのためにこんなに美しい曲を書いてくれたのですから、それにふさわしい音を奏でたいものですね。
余談ですが、オラトリオでフルートが目立つ曲をもう少し。天地創造は3本フルート中心ですが、弦楽器が伴奏であったり、また途中で色々な楽器が顔を出してきます。全く他の楽器の出番のない曲もあります。それは、ベルリオーズのオラトリオ「キリストの幼児」です。第3部、フルート2本とハープ1本の計3人だけで、なんと6分間演奏する曲があるのです!他の楽器は一切入りません。これまたハイドンに負けず、とても美しい曲です。この曲が演奏されること自体がまれですので、私がオーケストラで演奏できる可能性は少ないでしょう。確かにこの編成なら、フルートのアンサンブルで抜粋で取り上げることはできます。でもですね、本当はオーケストラの中で、オーケストラを聴きにきたお客さんの前で、ベルリオーズが書いたとおりに演奏したいですね。以上、余談でした。
・トップへ戻る
2007年7月21日(土)
エロイカが終わって、すぐにハイドンの天地創造の練習です。本格的な練習は9月からで、その前の練習は今日と来週の2回だけ。10月と12月の2つの演奏会を、同時進行で練習していきます。ここ数年、このパターンが続いているのですが、10月の演奏会では、だいたいモーツァルトの宗教曲が選曲されることが多いですね。モーツァルトの宗教曲、とてもいい曲なのですが、フルートを演奏する立場になると、実はあまりうれしくありません。まず、編成にフルートが入っていないことが多い。フルートのある曲でも、ほとんどがお休みで、1曲のみ出番あり、というパターン。まるで活躍の場がありません。今年はハイドン。モーツァルトと違い、フルートに活躍の場を与えてくれます。彼は、なかなかいいやつです。同じ時代に生きていたら、やつとは仲良くなれたかもしれません。練習回数がとても少ないのですが、いい演奏会になるよう、準備をしていきたいと思います。
初練習の今日は、譜読みです。弦楽器もぐっとプルト数を減らしてきました。このくらいの数であれば、木管楽器は自然な音量で吹いても、十分に響かせることができます。前回のベートーヴェンの交響曲と今回のハイドンのオラトリオ。どちらも1番フルートが活躍する機会が多いのですが、ハイドンの方が「歌」を意識する機会が多いですね。面白そう。今日気に入った曲は、13曲目のRECITATIV.です。弦と1番フルートのPPから楽器が重なっていき、時には同じ音になったり、再びハーモニーをつくったり。聴いていて、ハッとするような美しさを感じる曲です!
これまでの特別企画
・NO.21 ベートーヴェン:交響曲第3番「英雄」アマオケ練習日記
(2007年7月)
・No.20 ショスタコーヴィチ:オラトリオ「森の歌」アマオケ練習日記
(2007年2月)
・No.19 コダーイ「ハーリヤーノシュ」アマオケ練習日記
(2006年12月)
・No.18 マーラー交響曲第2番「復活」アマオケ練習日記
(2006年7月)
・No.17 歌劇「カルメン」&「バラの騎士」組曲
アマオケ練習日記
(2005年12月)
・No.16 ツェムリンスキー交響詩「人魚姫」 アマオケ練習日記
(2005年7月)
・No.15 マテキフルート工場見学記
(2005年4月)
・No.14 Ph.ハンミッヒ木管フルート ノマタチューンナップ記
(2005年2月)
・No.13 ベートーヴェン交響曲第9番「合唱」 アマオケ練習日記
(2005年2月)
・No.12 新世界より&キャンディード アマオケ練習日記
(2004年12月)
・No.11 ロイヤルコンセルトヘボウ管弦楽団2004年日本公演レポート
(2004年11月)
・No.10 幻想交響曲&ラヴァルス アマオケ練習日記
(2004年7月)
・No.9 ハイドン交響曲全104曲 完全制覇日記
(2003年11月より)
・No.8 イスラエルフィルハーモー管弦楽団2003年日本公演レポート
(2003年12月)
・No.7 シカゴ交響楽団2003年日本公演レポート
(2003年10月)
・No.6 マーラー交響曲第5番アマオケ練習日記
(2003年7月)
・No.5 ギルバート・キャプラン
(2002年8月)
・No.4 月に1度はコンサートへ行こう企画2001年総括
(2002年3月)
・No.3 ウィーンフィルハーモニー管弦楽団2001年日本公演レポート
(2001年10月)
・No.2 マーラー交響曲第3番アマオケ練習日記
(2001年7月)
・No.1 ベルリンフィルハーモニー管弦楽団2000年日本公演レポート
(2000年11月)