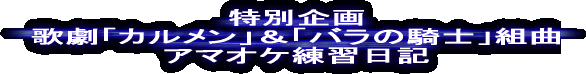
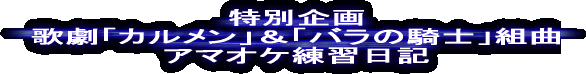
2005年10月16日(日)午後2時開演
市川市文化会館大ホール
ビゼー:歌劇「カルメン」(全4幕 ホールオペラ形式)
指揮:山崎 滋
独唱:伊原直子(カルメン)、他
市川交響楽団
(無事終了いたしました)
*********************
2005年12月11日(日)午後2時開演
市川市文化会館大ホール
ヴォーン・ウイリアムス:グリーンスリーブス幻想曲
ブリテン:青少年のための管弦楽入門
ブルッフ:ヴァイオリン協奏曲
R.シュトラウス:「薔薇の騎士」組曲
指揮:新通英洋
独奏:神保聡子
(ヴァイオリン)
市川交響楽団
(無事終了いたしました)
12月11日(日)
いよいよ演奏会当日。バラの騎士の譜読みを始めたのが、10月22日。2ヶ月未満の練習で、R.シュトラウスの本番です。
いつものように9時過ぎにホールに入り、音だし。10時30分より、本番とは逆順でリハーサルが始まりました。バラの騎士は少しずつまとまってきた、ブルッフはソリストとオケの距離が縮まり、ブリテンは完成度が高くなりつつある、そんな印象です。
午後2時開演。今回演奏するにあたって、ブリテンとR.シュトラウスでは、一つずつ目標を持ちました。ブリテン、フーガの出だしのテンポを指揮者と完全に共有すること。そしてR.シュトラウス、良い音程で歌心を忘れないこと。
グリーンスリーブスが終わり、ブリテン。出だしからオーケストラの呼吸がピッタリと合い、良いスタートを切れました。それぞれのソロもぴしっときまり、順調な展開。いよいよフーガにさしかかり、ピッコロの状態を確認し、出だしに細心の注意を払う。指揮者のテンポに正確に反応をしたつもりでしたが、完全に共有できたとは言いがたいですね。吹きながら少しテンポを修正する気持ちになってしまいましたので・・。
後半のブルッフ、ソリストもなかなか堂々とした弾き振りで、良かったですね。良い雰囲気で、音楽をつくっていたと思います。そして、メインのバラの騎士。始まる前のチューニングから、少し違和感を感じました。ちょっと、周りと合わないなあ。出だしのメロディも綺麗に決まり、オケとしては、良い出だしだったように思います。でも、私はすぐにその違和感が、現実のものとなってしまいました。いつもと自分の音(ピッチ)の居場所が違うのです。こうなった以上、歌心を忘れずに、吹ききることだけを考えるようにしました。全体としては、本番が一番まとまったかな、とは思います。それにしても、なんと難しい曲なんだろう。
通常、演奏会まで約3ヵ月半の練習期間をかけることが多いのですが、今回はそれよりもかなり短いものでした。練習内容を見ても、その期間で考えられるベストの内容であったと思いますし、マエストロの細かい”授業”も、今のオーケストラをランクアップさせるのに、必要な指導だったと思います。ただ、今の私の技量では、R.シュトラウスを味わったり消化するのに、時間的に無理がありました。きちんと仕上げてくる人もいるので、そういうレベルにまで引き上げることが今後の私の課題にしたいと思います。そして、なかなか取り上げられる曲ではありませんが、数年後には再び1番フルートを吹き、今回よりもレベルの高い演奏ができるよう、リベンジをしたいです。(終)
12月10日(土)
前日のGP。ホールでの練習です。本番と同じ曲順で、練習が行われました。
ホールで音を出して感じたこと。毎回のことですが、いままでの練習会場との響きの違いを感じ、周りとの距離感がつかめません。演奏をしているうちに段々と、つかめてはきますが。
さて、降り番のグリーンスリーブスの後のブリテン。先週は全くこの曲の合奏がなかったので、今一アンサンブルがうまくいきませんでした。吹いていて、しっくりとこないですね。私も、指揮者の感じているテンポをきちんと把握することが出来ず、合奏を止めてしまいました。常にアンテナを張らないと・・・。木管のアンサンブルがあるテーマB、事前に音の形を打ち合わせをしたので、その部分の改善は見られました。その後のブルッフは、出だしの木管のアンサンブル以外は、まあこんなものでしょう。
最後は、ここ数回問題だらけのバラの騎士。今日は、今までの中では一番良かったように感じました。でも、この曲の魅力はまだまだこんなものではないでしょう。もうGPですから、後は本番での集中力。オペラの場面イメージできるような、演奏がしたいものです。
12月4日(土)
本番1週間前。諸事情により、途中から参加。そして、個人的には今までの中で最悪の出来でした。
前半はソリスト付でブルッフ。かなり細かく、テンポ、音色、入りのタイミング等、そろえました。マエストロによる、”オーケストラの授業”は直前まで行われます。本当に1つ1つ意味のある音楽になります。これを忠実に、本番までに忘れずに実行できたなら、きっと良い演奏ができるだろうな、という感じがいたします。
さて、メインの問題のバラの騎士。この時期になっても、いまだに私の前に大きな壁が立ちはだかり、前に進めないでいます。どうしたらそれが解決できるのか、きっかけがつかめないでいます。さすがに1週間前となると、焦りが出てきました。大きなソロがあるパートに比べれば、まだ余裕があるべきなのでしょう。でも、大きなソロがなくても、全く余裕がありません。参りました・・・。
「第九」の1番を初めて吹いたときも、そしてオーケストラで初めて1番を吹いたときも、大きな壁を感じました。今回の演奏会も、私にとってそのような1つの大きな演奏会なのかもしれません。思い返してみると、そのときもああでもない、こうでもないと自分の中で試行錯誤していたような気がします。アンサンブルですから、周りに悪い影響を与えることはできませんが、許される範囲内で、直前まで色々試してみようと思います。
11月27日(日)
日曜日の特別練習。土日練習は、2週間連続です。10月中旬から本格的な練習を始めましたので、しょうがないですね。
グリーンスリーブスの練習の様子(2枚とも)
午前中は、私が降り番のグリーンスリーブスから始まり、メインのバラの騎士の順です。バラの騎士、ソロ陣はかなり良くなりました。聴いていて、おっ、と思う瞬間もあります。トゥッティは少しずつ良くはなっていますが、まだ自分のことでいっぱいいっぱいという感じがします。
私にとってもこの曲は、はっきり申し上げまして、自分の技術的キャパシティを超えています。毎回ここはこうしたらどうか、うまくいかなかったから次回はこうしてみよう、というように自分なりの課題は持っています。でも、うまくいかないことのほうが多いですね。そういう状況ではありますが、せっかくバラの騎士を演奏できる機会をもらいました。本番までに、自分のもてる力は発揮できるようにしていきたいと思います。
午後はブルッフ。ソリストと一緒に、練習が行われました。オケとソリスト、少しずつ近寄って気がします。来週もソリスト付ですので、まだまだ良くなるでしょう。最後はブリテン。今までとは打って変わって、通しの練習がメインでした。無事通りました。これも、これまでのマエストロの根気強い”オーケストラの授業”のおかげでしょう。
残りあと2週間。ひとつひとつ確実に・・・。
11月26日(土)
前半はブリテン。今日も、徹底的に”オーケストラの授業”でした。出だしのテーマを何度も繰り返し、ピッチ、音の形、ニュアンス、テンポ等、注意がありました。特に、心の中で刻むパルスが一番の問題のようです。長い音になったときに、お客さんの方から聴いていていると、行き先不明の音になるようです。しっかりテンポを心の中で刻む、これがまず一番注意しなければならいことです。
後半は、ソロ付きでブルッフです。とても繊細な音色のヴァイオリンです。後数回の練習で、ソロ・指揮者・オケのアンサンブルが整ってくると、良くなるでしょう。
・トップへ戻る
11月20日(日)
日曜日の特別練習。全曲の練習が行われました。本番と同じ曲順です。
グリーンスリーブス、降り番のはずですが、練習開始5分前に急遽譜面をもらい、代奏をすることになりました。まあ、フレーズ感も何も考える余裕はなく、ほとんど弦楽器の練習で終わってしまいました。
打楽器が勢ぞろいしたブリテン、全曲最初から最後まで通すことはなく、部分的に、とにかくきっちりと細かく練習をしました。昨日同様、”オーケストラの授業”です。メンバーが揃うと、合奏をしていて気持ちがいいものですね。
午後はブルッフから。比較的演奏をし慣れている曲ですが、ここでも”オーケストラの授業”が。ということは、曲の難易度にかかわらず、基本的にオーケストラに大切なことが欠如している、ということでしょう。そういうご指導は、大いに結構です。どんどんお願いします。漫然と演奏していることは、自分のためにもならないし、何よりも聴いているお客様が退屈してしまいます。
さて、メインのバラの騎士。昨日よりは数段マシになりました。というのは、部分的ではありますが、お互いに聴き合えるようになったからです。これは大きな進歩です。本番までには、1曲丸ごと、アンサンブルができるようになりたいですね。「銀のバラ」のテーマのニュアンスも、昨日と変えて吹いてみましたが、良かったようです。よしよし、今日の練習は本番で良い演奏をするための、きっかけにしたいです。
11月19日(土)
前半は、久しぶりのブリテン。10月8日に書いた、マエストロによる”オーケストラの授業”、再開です。普段は何となく演奏してしまっていることに、気づかされてしまいました。音の出だし、中の膨らませ方、音の処理の仕方、etc.・・・。こういう練習は、とても大切だと思います。トレーナー能力のある指揮者が指導していただいて、普段からこういう練習ができていると、オーケストラはどんどん良くなっていくでしょうね。
後半はバラの騎士。先週よりはマシになりましたが、まだまだ曲になっていません。私も、楽譜を追うのが精一杯で、とてもアンサンブルや、曲の表情などを考える余裕がありません。
11月12日(土)
いつものように遅刻をして参加。しかも、1時間以上の遅刻。これがバラの騎士を、しかもトップを吹く人のとる態度とは思えません。本当にこの途中参加って、気分が悪いものです。そんな途中から参加して、まわりといいアンサンブルをしようなんて、そんなこと考えが甘すぎるんだよね・・。
マエストロによる、初のバラの騎士。主に物語の説明をしながら、合奏が進められました。マエストロが本当にこの曲が好きなんだなあ、というのが伝わってくる指揮振りです。ただ、それ以上に曲そのものが難しく、そういった説明もなかなか自分の中に吸収することができず、なんとも安定感のないフルートになってしまいました。
いまのところ、この曲に共感できる部分が少なく、それが難曲をさらに私のフルート演奏を難しくしているのかな、と思います。リング場で、口から泡をふいてギブアップ寸前、そんな感じです。いや、いかんいかん、そんな気持ちでは!きっと12月までには、官能的な音楽が創り出される!!
11月5日(土)
今日は、弦楽器のみの練習で、管楽器はお休みです。なにも書くことがないので、写真を掲載いたします。バラの騎士のスコア表紙(左)と1ページ目(右)です。
10月29日(土)
トレーナー不在の中で、合奏が行われました。前半は、ブリテンの「青少年」が行われた模様。ピッコロのソロがあるにもかかわらず、私は時間に間に合わず、参加ができませんでした。ほんとにまあ、一番練習しなければならない人が参加できないなんて、先が思いやられます。
後半の「バラの騎士」からは、無事に参加。テンポをぐっと落とし、一つ一つ確認するように、進められました。前回よりは、少しマシになったかもしれません。でも、繰り返しになりますが、難しい曲です。調性も、ピッチも、強弱も、色々確認・調整しなければならないことが山ほどあります。
さらに、体力的なペース配分を考えなければなりません。ベートーヴェンの「第九」のことを思えば、まだ楽なのですが、この曲も最初から最後まで100%で吹ききることは、ちょっと難しいですね。曲を壊さず、いいペース配分ができるよう、毎回の合奏で探って行きたいと思います。
10月22日(土)
カルメンも終わり、12月の演奏会モードに突入します。
前半は、ブルッフを練習しました。数年前にも一度演奏したことがあり、譜読みというよりは、記憶を取り戻す、と言った感じでした。後数回練習すれば、大丈夫でしょう。ソロ代奏のコンミスの演奏、素晴らしかったです。お疲れ様でした。
ようやく「バラの騎士」の練習に取りかかれます。一度さっと通しましたが、これはかなりヤバイ。演奏をしていて、不快感を覚えたくらいです。いくら初見とはいえ、様にならないのも限度があります。なんと言ったらいいのか、そこから逃げてしまいたい気分。そんなことを言ってもしょうがないので、ひとつひとつ練習を重ねていくしかありませんね。
10月16日(日)
いよいよ、歌劇「カルメン」全4幕の上演です。いつも本番当日は、早めに行って、誰もいないホールで一人吹くのが習慣ですが、今日は早すぎて、文化会館がまだ開いていませんでした。開くのを待って、早速ステージで楽器の音だしです。
今回は当初、ステージ形式ということでしたが、下の写真のように、オーケストラピットができ、舞台にもちゃんと大道具が並んでいます。結局は、本格的なオペラ公演になってしましました。
午前中は、前日の通し稽古から、いくつかを部分的に取り上げて練習をしました。ここにきて、いまだにアンサンブルをする感覚がつかめません。オペラ自体に慣れてないだけでなく、何よりもいつもとは違う場所、かつ今まで頼りにしてきた音が聞こえにくい位置にいることが、原因です。
木管を下手後方に並べる配置は多くの歌劇場でとられる配置ですが、とても吹きにくい。ニューヨークのメトロポリタンでは、指揮者の目の前、つまり(木管は)通常のオーケストラの配置で演奏することがあるようです。アンサンブルのやりやすさでは、断然後者の配置がいいですね。下は、リハーサルの様子です。
カーテンコールのリハの様子 本番直前にさらうファゴット氏
舞台裏で演奏するための準備 暗いオーケストラピットの中
予定通り、午後2時に開演になりました。まあ、客席は凄い人・人・人。1階も2階も立ち見のお客様が多数いました。肝心の演奏、前日はテンポが3つくらいあった前奏曲、今日は決まっていました。途中、やはり何箇所か危ないところがありました。私も演奏全体に影響を与えかねないミスを、2つも起こしてしまいました。あーっ、申し訳ない。
歌手陣は、素晴らしい歌を披露してしまいました。若手のミカエラ、エスカミーリョは伸びのある、声量のある歌声。ベテランのカルメンとホセは、出てくるだけで舞台の雰囲気をがらっとかえるオーラをもって登場。それぞれの持ち味を発揮され、アリアでは拍手喝采でした。
そんな順調に進んでいった公演でしたが、第4幕で事件が起こりました。これからホセとカルメンの睨み合いが始まるころ、なんと震度4の地震が! 客席もざわつき始め、私も身をかがめました。オケピットは人が歩くだけで揺れる場所ですので、体感震度は5くらいに感じました。しかし、マエストロは気がつかなかったのか(!?)、音楽は一瞬たりとも止まることなく、進行しました。ああ、恐かった。
初の本格的なオペラ、結構はまるかもしれません。次は、プッチーニの「トスカ」を!
10月15日(土)
「カルメン」、前日のGPです。当初は、コンサート形式ということでしたが、実際はピットをかなり下げ、譜面台のライトをつけるほどの、本格的なオペラ公演になるようです。
ピットの中からステージを見あげる ピットの中の様子(FlはVlの後ろ)
曲が始まり、音を出してみて驚きました。いつもの音の聞こえ方と、全く違うのです。音が散ってしまい、周りの音がよく聞こえません。客席から聞いていた人は、最初はオケのテンポが3つくらいあった、と言っていました。いやー、まずいまずい。何を頼りにしていいのか。やっぱり、いつも以上に、指揮者をしっかり見るしかないですね。この状況(ピットの中+ヴァイオリンの後ろ)で頼れるものは、これしかありません。
今日は、本番と同じように、最初から最後まで通しました。オケは実質1ヶ月半の練習。オペラ経験のほとんどないオケにはとてもきつかったですが、私はとても楽しめそうです。きちんと吹けるかどうかは、別として。
10月10日(月・祝)
午前10時から午後4時までの、「カルメン」の特別練習。
とにかくシンフォニーと違い、機敏に反応することでしょうね。指揮を見て、歌を聴いて。これにつきます。
以上。
・トップへ戻る
10月8日(土)
12月の演奏会の練習日。今日はいつもの練習とは一味も、二味も違うものでした。まるで新通先生の”オーケストラの授業”を受けているような、そんな一日でした。
前半は、「グリーンスリーブス」。これは私は降り番。後半は「青少年」(ちなみに難曲「バラの騎士」は、「カルメン」の公演が終わり次第、練習に入ります)の練習。ラストのフーガから始まりました。ピッコロの出番! このピッコロ、とても目立つソロですが、実は指使いそのものはあまり難しくありません。強いて申し上げれば、出だしでいかに平常心で吹けるか、ということだと思っていました。しかし、私の考えはかなり甘かったようです。マエストロの”授業”を受けて、フレージング、音量=周りとのバランス、ブリテンの和声・リズム等々、考えなければならないことが山ほどでてきてしまいました。またこの部分だけではなく、トゥッティでの全員の呼吸のそろえ方、フォルテとフォルテシモの違いなど、基本中の基本、だけど今は忘れてしまっている、そんなことを思い出させてくれました。
アマオケを振る指揮者は色々なタイプの方がいらっしゃいますが、今はこういうようにトレーナーの部分まで踏み込んでやられる方が少ないように思えます。オケから嫌がられるからでしょうか、あるいは本番指揮者のやることではないのからでしょうか。ベルリンフィルのような完成したオーケストラならともかく、アマオケでは必要なことではないでしょうか。そういう基本部分をきっちり行うことで、団員自身が本番で良い気分で演奏できるのでは、と思います。
今日のマエストロの”授業”で一番印象に残った言葉、「良い音を出すのは準備に限る」、です。これは私自身も日ごろ忘れずに行っていることなので、ちょっと自身を持ちました。
・トップへ戻る
10月2日(日)
10月の「カルメン」の特別練習です。今日は豪華です。ミカエラを除くソリスト、全員が集合。もちろん主役のカルメン、伊原直子さんも登場しました。
下手に位置するフルートの座席から指揮台を見る マエストロと打ち合わせをする伊原さん(写真左)
午前10時から、約30分間、いままでほとんど手の付けられなかったオケだけの曲をさらいました。その後午前中いっぱい、合唱団との合わせです。今回は、ステージ形式のオペラですが、左上の写真のように、ピットに入った時に近い並び方をします。つまりフルートは下手、ヴァイオリンの後方に位置します。いつもは中央から指揮者を見ているので、やはり違和感があります。いつも以上に、集中しなければ、ポイントポイントを見失いかねません。
午後はソリストが入り、熱のこもった練習が行われました。ソリストの皆さん、素晴らしいですね。ホセ、エスカミーリオ、それぞれ持ち味をだされていたと思います。でも主役はカルメン、伊原直子さんだったと思います。特に「ラララ・・・」でのカスタネットを交えた演技には、鳥肌が立ちまくり!!! この一曲だけでも、練習に参加、伊原さんを見ることができて良かった、と思いました。ここの場面だけではなく、ソリストの皆さんは、すでに振付もされていました。
充実した合奏でしたが、人前で演奏をするにはもっともっと練習をする必要があります。「カルメン」の練習は残り1回とGPを残すのみとなりました。
10月1日(土)
今日は12月の演奏会の練習です。曲は「グリーンスリーブス」と「青少年」。指揮は本番の指揮者、新通先生です。かなり高度な、そしてハードな練習に感じられました。
まずは、私は降り番の「グリーンスリーブス」。終わりの5分ほど聞きましたが、いきなり”新通節”というか、”カンタービレ”のグリーンスリーブスでした。本当に短い曲ですが、1時間も練習していましたので、かなり細かい練習をしたのだと思います。私は舞台袖で聞くこととなりますが、本番が楽しみです。
さて、ピッコロで出演する「青少年」。はっきり言って、私のピッコロはなっていません。マエストロの要求も、今の私には高度すぎてちょっとついていけないところがあります。アドバイスをもらって、自分なりに練習をして解決できそうなところもあります。しかし、特にフレーズの取り方は、難しいですね。アドバイスを受けても、そういうふうに感じることができない等、音楽的なセンスの問題もあります。まあ、とりあえずやるだけやってみます。しかし、ラストのフーガが2つ振りだとは、想像もしませんでした。3つ振りにしてもらえないかなあ・・・。
明日は、10月の「カルメン」の1日練習です。
9月25日(日)
午前10時から午後4時までの特別練習日。午前中はオーケストラだけでの練習でした。オペラ独特の間の取り方に時間を割きました。つまり、歌手がどんな歌い方をしてもついていくような練習です。具体的には、指揮者が振るたびに、微妙にテンポや間の取り方を変えていました。譜面は大分読めてきましたので、もう少しさらう必要があるのはこういう部分でしょう。
個人的には、第2幕の「ロマの踊り」を練習する必要があります。もう一度メトロノームを使ってさらい直しです・・・。
午後は合唱団との合わせです。やっぱりオペラは、歌を入れるとガラット変わります。これでソリストが入ると、また変わるんでしょうね。今日はこのくらいにします。ちょっと、疲れました。
9月24日(土)
弦楽器のみの練習のため、お休み。明日は、「カルメン」の特別練習日です。
・トップへ戻る
9月17日(土)
2ヶ月ぶりに、Fl大村先生のレッスンを受けました。Andersenの9番と10番。9番は、規則的な音符の繰り返しで、少しアドバイスを頂いてすぐにパス。10番は歌が前面に出てくる曲で、致命的な音符の読み違いもあり、問題あり。音楽の流れのとらえ方、それに伴う音符の感じ方・吹き方等、たくさんアドバイスを頂きました。少しは、マシになったかも・・。次回、もう一度再チャレンジです。
さて、今日は前半は12月の「青少年」、後半は10月の「カルメン」です。一通り譜読みをした段階ですが、個人的には木管セクション内でのアンサンブル、特にピッチに気をつける必要があります。オケ全体としては、そうですね、そもそも曲がソロ合戦なので、ちょっと楽器が抜けていると、どうしてもつながりません。
カルメン、オペラ独特の音楽に前回は苦戦しましたが、今日は少し進歩が見られたような気がします。慣れてきたのでしょうか。もちろん、まだまだ形になっていない場面もありますが、演奏する喜びを感じられるようになりました。練習回数が極端に少ない演奏会ですが、なんとかいけるか、と今日の練習をしながら思いました。
・トップへ戻る
9月10日(土)
10月の「カルメン」の練習日。指揮は、本番の指揮者の山崎先生。途中からの練習参加でしたが、曲順に進んでいきました。私自身、本格的なオペラは初めてで、果たしてどんな練習、本番を迎えるのか、楽しみです。そして、カルメン役の伊原直子氏! どんな歌声を聞かせてくれるのでしょうか。
と期待の大きな公演なのですが、練習は苦戦続きでした。組曲にもあるオケだけの曲は、演奏経験のある人がある程度いるので、まあまあ、といったところです。でも、組曲にない曲、そしてレスタティーヴォはなかなか難しいですね。私自身もそうですし、オケもそうなのですが、オペラはほとんど経験がありません。慣れるまで、少し時間がかかりそうです。
慣れるといえば、このカルメンから新しいフルートを使用しています。前回の「青少年」は、ピッコロでしたので、実質今日がオケデビューです。初めはチューニングもせず合奏に参加したので慌てましたが、少しずつ「アンサンブル」の中でのクセ、をつかんでいきたいと思います。音そのものは、良いと思います。吹き込んだときの楽器の振動が、なんとも心地良い!
・トップへ戻る
9月3日(土)
これから3ヶ月間に、上に書いてあるように、別プログラムで2つの演奏会があります。もちろん、演奏してみたい曲ばかりなので嬉しいのですが、果たして個人的に本番までに仕上げることができるか、多少の不安もあります。
今日は練習初日。12月のプラグラムから、「グリーンスリーブス」と「青少年の管弦楽入門」です。「グリーン」は弦楽器とフルート2本、それにハープのみの編成。私は降り番。約20分ほどで、練習が終わってしまいました。「青少年」は残り時間、たっぷり練習をしました。アシスタント指揮者による、的確な指導が印象的でしたね。特に、音の発音を言葉の発音と同じようにやってみる指導は、他のどの曲にも応用することができ、とても役に立つアドバイスだと思いました。
・トップへ戻る
これまでの特別企画
・⑯ツェムリンスキー交響詩「人魚姫」 アマオケ練習日記
(2005年7月)
・⑮マテキフルート工場見学記
(2005年4月)
・⑭Ph.ハンミッヒ木管フルート ノマタチューンナップ記
(2005年2月)
・⑬ベートーヴェン交響曲第9番「合唱」 アマオケ練習日記
(2005年2月)
・⑫新世界より&キャンディード アマオケ練習日記
(2004年12月)
・⑪ロイヤルコンセルトヘボウ管弦楽団2004年日本公演レポート
(2004年11月)
・⑩幻想交響曲&ラヴァルス アマオケ練習日記
(2004年7月)
・⑨ハイドン交響曲全104曲 完全制覇日記
(2003年11月より)
・⑧イスラエルフィルハーモー管弦楽団2003年日本公演レポート
(2003年12月)
・⑦シカゴ交響楽団2003年日本公演レポート
(2003年10月)
・⑥マーラー交響曲第5番アマオケ練習日記
(2003年7月)
・⑤ギルバート・キャプラン
(2002年8月)
・④月に1度はコンサートへ行こう企画2001年総括
(2002年3月)
・③ウィーンフィルハーモニー管弦楽団2001年日本公演レポート
(2001年10月)
・②マーラー交響曲第3番アマオケ練習日記
(2001年7月)
・①ベルリンフィルハーモニー管弦楽団2000年日本公演レポート
(2000年11月)