

2007年7月15日(日)午後2時開演
市川市文化会館大ホール
入場無料
スメタナ:連作交響詩「我が祖国」より
第4曲「ボヘミアの森と草原より」(2nd Flute)
ヴォーン・ウィリアムズ:チューバ協奏曲(降り番)
~チューバ独奏:趙放(チョウホウ)~
ベートーヴェン:交響曲第3番「英雄」(1st
Flute)
指揮:森口真司
市川交響楽団
(終了いたしました)
2007年7月15日(日) 最終回
本番当日です。9時20分に楽屋入り。いつもより少し遅め。音出しをしながら、昨日うまくいかなかったところを何箇所か確認。予定通り、10時よりリハーサルを開始しました。エロイカ、一つ一つ確認しながら吹いていましたが、昨日混乱したところは整理されてきたように感じました。リハの時間の大半をエロイカに割きました。マエストロの気持ちが表れていましたね。その後は、チューバ協奏曲、ボヘミア、アンコールの順に進みました。
この日記の初回(3月3日)に、長年このオーケストラで活躍されていた方が亡くなったことを書きました。写真右のフルートの足部管、私が2年前まで使っていた楽器に時々接続していたのですが、実はこの方の作品なのです。私の昔の楽器はC足部管がデフォルトでしたので、曲によって、あるいは気分によってH足部管にしていました。高音域を吹くことが多いときには、H足部管にしていたような気がいたします。でもこの足部管、ただのH足ではありません。さらに半音低いB音まで出せるジョイントつきの、特別仕様の楽器です。マーラーの4番でデビューしましたが、他のマーラーの作品でも何回か使用いたしました。今となっては形見となってしまいましたが、個人的にも大変お世話になった方でしたので、今日はホールまで持参いたしました。
午後2時、予定通り開演いたしました。台風の影響が心配され、お客様が本当にいらっしゃるのか不安でしたが、たくさんの方にホールに来ていただきました。本当にありがたいことです。1曲目のスメタナ、本番が一番良かったと思います。途中で破綻をしなかったですからね。2曲目のチューバ協奏曲。なんとも不思議なサウンドがする曲です。舞台袖で聞いていて、楽しめました。チューバのアンコールは、ポール・マッカートニーのマイラブ。
休憩後は、メインのエロイカです。この数ヶ月間、個人の練習の98%は、このエロイカにあてていたと思います。今日の演奏、オーケストラ全体はとても冷静で落ち着いた演奏をしていたと思いますが、私個人はこれまでで最悪の演奏でした。いつもなら演奏前、どんなに緊張をしても、最初のひと吹きをすればすぐに落ち着いて、練習の時と同じ気持ちで演奏しています。でも、今日は演奏が始まっても、手の震え、唇の震えが止まりませんでした。降り番で客席から聴いていた人から、音に伸びがなかったね、と。やはり、音に表れてしまいますね。今回は、今の楽器にも少し慣れてきて、その楽器でオーケストラの笛の醍醐味を味わえる古典の交響曲を、どこまで表現できるかを試してみたかった。演奏終えてベートーヴェンに、あの怖い顔のまま、もし演奏できが良ければゆっくりうなずいてほしい、と思っていました。が、これではベートーヴェンがどうこう、という問題ではなかったですね。せっかく数ヶ月間こつこつと積み上げてきたものが、この本番の日のためにしてきたことが、全て崩れてしまったような気がいたしました。残念でなりません。
オーケストラ全体では、第1楽章出だしの2発のフォルテ、実に良い響きでした。オーケストラは調子が良かった証拠ですね。第2楽章は、マエストロ感情むき出しの葬送行進曲。本番のステージでは、こうでなくては。休みの多いフルートは、演奏を楽しむことができました。第3楽章、危ない箇所もありましたが、なんとかのこりました。トリオのホルンは、いいですね。第4楽章、第1楽章同様、目立つところがたくさんあります。今日の自分がどういう状態か分かっていましたので、かなりやけになっていました。楽器の音が出なくなったら、声を出してでも音をつないでやろうと思っていました。最後まで、こんな感じでした。アンコールは、グルックのミュゼット、そしてドヴォルザークのスラブ舞曲より8曲目です。
第九と同様、エロイカも大変な曲でした。全てがさらけ出されてしまう、なんとも恐ろしい曲です。第九の1番フルートを初めて吹いたときも、さんざんの出来でした。2回目に吹いた時は、曲全体のペース配分も分かり、1回目より遥かに良い感触を得られました。今回のエロイカは、もう一度演奏する機会にはなかなか巡りあえないと思いましたので、今回一発勝負をしにいったのですが、見事に打ち砕かれてしまいました。まあ、いろいろなことがありますね。(完)
2007年7月14日(土)
オケの練習前に、笛のレッスンを受けてきました。曲は、T.ベームのカプリスの第3番と第4番。それに、ドンジョンのナイチンゲールです。私の欠点をずばり指摘する、かつ私に自信をつけてくれる貴重なアドバイスをいただきました。とても心に響いたので、申し訳ありませんが、内容は「非公開」にさせてください。
オケは前日のホール練習。スメタナ、チューバ、アンコール、エロイカの順に練習をしました。今日は早く寝ます。
2007年7月7日(土)
今日は尊敬する大作曲家、グスタフ・マーラーの誕生日。そして、エロイカの本番1週間前です。残された時間で、どこまで課題をクリアできるか。問題点を挙げて結果を記します。
第1楽章
①15小節目からのEs-durの響きは? → △
②付点四分音符+八分音符のパターンのリズムは正確か? → ○
③194小節目からの八分音符の動き、チェロ・ベースとの対話はできているか? → ○
④330小節目からのメロディ、音程がぶら下がっていないか? → △
第2楽章
①45小節目の第3オクターヴのG音、勇気をもって弱音で、かつ芯のある音がでているか?→ △
第3楽章
①40小節目からのメロディ、大きなフレーズを感じながら吹いているか? → △
②206小節目からのFl+Ob+Fgのメロディに滑らかさがあるか? → ××
第4楽章
①20小節目からの八分音符の動き、Fl+Cl+Fgの響きのバランスは良いか? → ×
②174小節目(練習番号B)からのメロディ、Fisの発音の時に体の力が抜けているか? → △
③183小節目からの八分音符の動き、テンポをしっかりキープしているか? → ◎
④257小節目からのメロディ、十分な時間をかけてC音の発音ができているか? → △
⑤420小節目からのFlとFgの音程は合っているか? → ×
初めて1曲通しましたが、今日のエロイカ、全体的に集中力が少し欠けているような気がしました。私自身も、必要以上に口元に力が入っていて、楽器をコントロールすることが難しかったですね。マエストロの指揮をする表情、完全に本番用でした。何が起こっても先へ進み、とにかくエロイカの世界に没頭しているように感じられました。時々、もうあの世(ベートーヴェンと同じ世界)にいってしまっているのではという表情をされることがあり、面白かった!
第1楽章①の響き、もっとできるはず。もっといい響きを得られるポイントがあるはずです。まだ2回練習できるチャンスがありますので、そこで最後まで探っていきます。②は師匠に練習方法を教えていただいたところです。Ob→Cl→Fl→Vnのメロディのつなぎを、すべてフルートで吹けるようにする。そうすることで全体の流れを理解し、部分的なフレーズもどう吹いたら良いのかが理解できる、というもの。これは大いに役に立ちました。師匠に感謝です。
第3楽章の②、今日一番できの悪かったところかな、と思いました。該当する楽器としては、ため息をついてしまいます・・・。
第4楽章①は、今まであまり気にならなかったのですが、よーく耳をすませてみると響きが良くない。あれ、今までこんなに響きが悪かったかな、と面食らってしまって、その場では何もできませんでした。修正箇所が一つ増えました。②と③、口元に力が入っていたため、やはり第3オクターヴのFis音が発音できませんでした。八分音符の動きになってからは、先週の練習で先へ走ってしまっていましたので、今日はしっかりとテンポのキープを意識。意識をしっかりもてば、きちんとできるようになります。
いろいろ課題が山積みですが、本番まであと1週間。まだ練習する時間はあります。
2007年7月1日(日)
日曜日の特別練習。アンコールを含め、全ての曲を練習しました。
まずは、エロイカから。マエストロのアドヴァイスで、1つ1つの音が、ベートーヴェンに相応しい音に変わっていきます。第1楽章だけで、1時間20分を費やしました。マエストロのこの曲に対する想い入れの強さを感じずにはいられません。個人的には、この曲の練習が始まって以来、一番調子が良かったと思います。口だけでなく体全体が適度な脱力状態で、できるだけ良い音で十分に響かせる準備ができていました。といっても、全てがうまくいったわけではありません。15小節目からのEs-durの響き、もうちょっと良くなると思うんだけどなあ。後は、各楽器同士の対話があると、もうワンランクアップするかな、という感じです。
第2楽章、フルートは休みが多いので、他の楽器の活躍を楽しむことができる楽章です。今日楽しんだのは、160小節目からの弦楽器の動き。フォルテシモの三連符の弾き方、試しで全てダウンで弾いてみせてくれたのは、良かったですね。なんと恐ろしいサウンドが生まれるのでしょう!弓の使い方一つで、全く違った雰囲気の音楽になってしまいます。本番は・・・・、この弾き方ではないようですが、私はオール・ダウンでも面白い、と思いました。でもそうすることで、会場に聴きに来てくれた小さなお子さんが、あまりの恐ろしい音楽に泣き出してしまうのも困るし。オーソドックスな弾き方が無難なのでしょうか。久しぶりの第3楽章は、ちょっと落ち着きがなかったかな。しっかりテンポをキープすることを意識できれば、もう少しまとまると思います。
第4楽章は、時間が足りず、ほとんど止まらずに最後までいきました。この楽章でも、適度な脱力状態でなければ良い演奏ができない場面があります。練習番号Bからのフルート・ソロです。もっと細かくいうと、出だしの第3オクターヴのFisの音です。フルートを吹いている方の大半は感じていると思いますが、この音はとても吹き難い。なかなか綺麗にきまりません。でも、余分な力が抜けている状態だと、すっ、と綺麗に響くことがあります。もし、力が入りすぎて、Fisの音を外そうものなら、その先のメロディを気持ち良く吹く事は、困難です。今日は、珍しくFisの音が綺麗に響いたと思います。初めのほうにも書いたとおり、適度な脱力状態だったのでしょう。
次はチューバ協奏曲なので、私は降り番。ソリスト付きで練習が行われましたが、もうかなりまとまっているように思えます。特に大きな問題もなさそうだし、んー、どうなのでしょう。半音くらい間違えても分からないような箇所もたくさんあるようですが・・・。演奏している人は、どう感じているのかなあ?続いて、スメタナのボヘミア。昨日試した53小節目から69小節目にかけてのちょっとした見せ場。今日は、周りの音も十分に聞きながらアンサンブルができたと思います。あとは、場面場面のキャラクターをいかに感じ、いかに表現するか、でしょう。最後は、アンコール。笛が少し目立つ場面がある・・・。エロイカだけでなく、こちらの練習もしなくては。
盛りだくさんの一日でしたが、練習後はとても気持ちよく、帰ることができました。
2007年6月30日(土)
スメタナのボヘミアから練習を開始。実はこの曲、前半にフルートのちょっとした見せ場があります。53小節目から69小節目にかけてですが、主役は他の楽器で、その楽器にきらびやかにまとわりつくのが2本の笛、という場面です。今まではあえて二人一緒にブレスをとっていたのですが、今日はブレスの位置をずらして吹いてみました。いつもの感覚と違いましたので多少抵抗がありましたが、これはこれで演奏の面白さを感じましたので、次回以降もこの吹き方にしてみようと思います。練習番号のBからは、いつも弦楽器が難しそうに、そして個々人がかなり自由に演奏しているように聞えたのですが、今日は揃っていましたね!先週、特訓をしたのでしょうか。この曲の難所の一つだと思っていましたので、今日で一段階、ステップアップしたと感じました。
後半はエロイカ。先週に続いて、楽器の響きを注意してみました。改めて、ブレスのタイミングと十分な楽器の響きは密接な関係にあると思いました。ただ、このことに注意しすぎて、肝心のアンサンブルに注意がいかなかったところが何ヶ所か・・・。これでは意味がありませんので、直していかないと。最後に、アンコールの練習をしました。
明日は、日曜日の特別練習です。
2007年6月23日(土)
管楽器の分奏です。前半はエロイカの第1楽章。3ヶ月以上練習をしてきているのですが、まだまだ仕上がるまでにはたくさんやることがあります。基本にもどり、音程・リズム・フレーズの確認。15小節目からのEs-durの大事なメロディー、音程や響きを何度も調整してきたつもりですが、まだ修正するところが見つかりました。ただ、考え方の方向性は間違っていないかな、と思っています。
今日意識した点は、楽器を十分に響かす、ということです。曲全体も少しずつ分かってきて、個々のフレーズの気をつける点も1つずつ修正。それを十分に客席に伝えるためにも、楽器の響きも意識をしないと。十分に楽器を響かせるには、どうしたらよいか。たっぷり息を吸って、その息を十分に使うことでしょう。ブレスのとり方が、とても大切になってきます。このブレスのとり方・大切さを私に教えてくれた音楽家がいます。元シカゴ交響楽団のトランペット奏者、アドルフ・ハーセス氏です。
ショルティ指揮シカゴ響の(1990年?)サントリーホール公演。曲は展覧会の絵。もちろん、テレビで見ました。第6曲「サミュエル・ゴールデンベルクとシュミュイレ」のピッコロ・トランペットの演奏があまりにも見事で、感動した覚えがあります。輝かしい響き、目を見張るテクニック。そのソロの間、ずっとハーセス翁がアップで写っていたのですが、フレーズとフレーズとの間で、タップリと息を、しかも「十分な時間をかけて」吸っていたのがとても印象に残りました。ああ、これがあのすばらしい音につながるのか・・・。この演奏を聴くまで、ここの音楽はとても忙しく、ブレスをとる時間がほとんどないと私は思っていたのですが、大きな間違いであることに気がつきました。あれだけ十分に時間をかけてブレスをとっているのに、音楽が全く崩れていない。ブレスは音楽の流れを断ち切るものではなく、聴いている人が感動するような音楽をつくるために必要なものなんだ、という認識に変わりました。
後半は、スメタナのボヘミアです。この曲は、場面場面のキャラクターをいかにつかんで、いかに表現するかにかかっていると思います。例えば、流れるようなメロディーから急にポルカのリズムになった時、このポルカを意識するだけで、自然とテンポが落ち着いて、その場面にふさわしい音楽が生まれます。でも、ポルカの意識がないと単に音が通過しているだけで、演奏する人だけでなく聴いている人も??な音楽になってしまいます。今までの練習を振り返ると、そういう演奏をしていたかも。意識すること、イメージすることの大切さを認識した練習でした。
2007年6月16日(土)
今日は盛りだくさんです。午後、3月以来久しぶりに笛のレッスンを受けてきました。開始時間よりかなり早くついてしまったので、色々なタイプの頭部管を試奏させてもらいました。管体が銀で、リッププレートだけ違う材質のもの。リップが銀、18金、プラチナ。カットのタイプは標準的なものと、アンダーカットが全くないものがありました。今日吹いた第一印象では、リップ18金のアンダーカットなしの頭部管が、インパクトがありましたね。でも、実際ホールで演奏するときには、アンダーカットのない頭部管を使うには、勇気がいるだろうなあ。標準的な頭部管より吹き込む「感触」が味わえないので、楽器が鳴っている「感触」が少ないんですよ。音はとてもいいと思うのですが。さて、今日のレッスン曲は以下の4曲です。
①T.ベーム:24のカプリスNo.1
②T.ベーム:24のカプリスNo.2
③「歌の翼」による幻想曲
④ベートーヴェン:「エロイカ」より抜粋
①は前回やり直しの曲。吹き終わるなり師匠が、「まあ、こんなものでしょう」と一言。自分自身が、どんなに時間をかけて練習してもこれ以上吹けません、という気持ちになっていたので、演奏がそれに出てしまったのでしょう・・・。②は、①と比べてそれほど技術的に難しくはありませんが、曲の重要なポイントになる低音域の扱い方が×。でも、これは意識をすることで、解決しました。
解決しなかったのは③の歌の翼。何が問題か。曲が変わっても指摘されることは毎回同じです。音楽を大きくとらえる事ができず、細切れになってしまう。今日はそれに加えて、細かい音への丁寧さが欠けているとの指摘。音楽を大きくとらえるのって、歌心の問題ですよね?おそらく普通に歌心を持っている人であれば、フルートでもヴァイオリンでも何の楽器であれ、この曲はそれらしく演奏できるはず。音楽の「感じ方」も教わらないとこの曲が普通に演奏できないというのは、かなりの重症だなあ。どんな薬が効くのか、ドクターも悩んでしまうのでは。そのそも、そういうものって教わるものなのだろうか。でも実際それができていなのですから、「後付け」でも身につけていくしか、方法はないですね。④は、エロイカの練習方法や場面ごとの替え指のアドヴァイスを教えていただきました。これは長年オケで演奏されている百戦錬磨の師匠ならではのものでした。後は、どのくらいそれらを自分のものとして消化できるかです。
夜はオケのマエストロ練習です。前半はエロイカの第4楽章と第2楽章。んー、練習中は体が力んでしてしまい、自分が何をやろうとしているのか、全く訳が分からなくなっていましたね。キーを必要以上の力で押さえ、リッププレートを口に力強く押しつける。楽器にしがみついているような感覚でした。事前に十分な音だしをしていて、準備はしっかりしていたはずですが。マエストロが本気でベートーヴェンの世界を築こうと熱血指導をしているのに、それに反応することができずに第4楽章の練習が終わってしまいました。せっかく数時間前に師匠に教わった替え指を使う場面があったのに、それを1度も使うことができず。今日は演奏会本番ではありません。まだ、1ヶ月練習できます。
後半は、ソリストを迎えてチューバ協奏曲を練習しました(上の写真2枚)。なかなかの好青年で、しかも私より11歳若いソリスト・・・。このくらい若い人も、ソリストデビューしてもおかしくない年なのかあ。オケの世界を見てみても、私と同学年ですでに確固たる地位を築いている人もいますね。シカゴ響の主席フルートのデュフォー、ベルリンフィルの主席ティンパニのヴェルツェル。サッカー界では、フランスのジダンやポルトガルのフィーゴ、など・・・。このくらいで止めておきます。
降り番でしたので、しばらく聴いていました。出だしから豊かな音色。速いパッセージも、チューバとは思えないくらいコンパクトに演奏されていました。全楽章を聴きましたが、こんなに短い曲だったっけ?、と思ってしまいました。演奏される機会の少ない曲ですので、本番が楽しみです。私もステージ裏で聴いていることでしょう。
2007年6月9日(土)
遅れて合奏に参加。1曲目は、スメタナのボヘミアです。先週の日記に書きましたが、なかなか曲の雰囲気を感じ取ることができません。今日の合奏で感じましたが、これは私だけではなさそう・・・。オケ全体も苦労しているようです。練習番号Gからの音楽、笛はメロディーですが(かなり吹きにくい!)、その裏の伴奏は本当に難しそうです。それこそ、酒場で酔っ払った田舎の人をイメージしないと、この音楽のキャラクターは生まれないですね。
そう、音楽のキャラクターです!いい音を出す練習、スケールの練習はもちろん必要ですが、その場にふさわしい音楽をつくり出すには、やはりキャラクターをイメージしないといけないと思います。ベートーヴェンとスメタナでは、まるで違う音楽ですからね。今日の練習では、このキャラクターづくりに時間を割きましたので、これからいい方向に音楽が進んでくれることを願います。sfやsff、アクセント、メロディ途中のタンギングし直し等々。この曲、一つ一つ音符を見ていくと、気が狂いそうになります。
後半は、チューバ協奏曲。降り番ですので、今日の私は前半で終了。遅れて会場に到着し、帰りも他の人より早く帰る。楽器を組み立ててすぐにステージに上がったため、楽器が温まる前に練習が終わってしまいました。ああ、吹き足りない・・・。
2007年6月2日(土)
マエストロ練習です。やっぱりベートーヴェンは偉大な作曲家です。エロイカの練習中、ずっと感じていました。今日はマエストロの口から、世界一の演奏をめざす、とのお言葉が。これだけ一つ一つの音にマエストロもオーケストラも魂を込めて練習をしたら、いやいや、可能性はゼロではないと思いますよ。おそらく、2001年のラ○ル+ウ○ー○フ○ルの???なベートーヴェンより、森口ベートーヴェンの方が、きっといい演奏になるでしょう。本当は、エロイカの練習のことをすぐにでも書きたいのですが、練習曲順に書いていきます。
チューバ協奏曲から。本来私は降り番ですが、今日は演奏に参加しました。演奏をする機会があるのは、うれしいものです。実際に演奏をしてみて、なんとも不思議な曲に感じました。東洋と西洋が混ざっているような、難易度も高いのかそうでもないのか・・・、よく分かりませんでした。テクニック的には、多少練習を要するところ(写真左は第3楽章の楽譜)はあります。しかし、ベートーヴェンに比べれば精神的には気楽です。
2曲目は、スメタナ。ベートーヴェンと違って、なかなか素直に曲に入り込めません。曲の持つ土臭さやスメタナ独特の雰囲気に、どうしても距離を感じてしまいます。土臭さ、かといって普段洗練された吹き方をしているわけでもないのですが、このスメタナの土臭さはなんとも言えません。今週練習でこれを表現しようとしても、来週には忘れて元に戻っているかもしれません。演奏会本番まで、あと1ヵ月半。早くきっかけをつかみたいものです。
3曲目は、エロイカの第1楽章。今日もマエストロの世界に引き込まれてしまいました。出だしからサウンドが変わったような気がいたします。押し付けていたようなフォルテから、十分な響きを伴うフォルテへ。そして3小節目からの刻みも、マエストロのアドバイスで安心して聴ける刻みに変わりましたね。エロイカ、マエストロのアドバイスで、毎回進化していると思います。個人的には、今日は2つの課題をもって合奏に参加をしました。
一つ目は、音域による音程のバラつきの修正。結局、新しい吹き方をベースに、笛の高音域のときに周りとのアンサンブルに気を使うところは以前の吹き方をする。この2つの方法を併用することでうまくいくような気がいたします。しばらく、このやり方を使っていこうかな。2つ目は、この楽章でたくさん出てくる付点四分音符+八分音符のパターンです。1番フルートでは、この楽章だけで、ちょうど30回出てきます。そんなにたくさん出てくるのに、苦手意識を持ったままではちょっとまずい。気がついたのは、1拍目に休符がある場合とない場合では、私の意識が変わってしまっていることです。例えば練習番号Dの5小節目からのパターンでは、問題なく演奏可能。ところが、練習番号Aからのように1拍目に休符がある場合では、リズムに正確さが欠けてしまっているんですね。休符も音楽の1つです。もう一度楽譜を読み直さないと・・・。
655小節目からの木管の動き(写真右上、手書きで655の文字あり)に少し楽譜の変更が。どう変わったかは、本番までのお楽しみということで、ここではまだ伏せておきます。書きたいことは他にも山ほどあるのですが、まとまらなくなってきましたので、この辺で止めます。1つだけ申し上げたいことは、7月15日の演奏会当日は、何か特別なベートーヴェンになるような気がいたします。
2007年5月26日(土)
色々個人的な問題を抱えているベートーヴェン。先週の分奏から一週間、第4楽章のある部分をずっと眺めていました。それは練習番号B、そしてDからの、付点四分音符+八分音符のパターンです。それほど難しい音楽ではないはずですが、これまで一度も納得することなく、演奏をしていました。どうしたら、音楽的に演奏できるのだろうか。スラーを外してみたり、八分音符で刻んでみたり、別な角度から眺めていました。すると、今まで感じなかったフレーズのラインを発見!これで何とかいけるかもしれない。スラーに気をとられていて、短い八分音符を疎かにしていたのが原因でした。
今日は合奏です。諸事情により、遅れて参加。前半はチューバ協奏曲、後半はエロイカです。エロイカ、第1楽章の出だしからつまづいてしまいました。15小節目からのメロディ、どうしても笛がピッチを他の楽器と比べて高めにとってしまうのです。4月下旬から頭部管の向きを微妙に変えているのですが、それが影響しているかもしれません。アンサンブルの重要なところだけでも、以前の吹き方に戻そうかなあ。これが、今日の問題点の1つ。問題点の2つめは、練習番号Aからの付点四分音符+八分音符のフレーズのパターン。木管楽器で繋いでいきますが、くいつきが遅く、また笛だけ付点四分が伸びてしまっているようです。これも第4楽章と同じように、これから別な角度から眺め続けていきたいと思います。何か新しい発見があるかもしれません。
第3楽章の後、アタッカで第4楽章へ突入。この一週間眺め続けた成果を、合奏で試すチャンスです。練習番号のB。ピッチが上ずらないように気をつけて、八分音符を意識する・・・。結果は、明らかに今までとは違う感覚で演奏することができたと思います。少なくとも演奏者の感覚としては、良い方向にいっていると感じました。
繰り返して演奏しているはずなのに、3ヶ月練習してようやくポイントをつかむ。もっと早く気がつけよ!、と言われそうですが、私もその通りだと思います。早く気がつけば、その次からはまた新しいレベルで合奏ができますからね。
2007年5月19日(土)
管楽器の分奏です。2ヵ月半合奏をしてきましたので、曲の全体像はそろそろつかめてきたはず(?)です。アンサンブルも、慣れてきたはず(?)です。最初は曲の全体を理解し、今度は細かく見ていく。それから再度曲全体に戻る。良い練習計画だと思います。今のうちに修正が必要な箇所を出しつくして、次回以降の合奏につなげていきたいと思います。今日は、予定通り「要修正」箇所は出てきましたが、その数が余りにも多く、収拾がつきませんでした。ここに書ききれませんので、個々の問題点はこれからじっくり、一つ一つつぶしていくことにいたします。
約1ヶ月前、私が使っている楽器について熟知されている方から、頭部管の挿し具合と向きについて、アドバイスをいただきました。この楽器は、この向きとこの挿し具合でベストになるようつくられている、というもの。それは、私が今まで吹いていたものとは大きく異なるものでした。すぐにその吹き方を始めるか、7月の演奏会が終わってから始めるのか迷いましたが、少し自分にプレッシャーをかけようと思い、すぐに始めることにしました。自分自身でも違和感があるのですから、アンサンブルとなったらさらに気を使わなくてはならない・・・。しばらくは我慢我慢。長い目で見れば、今やっていることはプラスになるはずですから。
シンフォニーで1番を吹くことの難しさを感じた1日でした。
2007年5月12日(土)
今日は、珍しくエロイカの練習がありません。前半はチューバ協奏曲、後半はスメタナのボヘミアです。
客席で、フルートのパート譜を見ながら聴いていました。なぜ、スコアを見ないのか。実は、このチューバ協奏曲と次のボヘミアは、今回スコアを入手しませんでした。ある楽譜店で、2曲ともスコアを手にしたのですが、あまりの印刷の汚さに購入を断念したのです。2曲とも黄色が目印の、オ○レ○ブ○グ社のスコアです。よーく見ないと「A音」なのか「H音」なのか、分からないところもあります。これが、売り物なんですかね。こんな汚い楽譜でも、この会社には版権だか何だかの権利があって、複写禁止なんて言うんだろうね。でも、こんな楽譜、コピーをする気にはなれません。最近の日本の出版社のスコアは、本当にきれいです。オイレンブルグ(もう伏字はしません)を見ていると、日本製のスコアは、美しささえ感じます。
ちょっと脱線してしまいましたが、今日は代ソロつきで練習が進みました。チューバソロ、難しそう・・・。オーケストラの中では、低音域で全体を包み込む役割を担っていますが、この曲では高音域が多く使われているようです。そうですね、小回りの利かないはず大きな象が、訓練によって色々な細かい芸ができるようになった、そんなイメージを持ちました。オーケストラも普段あまり演奏しない雰囲気の曲ですので、少し難しそうです。でも、部分的に取り上げて繰り返して練習したところは、確実に良くなっています。根気よく、繰り返して練習。これしかありません。
後半はボヘミア。スメタナの神経質な楽譜の書き方を忠実に守ることが、スメタナの雰囲気を出す方法であることは、今までの練習を通じて理解しました。でも、それを意識しても、ひまひとつスメタナの音楽に入り込めないでいます。演奏をしても、体力的な疲れを感じてしまいます。まだ、自分の中でチェコの音楽が、十分に理解できていないのでしょう。愛聴盤(写真右上)は、スメターチェク指揮のチェコフィル、1980年の録音です。同じチェコフィルの演奏でも、クーベリックはNHKでテレビ放送されているのを見たし、ノイマンはおそらく聴いていると思ったので、スメターチェクを入手しました。このCDだけでなく、チェコの民族の雰囲気が分かるものを、少しずつ聴いていきたいと思います。
2007年5月5日(土)
前半は、ヴォーン・ウィリアムズのチューバ協奏曲の譜読み。私は降り番なので、客席で聴いていました。
まずは、私の愛聴盤ですが、左上のナクソスのCDです。本当は元シカゴ交響楽団のチューバ奏者、A.ジェイコブズが演奏するCDがほしかったのですが、店頭には置いてなく断念。お店には、この他にコリン・デイヴィス指揮のものがありました。これはヴォーン・ウィリアムズ交響曲全集の中の1曲でしたので、CDが複数枚セットのもの。今回はチューバ協奏曲だけが目的ですので、こちらも購入しませんでした。この曲をきちんと聴くのは初めてでしたが、なんともユニークな曲です。イギリスの曲ですが、東洋的な響きがします。
さて、譜読み。細かい音符や臨時記号がとても多い曲で大変そうですが、皆さんそれぞれきちんと譜読みをしてきているな、と思いました。管は指使い、弦は左手のポジションが怪しいところは多々ありましたが、想像していたより曲の形はできていたと思います。半音間違えても、合っているのか間違えているのかが分からない箇所もあるにはあるのですが・・・。
休憩後は、エロイカの第1楽章。ここからは、私の出番です。今日は、んー、今一歩でしたね。チューニングしても、出だしの音からきれいに響かない。立て直そうと、合奏中に色々調整をしてみたのですが、しっくりいきませんでした。半ばあきらめていたのですが、時間が経つにつれて少しずつ距離が縮まってきたように感じました。きっと、周りが見るに見かねて、笛に合わせてくれたのでしょう。感謝いたします。
今日の私の問題点は、またまた事前準備です。メロディが1拍目から始まる場合、2拍目から始まる場合、そして3拍目から始まる場合、それぞれタイミングのとり方があります。もちろん、そんなこと考えずにきちんと自然に演奏ができれば、それに越したことはないのですが。場所によっては、どこでブレスをとるかを意識することで、メロディが吹けるようになったところもあります。でも、大事なメロディを演奏する前に身構えてしまい、出るタイミングが微妙に遅れてしまうところが、他にもあるんだよな・・・。次回の練習までに1つ1つ洗い出して、合奏の中でそれがきちんとできるかどうか、見ていきたいと思います。
2007年4月28日(土)
先週の練習について。エロイカの第1楽章しか書かなかったのですが、実際は第3楽章、第4楽章の前半、そしてボヘミアも合奏が行われました。ついマエストロのベートーヴェンの世界に酔いしれてしまい、練習した曲を書き損ねてしまいました。
さて、今週も先週に引き続き、2回目のマエストロ練習です。今日も緊張感と楽しさが味わえる、良い練習でした。エロイカ、本当に素晴らしい曲!まずは第4楽章。
フルートとして目立つのは練習番号Bから(写真左)。ヴァイオリンと一緒にメロディを奏で、そのメロディが八分音符になり、最後は十六分音符の動きになります。オケスタにも出てくる有名なところ。写真では写っていませんが、この十六分音符の動き、当初ゆっくりなテンポではシングルタンギングで、速いテンポならダブルタンギングをするつもりでした。が、どんなテンポでもダブルタンギングで対処するほうが、7月までの練習期間中、安定した演奏ができるのではないかな、と思うようになりました。今日も、テンポは練習用の遅めでしたが、ダブルで演奏しました。本番はダブルで演奏するつもりでしたので、今のうちからダブル一本にしてしまおうと思います。それよりも、十六分音符の前の八分音符の動き、どうしてもフルートが走ってしまいます。今日は、こちらの方が問題でした。
もう一つ、この楽章で大きな発見がありました。練習番号Fからのメロディです(写真右)。ここの楽器編成はよーくスコアを見てみると、クラリネット2本、ファゴット2本、ホルン1本(!)、チェロ、コントラバスです。マエストロは、木管楽器がきちんと聞えるように要求をしました。そうして生まれた音楽は、私にとってはとても新鮮な音楽に感じられました。なぜって、普段私が聴いているCDは、バーンスタイン&ウィーンフィル。このCDでは、ウィンナホルン独特の割れた音が、全てを包み込んでいますからね。ホルンが1本だったなんて、今日初めて知りました。てっきりベートーヴェンは3本全員で吹くように書いているかと・・・。バーンスタイン好きの私ですが、ここは新鮮な音楽を教えてくれた、マエストロ森口に1票を入れたいと思います。
第2楽章、葬送行進曲ですが、少し早めのテンポで音楽が停滞することなく、進んでいきました。その後は、スメタナのボヘミア。なんでこんな書き方をするの、と思うところもありますが、それがスメタナ。とにかく、楽譜に忠実にいきましょう。
2007年4月21日(土)
初のマエストロ練習。心地よい疲れと幸福感さえも感じる、とても充実した合奏でした。作曲家やその作品と真剣勝負することが、こんなにも楽しいものだとは・・・。改めて、楽譜を丁寧に読み込むことが、いい演奏につながる事を実感しました。マエストロが前回登場したときは、ストラヴィンスキーのペトルーシュカとベートーヴェンの2番。その時は私はベートーヴェンは降り番でした。今日マエストロの合奏に参加してみて、前回ベト2にのった人は、こんなに良いおもいをしていたのか、と感じました。今回は、私も良いおもいをさせていただきます。
第1楽章。初回の練習ですが、曲をただ流すことはせず、細かく止めてマエストロの目指すベートーヴェン像を熱血指導です。今回の演奏会では、今流行のピリオド奏法ではなく、モダン楽器の性能をフルに生かした伝統的な奏法をとります。これについては、色々な意見はあるとは思いますが、私は大賛成。というのは、ここ数年ベートーヴェンの演奏会を聴きに行ったときに、たまたまではあるのですが、モダン奏法の演奏会の方がとても印象が良かったのです。具体的に挙げてしまうと、ヤンソンス&コンセルトヘボウのベト2とラトル&ウィーンフィルのベト4・ベト7。前者がモダンで、後者がモダン楽器によるピリオドアプローチの演奏でした。ここでは、詳しくは書きませんが、クリックしていただくと、その時の感想をご覧いただけます。
じっくり落ち着いたテンポで、一つ一つの音に魂を込めるように。ずっとピアノの音楽だったのが、この小節、この瞬間からいきなりフォルテの音楽になる・・・。この1つの楽章を演奏するだけで、神経が磨り減ってしまいます。ベートーヴェンは、われわれ凡人には到底思いつかない発想で、作曲をしているのでしょう。演奏をしていて、なぜこんなところでこんなことを要求すんだろう、と思うところが多々あります。いきなりその瞬間に強弱の変化を要求されても・・・、もう数小節猶予を下さい!、と思いたくなるところが沢山あるのです。でも、それをきちんと楽譜どおり音にすると、あのベートーヴェンらしさが出てきますね。ベートーヴェンもさすがですが、そのスコアからベートーヴェンの意図を読み取って演奏者に的確に指示をするマエストロも、非凡な才能を持った方だなあ、と感じました。
今回のベートーヴェンは、こんな感じていく、というベクトルが示されました。7月の演奏会まで、一つ一つの音を徹底的に追求して、はたしてどこまでベートーヴェンらしさを描けるか、楽しみになってきました。
2007年4月14日(土)
前回までの練習を振り返ってみる事にしました。私の演奏は、もう少し音と音のつながりを意識したほうが良いのかなあ。客観的に聞いてみると、一つ一つの音楽に丁寧さが足りないように感じました。そのあたりを意識して、今日の練習です。
まずは、エロイカの第4楽章。練習を重ねるごとに難しさを感じる、ベートーヴェン。3月にこの練習が始まって以来、今日は初めてプレッシャーを感じていました。気持ちが小さくなっていましたね。ちょうど初めてシンフォニーの1番フルートを演奏した時の感覚に、似ていました。先週と違って準備はきちんとしていたつもりですが・・・。ヤバイところは多々あるのですが、まずはリラックスをした状態、脱力した状態で自然に演奏することから、自分の演奏を見直してみます。冒頭に書いた「音と音のつながり~」は、ちょっと今日はゴメン、また次回・・・。本番は、7月です。全体の合奏では、アンサンブルのポイントを指摘されることが多いように感じました。自分がこのメロディを演奏しているとき、他のパートではこんなことをやっています、というように。初めて聞くような音もあり、まだまだ周りの音を十分に聴く余裕がなく、自分のことで精一杯の状態なんだな、と感じました。
後半は、スメタナのボヘミア。この曲、とても吹きづらい!音符の並び方は、他のヨーロッパの国々のメロディと大きな差はないと思うのですが、アーティキレーションの違いが大きいのかな。どうしてメロディの途中(と私には感じる)でスラーが途切れて、タンギングし直すのかなあ、なんて思うところもあります。そういうところが、スメタナ独特の音楽をつくっているのかもしれません。それにしても、体力的にきつい曲ですね。「我が祖国」は、こんな曲が6曲セットになっています。今回演奏する「ボヘミア」は4曲目、有名な「モルダウ」は2曲目です。全曲やると、演奏会は「我が祖国」だけになってしまうでしょう。そういう機会は、おそらくないと思いますが。もし全曲演奏することになったら、第九より体力的にきついかもしれません。
2007年4月7日(土)
音楽を演奏するにあたって、つくづく準備の大切さを感じた日になりました。合奏に参加するための準備、一つのメロディを吹くための事前準備、その他いろいろな準備・・・。今日は、スメタナのボヘミアの譜読みから練習が始まりました。で、私はというと、振り下ろし時間より大幅に遅れて会場入り。到着次第、その場で楽器を組み立てて、すぐに合奏に参加です。スタートから、準備不足を露呈してしまいました。
合奏をしていると、いろいろなことを感覚で感じることがあります。音程や、アンサンブルをしているときの”一体感”、などがそうです。例えば音程。初めから100%ドンぴしゃり音程がそろうというのは、なかなか難しいもの。その時々の各々の調子を感じあいながら、合奏中に少しずつ修正していきます。寄り添っていく、という言い方が正しいかもしれません。もちろん、そこには修正がきく許容範囲があります。この範囲内にないと、その日は修正できずに終わってしまうこともありますね。音程も含めて、もっと大きな意味で寄り添っていけると、オーケストラ全体で一体感が生まれるのだと思います。そのためには、個人の事前準備が必要なのです。
今日は、私は事前準備が完全に不足していました。合奏中の修正もなかなかきかず、もちろん私自身が一体感を感じるはずもありません。今日が演奏会当日でなくて良かった、ということにしておきましょう。
さて、合奏。まずは先ほどのボヘミア、第2曲「モルダウ」と似たような印象です。やはり同じ我が祖国なんだなあ、と感じました。フォルテの吹きっぱなしで、体力が必要。それから、民族的なニュアンスを出すのも、少し工夫が必要です。譜読みの段階ですから、こんなところでしょうか。後半は、ベートーヴェンの第1楽章を中心に練習。今日は、私自身がアンサンブルをしている感覚がなかったことはとても残念なことですが、個人レベルでの発見はいくつかありました。三拍目からメロディが始まる場合の呼吸のとり方、これは今日唯一といっていい収穫です。ああ、こうすればいいのかあ、という感覚でしたね。これも、実際に音を出す前の準備の仕方で、解決しました。後は、問題点の発見ばかりですね。木管のメロディの掛け合い、つまり練習番号Aや2番括弧の後、などがそれです。何気ないメロディですが、まだまだ自然な音楽にきこえません。シンプルなメロディほど、難しい。
2007年3月31日(土)
1週間お休みの後の合奏です。今日は、後半の2つの楽章、第3・第4楽章の練習でした。前半は、第4楽章を練習。管楽器も弦楽器も、大変な楽章のようです。まずは、交通整理が必要ですね。この練習で気がついたことを挙げていきます。
①練習番号Bから音楽の流れが停滞している。
②同じところの続きで、191小節目からの動きを注意。(写真左上)
③426小節目からの強弱とフレーズの感じ方。
①はきれいなメロディなので、ついたっぷり歌いすぎてしまうことが原因。ここは、僕が音楽を止めてしまっていたんだろうなあ。今からその癖を直します。②はオケスタにも出てくる、エロイカのフルートといえばここ、というソロです。通常の演奏のテンポで行けば、ダブルタンギングで演奏する箇所ですね。私も、ダブルを使うことを想定して、準備をしています。しかし、現在の練習ではテンポを少し落としているため、シングルタンギングで間に合ってしまいます。今日は最初はダブルで、もう一度通したときにはシングルで吹いてみました。しばらくは、どちらのタンギングでも演奏できるようにしておく必要があります。③は、弦とフルート+ファゴットの音楽。長いフレーズですので、大きく大きく音楽を捉えなければなりません。こういうところは、まさに私の弱点です。フレーズの感じ方が×。どの曲を吹いても、師匠に毎回のように指摘されている・・・。
続いて、第3楽章です。1つ振り三拍子のスケルツォの楽章。第九の第2楽章と同じ雰囲気ですね。この楽章は、特にアンテナを張って機敏な動作を心がける必要があります。ここの楽章で気がついたことは、以下の点です。
①39小節目・298小節目からのソロ、八分音符の動きが変。(写真右上、中段)
②206小節目からのメロディ、フレーズ等の音楽の感じ方が×。
①は指使いがちょっと難しい。しばらくは、指がスムーズに動くような矯正練習をする必要があります。②は当初は、何も考えずにのっぺらぼうのように吹くのがいいのかな、と思っていましたが、やはりそれはおかしい。滑らかさは残しつつも、どこの音を意識するのか、どこに音楽を持っていくのかを考えなければなりません。
ベートーヴェン、一瞬たりとも気が抜けません。
2007年3月24日(土)
今日の練習では、私の出番がありませんので、お休み。少しだけ、エロイカのCDの事を書こうと思います。
私の愛聴盤は、バーンスタイン指揮ウィーンフィルの78年ライブ録音(写真左)です。このCDをいつ入手したかは、よく覚えていません。バーンスタインであればOK、という時期もありましたので、おそらくその時に購入したのだと思います。はじける、そして躍動するベートーヴェンですね。素晴らしい!それにしても、バーンスタインは不思議な魅力を持った音楽家だと思います。もともと好きな作曲家(例:マーラー)はバーンスタインの指揮でさらに好きになり、それまで苦手だった作曲家(例:シューマンの交響曲)は彼の指揮で作品の面白さが見えてきました。バーンスタインは、私にとって特別な指揮者の一人です。でもですね、もし「カラヤンとバーンスタイン、貴方がどちらか一方になれるとしたら?」という質問があったとします。私の答えは・・・・、カラヤンですね。やはりあの目をつむって自在に自分の求める音楽を創造していく姿は、とても魅力的なのです。難しいなあ。
カラヤンの名前が出たついでに、もう少しだけ。借り物ですが、エロイカのCDをもう2枚、聴いてみました。マタチッチ指揮のチェコフィル(59年録音)とカラヤン指揮ベルリンフィル(62年録音)です。マタチッチのCDは録音が古く、演奏よりもそちらの方が気になってしまいました。一方のカラヤン、こういうベートーヴェンを聞くと、なぜか落ち着きます。聴き慣れたというか、ある意味でスタンダードというか。このCDで特に気になったのが、ここで演奏しているフルート奏者です。あの吹き方、そして録音の年から、カールハインツ・ツェラーでしょう。それでは、ご登場いただきましょう!

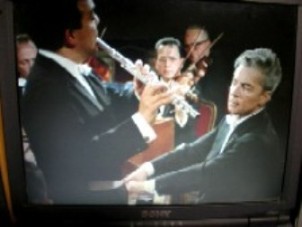
はい、ツェラーさんです。これは、私が持っているDVDを再生して、その画面を撮影いたしました。曲は、エロイカではなく、バッハの管弦楽組曲第2番です。カラヤンがチェンバロを弾き振りしています!このバッハも良いですが、先ほどのエロイカもスゴイです。ちょっと大き目のヴィブラートが気になりますが、何であんな存在感のあるいい音が出せるんだろう。少しは私に分けてほしい。一度ベルリンフィルを退団したツェラーを、カラヤンが連れ戻した気持ちがよく分かります。オーレル・ニコレ、アンドレアス・ブラウ、そしてカールハインツ・ツェラー。これが私の歴代のベルリンフィル笛吹き、ベスト3です。
2007年3月17日(土)
1週間お休みの後のベートーヴェンです。第1楽章と第2楽章を、たっぷり練習しました。
逆順で、第2楽章の葬送行進曲から。ここのテンポは、八分音符=80。でも、多くの演奏(録音)は、このテンポより遅いですね。今日は、できる限り楽譜に書いてあるテンポを守りながら、練習が進みました。まだまだ曲の難しさよりも、ベートーヴェンの交響曲を演奏できる楽しみのほうが、大きく感じられます。難しさを感じるのは、もう少し練習が進んで曲を少し理解できてから。来月、再来月くらいでしょうか。今日この楽章で気になったことは、どうも私の音は、この葬送行進曲にしては軽すぎるようです。もう少し、音に重みがつくよう、意識してみます。
後半は、第1楽章。第九同様、本当に体力と精神力の両方を必要とする楽章です。小節ごとにcresc.、fp、sf、sf、sf、fpが・・・。そして、その繰り返し。息を抜く暇を与えてくれないベートーヴェン。時々、メロディを吹くときに間延びしてしまう癖あり。要注意。
先週の練習日記に書きました、私の師匠からのプレゼント。明日の18日に、それについて書く予定です。
2007年3月10日(土)
弦楽器分奏の練習のため、管楽器はお休みでしたが、フルートのレッスンを受けてきました。今回は私にとってどれも難しく感じられる曲で、事前準備にとても時間がかかりました。
①C.J.アンデルセン:24のエチュードOp.21のNo.24(写真左)
②T.ベーム:24のカプリスOp.26のNo.1(写真右)
③W.A.モーツァルト:アンダンテK315
このアンデルセンの24曲目、時々入学試験にでるそうです。確かに指回しの難しい場面があり、かと思うと突然美しいメロディが現れたり。つまり、音楽の表現に必要なことが、この1曲に詰まっているのだと思います。師匠曰く、この1曲でその人の演奏家としての技量が分かる、とのこと。私はというと、う~ん、厳しいなあ。自分なりに音楽の流れを見つけてブレスの位置を考えたり、間違いやすい指使いをチェックしておいたつもりでしたが、演奏後はあまりいい感触ではありませんでした。でも、パスしました。きっと、演奏のミスはしても、音楽の流れは意識しているのが伝わったのでしょう。ここは強引に、プラスに考えることにします。今日でアンデルセンは、全て終了いたしました。エチュードを1冊終了するのは、本当に久しぶりです。昭和の時代に取り組んでいた、ケーラーの第2巻以来ですから、何年ぶりだろうか・・・。
そして新たに始まったのが、T.ベームのカプリスです。今我々が使っているフルートは、ベーム式フルートと言いますが、19世紀半ばにそのシステムのフルートを作ったのが、このテオバルド・ベームです。従来の楽器に比べてトーンホールを大きくして音量を増し、そのトーンホールを塞ぐためにキーシステムを考案することで、半音階の安定性と早い指回しを可能にしました。その楽器を念頭に作曲されたのが、この曲。まあ、大変です。今日の問題点は、ベースになる音と装飾的な音がまったく一緒になってしまっていること。つまり、指を回すことに気をとられてしまっていて、大事な音楽の流れが見えていないことです。もちろん、次回やり直しです。このベームのカプリス、難易度はどのくらいなのか、師匠に聞いてみました。大抵の受験生は取り組んでいて、既に終了している人もいるそうです。○京○術○学の笛課に入る人は、既に終了しているだろうね、とのこと。つまり、彼らにとって見れば、高校生レベルのエチュードなのでしょう。
もう1曲、モーツァルトのアンダンテです。この時代のアクセントの演奏の仕方、トリルの意味、カデンツァでの音楽の作り方、などなど。今までになく、ハイレベルなレッスンだったように感じました。こちらも、必死になって師匠のアドバイスを楽譜にメモ。演奏上色々改善点はありますが、吹きながら、まるで天から舞い降りてくるような、モーツァルトの美しいメロディに浸っていました。とても人間が創造した音楽とは思えません。
盛りだくさんの、そしてとても充実したレッスンでした。実は、レッスンが始まる前、師匠よりとてもうれしいプレゼントをいただきました。これについて書くととても長くなってしまうので、後日書くことにいたします。私がうれしいといっても、楽器をいただいたわけではありませんので、あしからず・・・。
2007年3月3日(土)
ベートーヴェンです。エロイカです。わくわくしますね。まずは、この曲が演奏できることに、感謝をしたいと思います。というのは、楽器編成の都合上、どうしても乗り番と降り番がでてくるからです。2003年のマエストロ森口による演奏会では、中プロでベートーヴェンの2番が演奏されましたが、私は降り番でした(メインのペトルーシュカは乗りましたが)。今回は是非ベートーヴェンを演奏したい、と思っていましたので、良かったです。7月の演奏会は、練習期間が約4ヶ月あり、年間の演奏会の中では最も長く練習時間をとれます。前回2月の演奏会のように1ヵ月半の突貫工事ではなく、じっくり1つ1つ積み上げていきたいと思います。
練習初日の今日、ベートーヴェンではなく、黙祷から始まりました。数日前に、長年ここのオケで活動されていた方が、亡くなられたのです。私も大変お世話になっていた方で、私が2年前まで使っていた楽器は、この方にかなり手を入れていただき、楽器屋さんではまず見かけることのない特別仕様の楽器になってしまいました。楽器全体の3分の1は買ったときと変わっており、この方の「作品」といってもいいくらいです。出棺の前夜に、棺の中の安らかな顔を拝見できたことが、せめてもの救いでした。ご冥福をお祈りいたします。
ベートーヴェン、本来なら第1楽章から通すところですが、黙祷のこともあり、第2楽章の葬送行進曲から練習が始まりました。そして、第1楽章、第3楽章、第4楽章の順に通しました。初めてエロイカを演奏してみて、う~ん、やっぱりベートーヴェン。作品から込み上げてくる力強さは他の作曲家とは比較にならないし、気を抜けるところが全くない。オーケストラでフルートを演奏していて、あらゆる意味で最も難しさを感じるのが、ベートーヴェンの第九です。エロイカも、第九を演奏する時と同じ気構えで臨む必要がある、と感じました。でもきっとその先には、シンフォニーのトップを吹ききったときの喜びが待っている、と思います。
これまでの特別企画
・⑳ショスタコーヴィチ:オラトリオ「森の歌」アマオケ練習日記
(2007年2月)
・⑲コダーイ「ハーリヤーノシュ」アマオケ練習日記
(2006年12月)
・⑱マーラー交響曲第2番「復活」アマオケ練習日記
(2006年7月)
・⑰歌劇「カルメン」&「バラの騎士」組曲
アマオケ練習日記
(2005年12月)
・⑯ツェムリンスキー交響詩「人魚姫」 アマオケ練習日記
(2005年7月)
・⑮マテキフルート工場見学記
(2005年4月)
・⑭Ph.ハンミッヒ木管フルート ノマタチューンナップ記
(2005年2月)
・⑬ベートーヴェン交響曲第9番「合唱」 アマオケ練習日記
(2005年2月)
・⑫新世界より&キャンディード アマオケ練習日記
(2004年12月)
・⑪ロイヤルコンセルトヘボウ管弦楽団2004年日本公演レポート
(2004年11月)
・⑩幻想交響曲&ラヴァルス アマオケ練習日記
(2004年7月)
・⑨ハイドン交響曲全104曲 完全制覇日記
(2003年11月より)
・⑧イスラエルフィルハーモー管弦楽団2003年日本公演レポート
(2003年12月)
・⑦シカゴ交響楽団2003年日本公演レポート
(2003年10月)
・⑥マーラー交響曲第5番アマオケ練習日記
(2003年7月)
・⑤ギルバート・キャプラン
(2002年8月)
・④月に1度はコンサートへ行こう企画2001年総括
(2002年3月)
・③ウィーンフィルハーモニー管弦楽団2001年日本公演レポート
(2001年10月)
・②マーラー交響曲第3番アマオケ練習日記
(2001年7月)
・①ベルリンフィルハーモニー管弦楽団2000年日本公演レポート
(2000年11月)